私の家は辺鄙な山村にあり、両親は畑を耕してどうにか生計を立てていました。私には3つ離れた弟がいました。ある日、私は女の子なら誰もが持っている柄物のハンカチがほしくて、父の引き出しからこっそり5毛のお金を持ち出しました。父はその日のうちにお金が減っているのに気がつき、私と弟を壁際に跪かせました。そして、竹の棒を手に、一体誰が盗んだのか白状しろと言いました。私はそのとき怖くてうつむいたまま何も言えませんでした。
父は「どちらも白状しないなら二人一緒にたたくぞ」と言うなり、竹の棒を振り上げました。すると、弟が突然父の手をつかみ、「お父さん、ぼくがとったんだ。お姉ちゃんじゃない。ぼくをたたいて!」と言いました。父が手に持った竹の棒は、無情に弟の背中や肩に何度も落ちました。父は息が切れるほどに怒り、たたき終わるとオンドルに座り込んで叱りました。「お前はそんな歳で家のものを盗むことを覚えたら、大きくなったらどうなる。お前のようなろくでなしはたたき殺してやる」
その日の夜、私と母は全身傷だらけの弟を抱いて寝ました。弟は一粒の涙も流しませんでした。夜中に私は突然大声を上げて泣き出しました。すると、弟が小さな手で私の口を押えて、「お姉ちゃん、泣かないで。もうぼくがたたかれて終わったんだから」と言いました。
私はそれ以来ずっと、あの時どうして自分がとったんだと白状することができなかったのかと悔やんでいます。それから何年経っても、弟が私をかばって竹の棒でたたかれる様子が鮮やかによみがえってきます。その年、弟は8つで、私は11でした。
弟は中学卒業と同時に県の重点高校に受かりました。私のほうも省都にある大学の合格通知書を受け取りました。その日の夜、父は庭にしゃがんでしきりにキセルを吸いながら、「二人とも本当に大したものだ」と、ぶつぶつつぶやいていました。母はそっと涙をぬぐいながら、「頑張ってもどうにもならない。どうやって学校へ行かすの?」と言いました。
弟は父の前に歩み寄ると、「ぼく、学校へ行かない。勉強なんか、もう十分だ」と言い出しました。父はバシッと弟の顔をたたきました。「お前はなんという意気地なしだ。わしは、家財道具を一切売ってでもお前たち二人を学校に通わせてやる」。そう言うと、一軒一軒お金を借りに回りました。
私は弟の赤く腫れた顔をなでながら、「あなたこそ勉強しなさい。男の子が勉強しなかったら、一生この貧しい山里から出られないんだから」と言いました。弟は私を見て頷きました。私はそのとき、大学に上がるのを止める決心をしていました。
ところが、翌朝日が昇らないうちに、弟はぼろい服を数枚とかさかさのマントウを何個か持って、こっそりと家を出て行きました。私の枕元には書置きがありました。
「お姉ちゃん、せっかく大学に受かったんだから、ぼくが働いて通わせてあげる。弟より」
私はその書置きを握りしめて、オンドルに伏せて声を上げて泣きました。その年、弟は17で、私は20歳でした。
私は父が村中から借りたお金と、弟が工事現場でセメントを運んで稼いだお金で、大学3年生になっていました。ある日、私が部屋で勉強していると、同級生が駆け込んできて、「梅子、同郷の人が訪ねて来たわよ」と教えてくれました。私を訪ねてくる同郷の人って誰だろうと思いながら、外に出てみると、弟でした。全身セメントと砂だらけの作業服を着た弟が待っていました。
「なんで、同級生に同郷人だなんて言ったの?」「こんな格好だろ。弟だって言うと、お姉ちゃんがみんなに笑われたらいけないと思って」
私は涙がこみ上げてきました。私は弟の服のほこりを払いながら、「誰が何と言おうと、あなたは私の弟じゃないの。どんな格好をしていたって、他の人がどんなに笑おうと関係ないわ」とむせびました。
弟はポケットから大切そうに、ハンカチに包んだ蝶々のヘアクリップを取り出し、私の髪にあてがいながら、「街の女の子はみんなこれを付けているんだよ。お姉ちゃんにも一つ買ってきてあげたんだ」と言いました。私はこらえきれず、大通りで弟を抱いて泣きました。その年、弟は20歳で、私は23でした。
私は初めてボーイフレンドを連れて家に帰りました。帰ってみると、何年も外れたままになっていたガラスが付いているし、部屋もきれいに片付いてほこり一つありませんでした。ボーイフレンドが帰ってから、私は母に「なんで家をこんなにきれいに片づけたの」と聞きました。母はすっかり老けて、笑うと顔が菊の花のようにしわくちゃになりました。「あの子が早めに帰ってきて片づけたんだよ。手の傷を見たかい。ガラスをはめるときに切ったんだよ」
私は弟の部屋に入り、ますます痩せてきた顔を見て、つらくなりました。ところが、弟はにっこり笑って、「初めてボーイフレンドを連れてきたんだし、街の大学生だろ。笑われたらいけないから」と言いました。
私は傷口に薬を塗りながら、「痛くない?」と聞きました。「大丈夫。工事現場では石が足に落ちて靴が履けないほど腫れても働くんだから……」。弟はここまで言うと、急に口をつぐみました。私は声を上げて泣きました。その年、弟は23で、私は26でした。
私は結婚して街に住んでいました。夫と相談して、両親を街に呼び寄せようとしましたが、二人はうんと言いませんでした。村を離れたら、何をしたらいいかわからないと言うのです。弟も「お姉ちゃんは、ご主人の両親の面倒をしっかり見なよ。お父さんとお母さんはぼくにまかせたらいい」と言って、反対しました。
夫は工場長に昇格しました。そこで、私は彼に相談して、弟を修理管理部に移らせようとしました。ところが、弟は修理工のままでいいと言って承知しません。
あるとき、弟は梯子に上って電線を修理していたところ、感電して下に落ち、入院してしまいました。私は夫と一緒に見舞いに行きました。弟のギブスをした足をなでながら、「管理職に就いたらと言っているのに承知しないから、こんなけがをしてしまって」と私が言うと、弟は真剣なまなざしでこう言いました。
「お姉ちゃんはどうしてお兄さんのことを考えないの?お兄さんは工場長になったばかりで、ぼくのように学歴のない人間を管理職にしてしまったら、お兄さんが何を言われると思う?」
夫の目から涙があふれました。私も泣きながら、「あなたに学歴がないのは全部私のせいだわ」と言いました。すると、弟は私の手を取って、「過ぎたことを今さら言うなよ」となぐさめてくれました。その年、弟は26で、私は29でした。
弟は30の時、農村の女の子と結婚しました。結婚式で司会者が弟に「最も敬愛する人は誰ですか」と聞きました。弟は迷うことなく即座に、「お姉ちゃんです」と答えました。
弟は、私でさえ忘れていたことを話し始めました。「小学校に上がったばかりのころのことでした。ぼくは毎日お姉ちゃんと隣村にある学校まで1時間かけて通っていました。冬のある日、家に帰る途中で、ぼくは片方の手袋を無くしてしまいました。すると、お姉ちゃんは自分の片方の手袋をぼくに貸してくれ、自分は片方だけはめて、長い道のりを歩いて帰りました。家に着いた時には、お姉ちゃんのその手は箸も持てないほどに凍えていました。それ以来、ぼくは一生お姉ちゃんを助けてあげると誓いました」
会場には拍手が巻き起こり、お客さんたちの目は私のほうに注がれました。
「私が生涯で一番感謝しているのは弟です」。一番喜ばしい席なのに、私は涙がとめどなくあふれてきました。







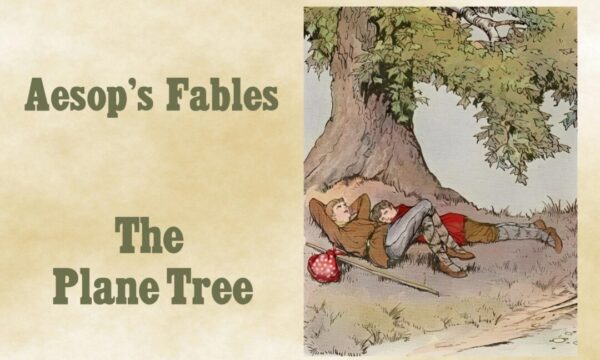









 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram


ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。