本当に何かをしたい人は、必ず方法を探し出します。特に、心から人を助けたいと思うとき、不思議と智慧が湧いてくることがあります。何かをしたくてもできない時、言い訳ばかりしていませんか?どんな時でも、必ずやり方はあるものです。
1953年11月13日、デンマークの首都コペンハーゲン。朝3時、消防署に一本の電話が入りました。その時、22歳の若い消防員のエリッヒさんは当直でした。 「もしもし!こちらは、消防隊です」
電話の向こうからは返事がなく、沈黙が続いていましたが、大きな呼吸音が響いていました。 すると、急に絞り出すような声が聞こえました。「助けて、助けて!私はもう、立ち上がれません!どんどん血が流れています!」
「慌てないでください、奥さん」。エリッヒさんは、落ち着いた声で応答しました。「私達はすぐに駆けつけます。あなたは今、どこにいますか?」
「分からないわ」
「あなたの家でしょうか?」
「ええ、私は家にいるわ」
「家はどこにありますか?」
「分からないの。めまいがひどくて・・・血が流れているわ」
「名前を教えてください!」
「名前も覚えていないの。頭をぶつけてしまって」
「電話を切らないでください」
エリッヒさんはすぐに別の電話を取り、電話会社にかけました。年配の男性が電話に出ました。
「電話番号を探しています。この電話番号が、今消防署にかかっているのですが、場所が分かりません」
「私は警備員です。今は週末で誰もいないし、番号を探せる人はいない」
エリッヒさんは仕方なく電話を切りました。彼はまた一つの考えが浮かび、女性に聞きました。「あなたはどうやって消防隊の電話番号を見つけましたか?」
「電話番号は電話機に書いてあるから・・・。でも、私が転んだ時にそれを引き下ろしてしまったわ」
「そこに他の電話番号がありませんか?」
「ないわ、他の番号はない・・・。早く来て下さい・・・」女性の声は、ますます弱くなりました。
しかし、エリッヒさんはあきらめずに、質問を続けました。「あなたは今、そこからどんなものが見えますか?」
「窓・・・窓が見えるわ。窓の外に街灯がある・・・」
よし!エリッヒさんにはひとつの考えが浮かびました。「街灯が見えるなら、彼女の家は大通りに向いているに違いない。それに、あまり高くない階に住んでいるだろう」
「どんな窓ですか?」彼は引き続き質問しました。「正方形の窓ですか?」
「いいえ、長方形です」 。それなら、古い住宅街に住んでいるはずです。
「電気をつけましたか?」
「はい、つけました」
エリッヒさんはまた質問をしましたが、女性は返事をしなくなりました。 早く行動しないといけません! しかし、彼女の居場所が分かりません。 エリッヒさんはすぐに上司に電話をかけ、このことを報告しました。 上司は、「どうしようもない。その女性を見つける方法はない」と少し不機嫌に言いました。しかし、エリッヒさんは諦めませんでした。人の命を助けることが、消防隊員の最も重要な責務です。
その時、1つの狂気じみた考えが彼の頭に浮かびました。すべての消防車を、サイレンを鳴らしながら出動させるのです。 上司は、びっくりして言いました。「町中の住民が、核戦争が起きたかと思うだろう!コペンハーゲンのようなこんな大都市でそんなことをやらかしたら、大変なことになる。しかも深夜だぞ!」「お願いします!」エリッヒさんは懇願しました。「私達は早く行動しなければなりません。そうでなければ、後で何をしても無駄です!」
上司はしばらく沈黙した後、答えました。「よし、いいだろう。私が責任を取る。すぐにそっちへ向かう」 。15分後、20台の消防車がサイレンを鳴らしながら町中を走りました。
女性はすでに話ができなくなっていましたが、、エリッヒさんには彼女の呼吸の音が聞こえます。 10分後、エリッヒさんは叫びました。「電話の中でサイレンの音が聞こえます!」
隊長はトランシーバーですばやく伝達しました。「1号車、サイレンを消してください」 エリッヒさんは、「電話の中でまだサイレンの音が聞こえます」と言いました。
「2号車、サイレンを消してください!」 「まだ聞こえます……」。12号車のサイレンを消した後、エリッヒさんは叫びました、「今、聞こえなくなりました!」
隊長は、12号車にサイレンを鳴らすよう命じました。
「今、聞こえますが、どんどん遠くなっています」
「12号車、反対方向に走ってください」
「だんだん音が近づいてきました。今、音がとても大きく聞こえます。かなり近いところに着いたはずです」
「12号車、電気がついている窓を探してください」
隊員は、答えました。「たくさんの家が灯りをつけています。皆、何事かと窓から覗いているので・・・。」
「拡声器を使って呼びかけて下さい」
隊員が、話しました。「皆さん、私達は命の危機にさらされている、一人の女性を探しています。彼女は電気がついている部屋にいますので、皆さんは家の電気を消して下さい」
一つの窓を除き、すべての窓は黒くなりました。 暫くすると、エリッヒさんは電話越しに、消防隊員が部屋に突入する音を聞き、その直後、隊員の男性がトランシーバーで話しているのが聞こえました。「女性は意識を失っているが、脈拍はまだあります。すぐに彼女を病院に搬送します。助かる見込みがあるようです」
こうして、意識を失っていたヘレン・ソエンダーさんは救われました。彼女は蘇って、数週間後に記憶が戻ったそうです。
(翻訳編集・知行)







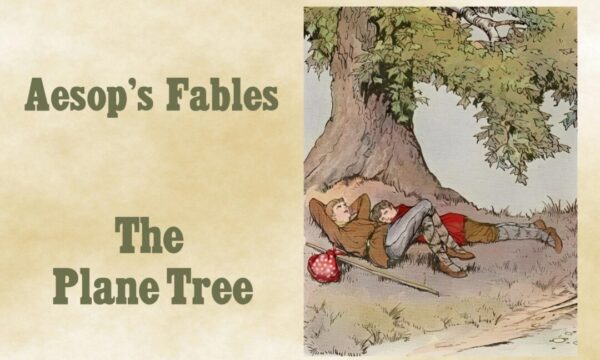








 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram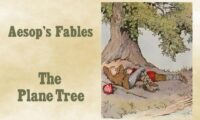




ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。