嘗聞玉泉山、山洞多乳窟、仙鼠如白鴉、倒懸清渓月、茗生此中石、玉泉流不歇、根柯灑芳津、採服潤肌骨、叢老巻緑葉、枝枝相接連、曝成仙人掌、似拍洪崖肩、挙世未見之、其名定誰伝、宗英乃禅伯、投贈有佳篇、清鏡燭無塩、顧慙西子妍、朝坐有余興、長吟播諸天
題名:族姪(ぞくてつ)の僧、中孚(ちゅうふ)が玉泉(ぎょくせん)の仙人掌(せんにんしょう)茶を贈るに答える。
嘗(かつ)て聞く玉泉山、山洞に乳窟(にゅうくつ)多し。仙鼠(せんそ)白鴉(はくあ)の如く、倒(さかしま)に清渓(せいけい)の月に懸(かか)る。茗(めい)此の中の石に生じ、玉泉流れて歇(や)まず、根柯(こんか)に芳津(ほうしん)灑(そそ)ぎ、採(とり)服(ふく)すれば肌骨(きこつ)を潤(うる)おす。叢(そう)老いて緑葉を巻き、枝枝(しし)相い接して連なる。曝(さら)して仙人掌と成せば、洪崖(こうがい)の肩を拍(たた)くに似たり。世を挙げて未(いま)だ之(これ)を見ず。其の名定めて誰(たれ)か伝う。宗の英は乃(すなわ)ち禅伯(ぜんはく)、投贈(とうぞう)佳篇(かへん)有り。清鏡(せいきょう)無塩(むえん)を燭(てら)し、顧(かえり)みて西子(せいし)の妍(けん)に慙(は)ず。朝坐(ちょうざ)余興(よきょう)有り、長吟(ちょうぎん)諸天(しょてん)に播(し)く。
詩に云う。我が一族の甥(おい)にあたる僧侶の中孚が、玉泉の名茶である「仙人掌」を贈ってくれたことに答えた詩。かつて玉泉山のことを聞いたことがある。その山の洞窟には鍾乳洞が多くあり、そこには白いからすのように年取った蝙蝠(こうもり)が、清渓の月の光のなか、逆さにぶらさがっている。茶の木が、その洞窟のなかの石に生えているのだが、その傍らに玉のような泉が絶えず流れている。茶の木の根や枝には、いつも香り高い水が注いでいるため、その茶を摘んで服せば肌や骨までが潤うのだ。茶の木が年を経ると、緑が一層しげり、茶葉が巻いたようになって、枝と枝が交わって連なるようになる。それを摘んで日に晒すと「仙人掌」になるが、その茶の味のすばらしさといったら、思わず仙人の洪崖の肩をたたいてほめたくなるほどだ。世の中には、まだ知られていない。その名「仙人掌」を一体誰が伝えたのだろう。我が一族の英才である中孚和尚どの、この度は、すばらしい詩(と茶)を私に贈ってくれた。まるで、清らかな鏡が、無塩の醜女(李白自身をさす)を照らし出すようで、西施(せいし)の美しさの前では(我が身が)恥ずかしい。中孚どのは、朝の勤行の合間に、たしなみとして詩を吟じ、なんと宇宙まで響き渡らせるのだなあ。
李白(701~762)の詩であるから、また酒かと思ったら、今回は茶がテーマである。李白おそらく43歳ごろ。都長安へ呼ばれる前の、世間に「李白とかいう、奇妙な詩人がいるぞ」と評判が立ってきたころの作品らしい。
仙人掌は、今の中国語ではサボテン(ウチワサボテン)を指すが、この詩中のそれはサボテンではなく「仙人掌」という名の茶である。ネットで見ると、サボテンを原料にした「茶外茶」で仙人掌茶という商品があるらしいが、もちろんそれのことではない。
さて、改めてこの詩を読むと、李白が中孚という僧侶から詩と茶を贈呈されたので、その礼もかねて、儀礼的なお返しの詩を送ったものらしい。中孚という僧侶については、よく分からない。ただ、李白が「我が一族の英才」にしていることから、出家前の俗姓が「李」だったことは確かだろう。姓は同じだが、おそらく同族ではない赤の他人で、そこは李白が作詩上の色付けをしているに違いない。人に贈る詩なので、かなり演出もしている。
茶は、中国では紀元前から飲まれていたので、唐代に至っては、すでに長い茶の歴史をもっていたはずだ。日本へ初めて茶がもたらされたのは遣隋使の天平時代と思われるが、茶を飲む習慣が日本に定着するには至らなかった。
12世紀になって臨済宗の禅僧・栄西(えいさい 1141~1215)が渡宋。禅の修行のなかで必要とされる喫茶を、入手した茶木の種とともに日本にもち帰った。これが武家社会にも広く伝わって、以後、日本人の飲茶は盛んになる。栄西の南宋滞在は1168年の4月から9月と長くはなかったが、日本にもたらした功績は、衰亡した禅宗の再興のみならず、大きいものがある。
李白に話をもどす。酒好きの李白にとって茶などはどうでもよいものであって、本当に茶に関心があって、この詩を詠んだわけではあるまい。茶は、李白にとって心地よい眠気や酔いを覚ましてしまう。ただ、相手から詩と茶を贈られたので、その返礼をしたまでである。そういう意味で、李白から相手への「ほめ上げ」がちらりと見えて、おもしろい。
(聡)









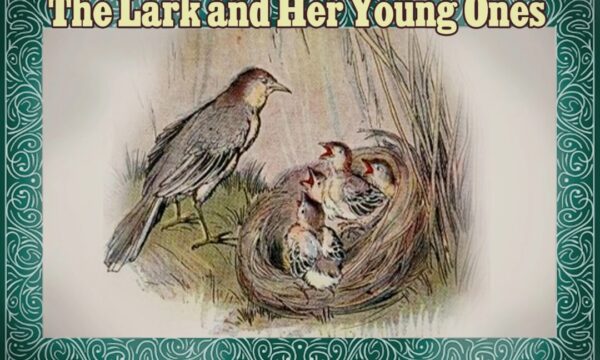
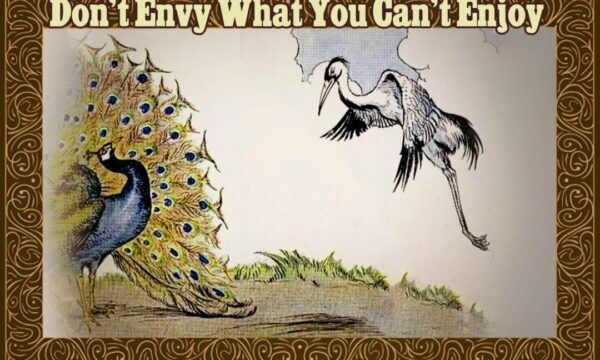








 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram




ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。