中国の史書によると、三皇五帝(さんこうごてい)の時代、中国の大地は仙人たちの足跡で覆われていました。仙人が現われるときには、様々な神獣や神鳥、吉祥を意味する雲・祥雲も附随します。夏商周時代から現代まで伝えられている文様の一部にこの様子が見受けられます。雲紋、夔紋、鳳凰紋、蔓草紋、饕餮紋、連珠紋などの文様は、各王朝の青銅器、陶器、玉器、建築彫刻、服飾の刺繍などの工芸品に多く見られ、数千年にわたり独特な文様の体系が生み出されてきました。
これらの文様について詳しく見てみましょう。
1. 雲紋

雲紋または祥雲紋は、よく使われます。勾雲紋、朵雲紋、雲頭紋、流雲紋などの種類があります。「祥雲」とは、もともと七色の彩雲のことを指し、仙人はこの雲に乗って現われます。古代の帝王たちも常に祥雲で身を守られていると信じられていました。徳の高い人は天界の守護を賜るからです。
時を経て、祥雲は次第に吉祥のイメージとなり、詩歌や物語でしばしば言及されるようになりました。
雲の上に天界があり、天界には東皇太一様と美しい仙女たちが住んでいるとされていました。雲紋がこれほどまでに好まれる理由は、天界への憧れにあるのかもしれません。
2. 雲雷紋
雲雷紋は連続する幾何学模様です。その中の四角い回紋は雷の象徴で、丸い回紋は雲の象徴です。四角と円の交差は、天空にある雲と雷を象徴します。
『易経』に、「雲,雷,屯;君子以經綸」(雲雷は、屯なり。君子もって経綸す)と書かれています。雷が鳴り始めると、物事が始まる芽生えとして、君子は国家経綸(けいりん)の大志をおこすという意味です。殷周王朝期の青銅器には、荘重で優雅な雲雷紋が多く刻まれています。以降、雲雷紋を基に、色々な回紋が派生しました。永遠と続く回紋は、「尽きない富」を表すとも言われています。
3. 鳳紋

鳳凰は天界の鳥です。『山海経』『淮南子』『庄子』で「鳳凰」を詳しく描写しています。太平の世にたまにしか姿を現さない鳳凰は、梧桐にしか棲まず、醴泉の水しか飲まず、気高く美しい神鳥だと伝えられてきました。
商王朝期(紀元前1600~1046年)以降の様々な遺物に、鳳凰の様々な姿が見受けられます。著名なものとして、三千年以上前に用いられた殷王武丁の妻・婦好(ふこう)の副葬品―鳳凰をかたどった玉器―が挙げられます。
それ以降の各王朝の芸術や工芸品に益々精巧で華やかな鳳凰の姿が見られるようになります。多くあるのは飛鳳(飛ぶ鳳凰)、立鳳(枝に留まる鳳凰)、団鳳(群れをなす鳳凰)、鸞鳳(らんぽう:つがいの鳳凰)などです。龍と一緒の鳳凰は、皇后を意味します。
4. 龍紋

中国の古伝、地方の歳時記などに、龍 が地上に現れたという記述が繰り返し出てきます。文物、絵画、彫刻での龍の描写には多少の違いはありますが、概ね一貫しています。つまり、鹿のような角、鯉のような鱗、鷹のような爪、蛇のような体です。
龍は、雲霧に乗り風雨を呼ぶ神獣だと、信じられていました。古代中国では、至高の龍は男気と帝王の象徴とされていました。
芸術作品や装飾品では、龍紋は鳳紋、雲紋、水紋、宝珠などと合わせ、吉祥文様として用いられています。
「龍生九子(りゅうせいきゅうし)」と言われるように、龍の九つの息子たちも独特で、多くの龍紋を生み出しています。春秋戦国時代(紀元前771~221年)の青銅器に見られる「蟠螭(ばんち)紋」の龍には角はなく尻尾も丸まっています。一方、「夔龍(きりゅう)紋」の龍神は一本足で、角があり、口を開けています。
清王朝 (1644~1911年)では皇帝たちは五爪坐龍紋や立龍紋を好み、民間では男女を問わずに三爪団龍紋、四爪団龍紋が好まれました。そして九龍柱の装飾には、常に天昇している昇龍紋が用いられます。佛教文化では、龍は天界を生きる命で、八部衆の中の一つであり、佛法を守護する護法善神と伝えられています。
神伝文化の一部である多種多様な伝統文様は「天人合一」の理念を内包しています。天界からの文様はほかにもたくさんあります。例えば、仏様の慈悲と高徳を象徴する卍字紋、吉祥と善徳を伝える神獣を代表する麒麟紋、そして西王母様の頭上に輝く髪飾りを象徴する方勝紋。挙げればきりがありません。
――「神韻芸術団」(日本語ホームページ)より転載









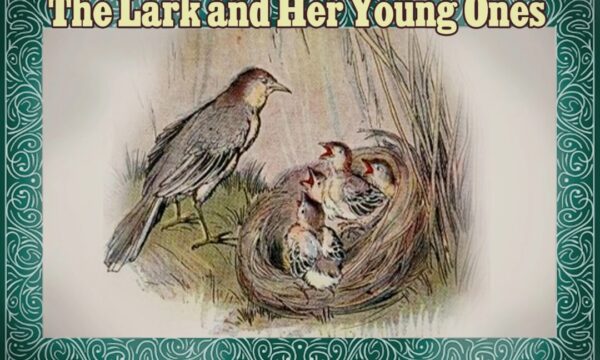
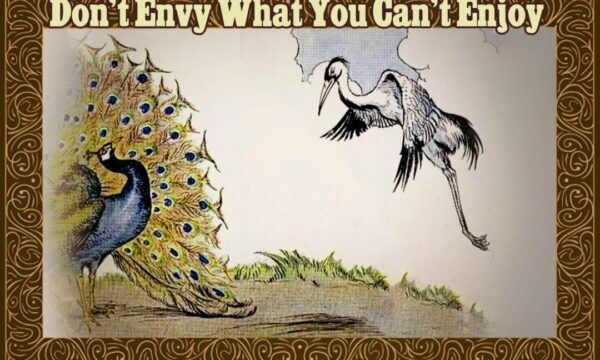








 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram




ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。