夏6月、つまり旧暦の5月は、昔から暑さと湿気が最も強い時期とされています。この時期は、体の消化器官である脾(ひ)や腎臓が特に弱りやすく、腹痛やむくみなどの不快な症状が出やすくなります。そのため、脾を元気にし湿気を取り除くこと、余分な水分を尿として排出しむくみを解消すること、腎臓をサポートし心を健康に保つ食材を摂ることが重要です。
では、これらの効果を持つ食材にはどのようなものがあるでしょうか? 小豆、黒豆、はとむぎの3つの穀物は、湿気を取り除き、利尿作用を促し、脾を強化し、腎臓をサポートする効果が特に優れています。これらの食材は体内の不要な水分や湿気を効率よく排出し、足や顔のむくみを解消します。特に小豆は、心臓を強くし血液を健康に保つ効果があり、血糖値、血圧、血脂肪を下げる効果も認められており、「赤いダイヤモンド」とも呼ばれることがあります。
小豆の素晴らしい効果を中心に紹介し、他の食材と組み合わせた簡単で効果的な食事療法をいくつかご提案します。
腎臓の形そっくり! 小豆の力でスッキリむくみ解消
小豆は腎臓の形に似ているため、中国の伝統医学では「同じ形のものを使って補う」という理論に基づき、腎臓の機能を補い、尿の排出を助けるとされています。
中医学の見解では、腎臓は体内の水分代謝を司っています。水分の代謝が食事の問題や過労など、さまざまな原因で影響を受けると、腎臓の機能に問題が生じ、排尿量や回数が減少し、異常な下痢を引き起こすことがあります。
この原理はシンプルです。体内の廃液は尿として排出されるべきですが、腎臓に問題が生じると排尿が減ります。体は自己救済のために排水機構を変え、本来尿で排出されるべき廃液を便として排出するようになり、下痢を引き起こします。この時、無理に下痢を止める薬を服用すると、水分が適切に排出されず、重度の水分代謝障害を引き起こします。最も根本的な対策は、腎臓の正常な排尿機能を回復させることです。
小豆は腎機能を補い、強化することで、余分な水分を排出し、むくみを解消する助けとなります。数千年前には、伝説の医師・扁鵲(へんじゃく)が小豆を黒豆や緑豆と組み合わせて、むくみ治療の有名な処方として用いていました。

小豆の甘みで脾を元気にしよう
伝統的な中医学では、「甘い」という味覚は単なる甘さとは異なります。「甘い」という字は「舌」と「甘」から成り立っており、舌ではっきりと感じる強い甘みを意味します。そのため、非常に多くの量でなければ「甘さ」と感じられないことが多いです。医薬学での「甘い」は五行の「土」の属性を持ち、脾と胃の機能に合致しているため、脾を強化し、自然界の法則に従って物質が集まるように作用します。
脾は五行で「土」に分類され、自然界の湿気と関連が深く、湿気によって消化の問題が起こりやすいです。体内の水分と湿気が多くなると、下痢がひどくなることがあります。小豆は脾と胃の水分の消化と吸収を助け、体内の余分な湿気を排出し、むくみや体重の増加を抑える効果があります。
小豆の力で心臓と血液もサポート
小豆の色は赤く、五行では「火」に相当し、心臓と関連があります。心臓は血液の流れを管理しているため、小豆は心臓を強化し、血液の栄養バランスを整え、血流をスムーズにします。これは自然が与えた黙示的な知恵であり、色がその効果を示しています。心臓と血管の健康を整え、血液の流れを良くし、血圧を正常に保つことで、高血圧や糖尿病、高脂血症などの問題を自然に解決します。
また、小豆は心の熱を冷まし、暑さを和らげ、精神を落ち着かせ、良い睡眠を促す効果があります。
現代研究による確認
利尿とむくみ解消
最新の研究で、小豆がカリウムとサポニンを豊富に含んでいることが分かりました。乾燥した小豆100グラムには約1300mgのカリウムが含まれており、これはレーズンの約2倍です。カリウムは体内の余分なナトリウムを排出し、尿の量を増やして体内の余分な水分を減らす効果があります。サポニンも利尿効果があり、体のむくみを和らげる手助けをします。
血圧、血糖、血中脂質の低下
小豆にはごぼうの2倍以上の食物繊維が含まれており、アントシアニンなどのポリフェノールも豊富です。これらは糖の吸収を遅らせて血糖値を調整する効果があります。また、抗酸化物質が血中脂質を下げるため、高脂血症の予防や心血管系の保護、高血圧リスクの低減に役立ちます。
抗酸化と抗炎症
小豆には、大豆の6倍、赤ワインの1.5倍の量のポリフェノールが含まれており、非常に高い抗酸化作用を持っています。これにより、体内の有害なフリーラジカルを中和し、細胞を保護して肌の潤いと若さを保つ効果があります。また、フラボノイドは抗炎症作用を持ち、慢性炎症を軽減し、様々な慢性病の予防に役立ちます。
小豆は心の熱を冷まし、血液を冷やし、赤く腫れた炎症を自然に治します。その性質は穏やかで、消炎効果がありながら体に優しいため、体力が落ちている人にも適しており、理想的な健康食品です。
レシピその1 小豆と黒豆のはとむぎ粥

<材料>
小豆 50グラム
黒豆 50グラム
はとむぎ 50グラム
白米 100グラム(糖尿病の人は玄米や山芋に置き換え可能)
水 適量
<作り方>
1.小豆、黒豆、はとむぎをそれぞれ洗い、2~4時間水に浸します。白米も洗っておきます。
2.鍋に適量の水を入れ、小豆、黒豆、はとむぎを加えて沸騰させ、その後弱火で60分煮ます。次に白米を加え、全ての材料が柔らかくなり粥になるまで煮続けます。お好みで、食べる時に少し砂糖を加えて味を整えることもできます。
<健康効果>
黒豆はその黒い色から五行で水に関連し、腎臓の機能を補強するとされています。利尿作用に優れ、むくみを解消する効果があります。
はとむぎは脾を強化し湿気を取り除くので、この粥は腎臓の機能を助け、体内の余分な水分を排出し、脾を強化して湿気を取り除く効果があります。
この粥は、腎虚によるむくみ、脾虚による湿気の多さ、血圧、血中脂肪、血糖のある方に適しています。
レシピその2 小豆とトウモロコシのひげ茶

<材料>
小豆 30グラム
市販のとうもろこしひげ茶のティーバッグ 1個
水 適量
<作り方>
1.小豆を洗い、水に1時間浸します。
2.鍋に適量の水を入れ、小豆を加えて強火で沸騰させ、その後弱火で30分煮ます。
3.市販のとうもろこしひげ茶のティーバッグをカップに入れ、小豆の煮汁を注ぎます。数分間抽出したら、ティーバッグを取り出して出来上がりです。
<健康効果>
とうもろこしのひげは利尿作用があり、むくみを解消し、血圧と血糖値を下げる効果があります。
小豆と組み合わせることで、むくみの緩和と血圧、血糖、血中脂肪の調整に役立ちます。
(翻訳編集 華山律)









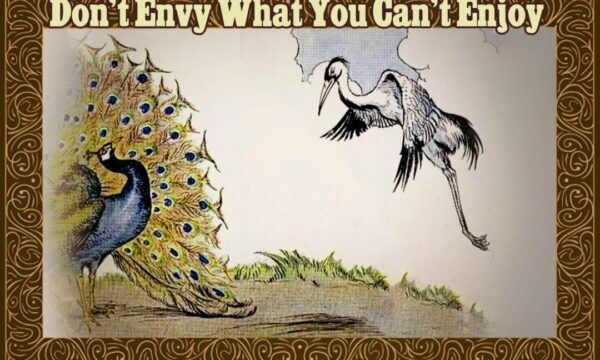










 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram




ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。