古代中国には、神々や仙人が共に居住し、神が伝える文化が生み出されました。このため、初期の中国史と神話は互いに絡み合っています。
龍は、中国の伝説では様々な形や大きさで現れます。慈悲深いものも邪悪なものも存在します。天高くそびえ立つかと思えば、海底深くに潜り込みます。鳳凰や真珠を弄びます。智慧、皇帝、人間世界を超えた次元の象徴です。
中国の良い龍は、九つの資質を備えた聖なる生き物です。水、火、風、氷を操り、陸、海、空で生息でき、いろいろな姿に変身し、雲のなかで呼吸できるなど、実に広域に超自然的な能力を備えます。
龍王は、エビの兵士、カニの将軍、亀、鯉などを指揮下に持ちます。

龍王とは?
大海から小川、滝、井戸まで、あらゆる形の水は、龍が管轄しています。伝説によると、創造の女神である女禍(じょか)は、4つの龍に東の大陸を囲む四つの海の管理を委託しました。それ以来、龍王は海底に水晶宮を備えます。
龍王の水晶宮は、地上の水晶宮を真似て作られましたが、海中ならではの特徴がありました。瑪瑙(めのう)の城門が、半透明の水晶の建物内をのぞかせ、板葺き屋根は虹色の二枚貝の殻で作られ、浅く浮き彫りにされた龍のとぐろが真珠を埋め込んだ柱を飾ります。龍王は、きらめく宝石で飾り立てられた翡翠の冠を戴いていました。建物全体を通して、アワビの殻を敷き詰めた歩道が桃色のサンゴの庭園へと導きます。繁茂した海藻が海水の流れに揺られています。
東西南北それぞれの海洋をおさめる龍王たちは、龍の頭、人の胴体を持ち、帝王の礼服に身を包みます。龍王は、各々の海洋の地域と生命を守護しているのです。玉皇太帝の指示に従い、周辺の土地の天候や雨量をコントロールします。
多くの歴史書にこれらの龍王のことが書かれています。『封神演義』と『西遊記』の話がよく知られています。

西遊記の中の龍王
『西遊記』の一節「龍宮でひと騒動を起こす孫悟空」では、東海龍王が登場します。いたずら者の孫悟空が、年老いた猿の提案に従い、自分に見合った武器を探しに東海龍王の龍宮に行きます。悟空は海に飛び込み、龍宮でひと騒動おこし、6トン以上もある金の如意棒をもらって花果山の滝の背後に隠れた自分の洞窟にさっさと戻りました。
めでたしめでたしと思われるでしょう。そうでもないのです。原作では、孫悟空はこれで満足しません。完璧な武器を手にした後、ずうずうしくも、パリッとした服を求めます。しつこくせがまれた東海龍王は、太鼓と鐘を鳴らして他の海洋を統治する三名の龍王を集め、孫悟空を金の鎖帷子(くさりからびら)の鎧(よろい)、鳳凰の羽で飾られた兜(かぶと)、蓮の糸で編んだ雲を歩ける履き物で着飾らせます。きらびやかで人目を引く服装に身を包み、ようやく、このやんちゃな猿は水晶宮を後にします。

四番目の弟子
観音菩薩が三蔵法師の守護を選んでいるとき、1匹の龍に遭遇します。西海龍王の三太子である玉龍が、父の貴重な珠玉を誤って焼いてしまい処刑されるところでした。
観音菩薩は、この悲しげな龍が三蔵法師の馬となるよう指名し、取経の旅が終わった時点で自由と元の姿が取り戻せることを約束します。最終章で、王の血統を引く気高い馬は「龍を変化(へんげ)させる水」に浸かり、角、金鱗、銀のヒゲを取り戻し、立派な称号も授かります。
一行を救済する北海龍王
孫悟空や三蔵法師とお供の者たちを受け入れた龍王たちは、取経の旅路で何度か一行を救済します。一行が獅駝嶺(しだれい)で怪物に捕らえられ、巨大な蒸し器にいれられるという話があります。三蔵法師の肉を食べると不死の体になるため、三蔵法師はあらゆる邪悪に命を狙われます。
幸いにも、孫悟空が、氷と雪を司る北海龍王を呼び寄せます。キン斗雲に乗ってやってきた龍王は、凍てつく風に変化(へんげ)し、煮え立つ釜の火から三蔵法師の一行を守ります。三蔵法師の一行は、邪霊の餌食になる一歩手前で救われたのです。
『封神演義』の中の龍王 海を騒がせた後の話
『封神演義』の一節では、哪吒が邪悪の龍を斬り殺すところで幕が下ります。この龍は東海龍王の息子だったのです。
龍王とその兄弟たちは、哪吒の町に洪水を引き起こすと脅します。さらに玉帝に訴え、哪吒の家族に償いを要求します。皆を救うため、哪吒は責任をとって自害します。この哪吒の孝行に感銘した龍王は、復讐心を捨て水晶宮に戻ります。
話はこれで終わりません。道家の師である太乙真人(たいいつしんじん)が、蓮の花に金丹を入れて、哪吒はこれまで以上に立派に復活します。
中国の神話や小説では、龍と哪吒がさらに多くの冒険を、無数の登場人物を交えながら展開していきます。波乱に富んだ英雄たちの話はまた次の機会にご紹介しましょう。
――「神韻芸術団」(日本語ホームページ)より転載









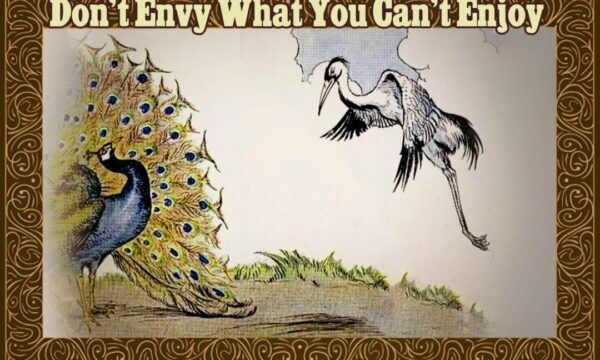









 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram




ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。