1876年にトマトから初めて抽出されたリコピンという色素の存在を研究者たちはかなり以前から知っていましたが、その健康効果が注目されるようになったのは、比較的最近のことです。
研究者たちは、リコピンがうつ病の治療に役立つかどうかを調べ、そこでリコピンは、トマトやグアバなどの赤やピンク色の果物に含まれるカロテノイド系の天然抗酸化物質であることを突き止めました。また、より広い視点からは、抗酸化物質を多く含む植物性の食品全般が、うつ病に対して効果があるかどうかも調べました。
リコピンと心の健康との関係
不安やうつなどの心の不調は、体内の抗酸化物質のレベルが低いことと関係しているとされています。慢性的なストレスは、視床下部―下垂体―副腎(HPA)軸を過剰に活性化させます。
このHPA軸は、体のストレス反応をコントロールする重要な脳内システムであり、その活性化によってストレスホルモンが増加します。ストレスホルモンの増加は、酸化ストレスを引き起こし、脳細胞を傷つけます。特に影響を受けやすいのは、感情の調節に深く関わる「海馬」と呼ばれる脳の部位です。
2024年に『ジャーナル・オブ・アフェクティブ・ディスオーダーズ(Journal of Affective Disorders)』に発表された黄疸の研究では、血液中の特定のカロテノイド(リコピンを含む)の濃度が高い人は、うつ症状のリスクが低い傾向にあることが示されました。この研究では、7,000人以上の成人のデータを分析し、カロテノイド濃度が高い人ほど、うつ症状の発症率が低いという結果になりました。
さらに、複数のカロテノイドの中でもリコピンは特に安定した関連性を示し、血中リコピン濃度が高まるほど、うつ症状のリスクが一貫して下がる傾向が見られました。リコピンには、摂取量が一定の範囲を超えた時点で効果が止まるような限界がなく、摂取量が増えるほど効果が向上するという点で、他のカロテノイドとは異なります。つまり、リコピンの摂取量が多いほど、より良い精神状態に結びつくということです。
また、別の系統的レビューおよびメタアナリシスでは、12件の研究(計3万3,000人以上のデータ)を分析した結果、リコピンを含む抗酸化物質が、酸化ストレスの軽減や脳のダメージ予防を通じて、うつリスクの低下に貢献している可能性が示されました。
「酸化ストレスの影響による症状に対しては、リコピンのような抗酸化物質が助けになるかもしれません。さらに重要なのは、酸化ダメージを引き起こすストレス要因との接触を減らすことです」と、TaperClinic創設者であり、元FDA医務官・精神科医のヨーゼフ・ウィット=ドーリング(Josef Witt-Doerring)氏が『大紀元時報』のメール取材で語りました。
私たちの食生活は、心の健康に深く影響を及ぼします。不健康な脂肪分や加工食品を多く含む食事は、炎症や酸化ストレスを引き起こし、うつリスクを高める原因になります。一方で、果物や野菜などの植物性食品や、リコピンのような抗酸化物質は、炎症を抑え、脳の健康を保つことで、うつ症状の緩和につながるとされています。
1万人以上のデータを含む別のメタアナリシスでは、うつ症状が慢性的な炎症状態と深く関係していることが明らかになっています。うつ病患者は、CRP値やIL-6などの炎症マーカーが常に高いレベルを指し、炎症がうつ病に重要な役割を果たしていることが示唆されています。また、食事の質を改善し、とくに植物性食品の摂取を増やすことが、うつリスクを下げる効果があることも、研究で示されています。
「何の前触れもなく突然うつのような症状を感じた人にとって、食生活を変えることは大きな効果をもたらします」とウィット・ドーリング氏は述べています。
彼は、いわゆるパレオ(原始人)式の食事療法を取り入れた患者に、著しい健康改善が見られたと話します。「それは、グルテン、大豆、乳製品といった炎症を引き起こしやすい食材を排除する事で、血糖値の乱高下を防ぐことにもつながっている」と彼は付け加えました。
作用の仕組みと最新の研究結果
リコピンは脂溶性の抗酸化物質であり、血液脳関門を容易に通過することができるため、脳の健康を保護・支援する働きがあります。研究では、リコピンが環境中の有害物質や、高脂肪の食事による脳への悪影響を和らげるのにも役立つことが示されています。
「リコピンは活性酸素(フリーラジカル)を除去し、炎症を抑えることで、神経細胞を守り、脳内の化学反応の安定に寄与する可能性があります」
――米国ニューロニュートリションセンター(Neuronutrition Centers of America)創設者であり、米国国家神経栄養学会(National Academy of Neuronutrition)会長の栄養神経学者ティモシー・フリ(Timothy Frie)氏が、『大紀元時報』の取材に対して語りました。
フリ氏はさらに次のように述べています。 「リコピンの抗酸化作用による効果は、うつ症状の緩和に役立つと考えられますが、これはあくまでうつ病の複雑な生化学的仕組みの一部であり、万能薬ではありません」
酸化ストレスの軽減とは、有害な分子である活性酸素(ROS)による細胞への損傷を防ぐために、体が抗酸化物質や酵素を使ってこれらを中和し、健康な状態を保つ働きのことを指します。このバランスが保たれることで、体への負担が軽減されます。
動物実験では、リコピンが神経細胞や脳細胞のつながり(シナプス)を強化することで、うつ症状を緩和する効果が確認されています。2025年に行われた研究では、リコピンが脳内の接続を保護し、ストレスによって損傷を受けたマウスの脳を回復させる効果があることが証明されました。
別の動物実験では、リコピンがバランスを整えることによって腸と脳の健康をサポートすることもわかっています。マウスに40日間リコピンを投与したところ、腸の損傷や炎症が軽減され、不安やうつなどストレスに関連する行動の改善も見られました。
腸と脳は「腸脳軸(ちょうのうじく)」と呼ばれる経路で密接につながっており、研究によれば、うつ病の患者は健康な人と比べて腸内細菌の構成が異なっていることが多いとされています。不健康な腸内環境は炎症を引き起こし、それが脳機能に悪影響を与え、感情の変化やうつにつながることがあります。
肥満や糖尿病等、代謝障害がある「炎症レベルが高い」患者は、栄養による介入から最も大きな恩恵を受けられる可能性があります」と、前FDA医務官で精神科医のドーリング氏は語ります。
「炎症や代謝の問題が精神的な健康と密接に関わっているため、食生活の改善と抗酸化物質の摂取量を増やすことが、症状改善の第一歩となり得ます」と彼は付け加えました。
リコピンを多く含む主な食品
トマトは、リコピンを最も豊富に含む食品のひとつです。リコピンは、生のトマトだけでなく、加工されたトマト製品にも含まれており、例えばトマトケチャップ、トマトジュース、ソース、フルーツジュース、スープなどが該当します。
研究によれば、リコピンは生のトマトよりも加熱調理されたトマトのほうが吸収されやすいことがわかっています。また、温室で育てたトマトよりも、露地栽培のトマトのほうがリコピン含有量が高い傾向があります。
リコピンを含むその他の食品(100グラムあたりの目安量)は以下のとおりです:
• カボチャ(0.38~0.46mg)
• サツマイモ(0.02~0.11mg)
• ピンクグレープフルーツ(0.35~3.36mg)
• ニンジン(0.65~0.78mg)
• ピンクグァバ(5.23~5.5mg)
• スイカ(2.30~7.20mg)
• アンズ(0.01~0.05mg)
• パパイヤ(0.11~5.3mg)
• ローズヒップ(0.68~0.71mg)
栄養神経学者のティモシー・フリ氏は、リコピンはサプリメントとしても摂取可能ですが、最も理想的なのは食品から摂ることであり、食品には脳の健康をサポートするポリフェノールや他の栄養素も含まれていると述べています。さらに、リコピンは脂溶性であるため、健康的な脂肪と一緒に摂取することで吸収がより良くなります。
また、食事以外にも、うつ症状の改善には生活習慣の見直しが効果的です。栄養で心の健康を整えたい人には、以下のような方法をお勧めします。
• 血糖値を安定させることに意識を向ける
• 炎症を引き起こす食品の摂取を減らす
• 睡眠の質を改善する
• 適度な運動を取り入れる
• 隠れた健康問題や慢性的なストレスに目を向ける
「大切なのは、根本的な原因に目を向けることです。もし誰かのうつ症状が、長期的な孤独感、仕事のストレス、あるいは薬物の乱用からきているのであれば、リコピンだけでは十分な効果は期待できません」と
精神科医ヨーゼフ・ウィット・ドーリング氏は語ります。
「リコピンの摂取を増やすことは、比較的安全で有益な変化です。ただし、過度な期待を持たずに取り入れることが大切です。うつ病を“治す”単一の栄養素というものは存在しません。それでも、ほかの生活習慣の改善と組み合わせることで、精神の健康に大きな影響を与えることは十分に可能です」
(翻訳編集 華山律)




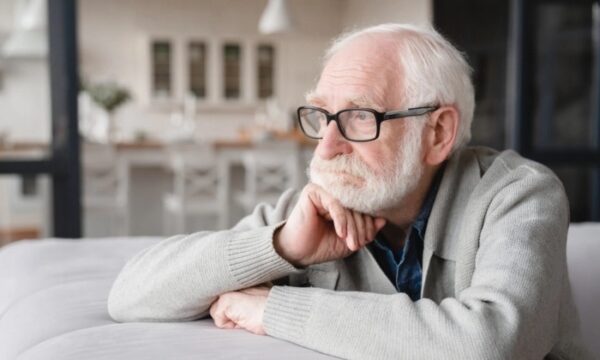


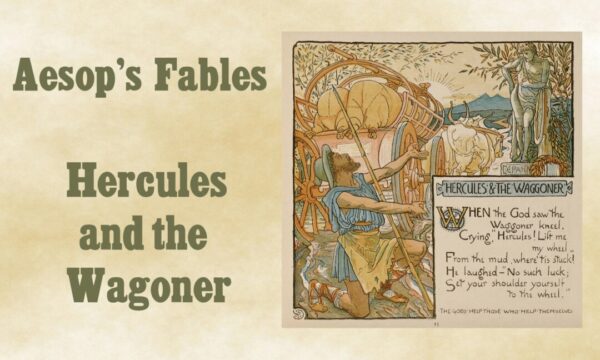
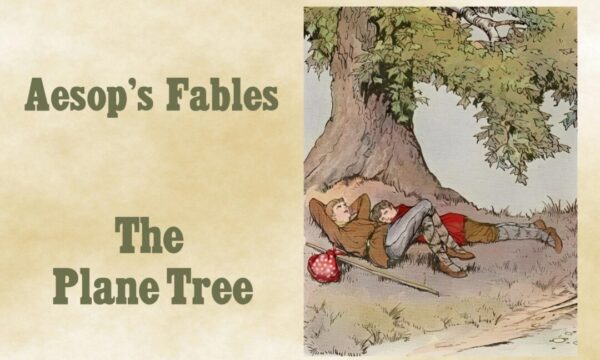















 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram




ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。