寒暖が入り混じる気候――その原因は天地の五行エネルギーの変化にある
乙巳年の清明(せいめい)以降、寒さ・暑さ・風・湿気が入り混じった不安定な気候が続いています。その背景には、地球の五行の経絡(エネルギーの流れ)が春の終わりに差し掛かっていることが関係しています。ちょうど穀雨(こくう)の時期に近づくにつれ、大気中の湿気が増しやすくなり、その影響で脾胃(ひい)や腸の消化機能に不調が出やすくなります。
晩春のこの時期は、五行で「木」に属する木のエネルギー(木気)が陽の気を持ち、気候全体を支配しています。陽気はまだ上昇を続けており、春の木の陽気は「風」を特徴とするため、風が強くなりやすいのが特徴です。さらに日本は五行において「木」に属する東の方角に位置し、太陽が昇る地域でもあるため、木のエネルギーが強く、風の影響がとくに顕著です。そのため、風邪をひきやすい季節といえます。
また、乙巳年は、古代の暦法と五行の運行から見ても「風木」のエネルギーがその年の主役となる年です。そのため、例年に比べて「風」が強調され、特に上半期は風の勢いが非常に強くなる傾向があります。これは呼吸器系への影響を及ぼす要因にもなり得るため、今年は肺のケアをしっかりと行う必要があります。
加えて、春分から立夏までの2か月間は、地球周辺の宇宙空間において、「水」に属する寒のエネルギー(寒水の気)が運行する時期にあたります。そのため「戻り寒」や「春の寒さのぶり返し」といった現象が起きやすく、季節が冬に逆戻りしたように感じることもあります。このような寒気の影響は、五行で「水」に属する腎のエネルギー(腎気)にダメージを与えやすいため、腎を守る生活を心がけることも重要です。
人体と天地のエネルギー場はつながっている
中医学では、「人体は小宇宙である」と考えられています。人の体の中には五臓と対応する小さな五行のエネルギー機構が働いており、それぞれが臓腑の機能を調整しています。そのため、養生の本質的な目的は、天候や気候の変化によって体内の五行の「気の流れ(気機)」が乱れるのを防ぐことにあります。
地球や宇宙空間の気象エネルギーの影響を受けて、人体の五行の気機もまた変動します。そして、体のエネルギーシステムが乱れると、臓腑の働きにも支障が生じます。中医学では、こうした天候による影響に応じて、人体のバランスを調整し、気の流れを正すことで病気の予防を行います。現代の言葉で言えば、いわゆる「未病」や「不調」の段階で、早期にケアを行うという考え方です。
五行のエネルギーは、宇宙のあらゆるものを形づくる基本原理であり、生命同士、そして星と星の間のエネルギー場も、互いに見えない形で影響し合っています。この見えないつながりこそが、生命の営みを支えているのです。中医学でいう「人体のエネルギー場の調整」とは、まさにこの人体という“小宇宙”の気候を整えることを意味します。現代的に言えば、体内に入ってきた「寒気」「湿気」「熱気」などの外的な要因を排出したり、中和することで、乱れたエネルギーバランスを正常に戻すことにあたります。
このような考え方に基づいて食事を調整するのが、古代の優れた「食医(しょくい)」たちが用いた方法であり、これこそが本来の中医学的な食養生法です。つまり、特別な薬を使わなくても、日々の食材選びや調理法によって行う広い意味での「食療」「薬膳」となります。
では、どのように食べ物で病気を予防し、軽い不調を改善すればよいのでしょうか?
それには、五行のエネルギー――たとえば、木の気が引き起こす「風」や「熱」、水の気がもたらす「寒」、土の気による「湿」など――がどの臓腑に影響しやすいかを理解することが鍵になります。どの臓器が最も影響を受けやすいかを見極め、その上で食材を選び、調整していくことが、具体的な食療の方針となります。
現在に合った薬膳の考え方
五行の「木・火・土・金・水」は、それぞれ人体の五臓「肝・心・脾・肺・腎」と対応しています。たとえば、風や熱の気は「木」に属し、肝の経絡に影響を与えます。寒の気は「水」に属し、腎の経絡に自然と通じます。湿気は「土」に属し、脾の経絡へと直接影響します。これは、人の五行エネルギーと自然界の五行エネルギーが同じ性質を持ち、互いに感応し合い、連動しているためです。
このような前提から、現在の気候や体調に合わせた薬膳の方針は以下のようになります:
① 脾を強め湿気を取り除き、消化器系を守ること
湿気は脾の働きを妨げ、肝と脾のバランスを崩す原因になります。脾が弱ると消化不良やだるさ、食欲不振などが現れやすくなります。よって、健脾(けんぴ)と祛湿(きょしつ)が基本の第一歩となります。
② 肝の気を整え、熱や火を取り除くこと
風・湿・熱の三つの気が肝の機能に影響を与えると、関節や筋肉に不調が出たり、気分の落ち込み、不眠、めまい、目のかすみなどの症状が出ることがあります。また、肝のエネルギーが肺を抑え込むように作用し、呼吸器系の機能が低下、免疫力も落ち、風邪やアレルギー、皮膚トラブルなどの外感病にかかりやすくなります。肝の気が滞れば、気血の流れが悪くなり、全身のエネルギー循環にも障害が出て、複雑な症状が現れやすくなります。
③ 腎を温め、補うこと
体が冷えやすい人、特に足元が冷える人は、腎の働きが弱まり、免疫力も低下します。腎の水が足りないと、肝をうまく滋養できず、結果として肝火(かんか)が強まってしまいます。腎を温めることで、肝と腎のバランスを整えることが大切です。
〜春の終わりにおける調整の要点まとめ〜
◆ 肝の気を巡らせ、気分の滞りを解消する
春は五行で「木」に属し、「肝」と深く関係しています。肝の気が滞ると、感情の起伏が激しくなったり、胸のつかえ、腹部の張り、女性では月経の乱れなどが起こりやすくなります。これを防ぐためには、肝の気をスムーズに流す「理気(りき)」作用のある食材を取り入れましょう。具体的には、紫蘇(しそ)、バラの花、小松菜、陳皮(ちんぴ)、ブロッコリー、グレープフルーツの皮、セロリ、もやし などが効果的です。
◆ 脾を強め湿気を取り除き、胃腸を整える
春の終わりには湿気が増してきます。湿邪の影響を最も受けやすいのが「脾」です。脾の働きが弱まると、消化不良や体のだるさ、免疫力の低下が起こりやすくなります。山芋、はと麦、豆腐、扁豆、小豆入りの味噌などの食材は、脾を強め、湿を取り除く効果があり、胃腸の調子を整えながら体力を高めてくれます。
◆ 腎を温め、体の根本を補い、陽気を守る
「戻り寒(寒の戻り)」がある春の終盤は、冷えが腎を傷めやすく、手足の冷え、疲れやすさ、風邪を引きやすいなど、虚寒体質の症状が現れやすくなります。黒豆、サバ、生姜、ニラ、紫蘇の葉、エビ などの食材を使って、腎を温め、体の陽気を補いましょう。これにより、体の根本的な活力が養われます。
養生薬膳セットメニュー例(2人分)
【メイン料理】豚肉と豆苗の生姜炒め

効能: 胃腸を温めて腎を補い、肝の気を巡らせ、脾を強めて湿気を取り除く
食材:
- 豚肩ロース薄切り:150g(腎を温め気を補い、肝を養う)
- 豆苗:1袋(肝の熱を冷まし、気の巡りを良くする)
- 生姜(新生姜でも可):10g(寒さと湿気を取り除き、胃腸を温め吐き気を抑える)
- 紹興酒または料理酒:小さじ1
- 醤油:大さじ1
- ごま油:小さじ1
作り方:
- 豚肉は酒と醤油で軽く下味をつけ、10分ほど置く。
- フライパンを熱し、ごま油と生姜の千切りを炒めて香りを出す。
- 豚肉を加え、色が変わるまで炒める。
- 豆苗を加えてさっと炒め、最後にお好みで白こしょうをふる。旨味調味料を少量加えても良い。
体質別アレンジのアドバイス:
- 虚寒体質の方: 生姜の量を増やし、唐辛子を少し加えることで陽気を補い体を温めます。
- 肝うつ・気滞タイプの方: 紫蘇の葉を少量加えて香りを立たせると、肝の気を巡らせる助けになります。
【サラダ】大根の味噌和えサラダ

効能: 熱を冷まし痰を取り、湿を排出し脾を強め、肺を潤して解毒
食材(2人分):
- 大根:150g(千切り、熱を冷まし湿を除く)
- きゅうり:1/2本(清涼感があり、体内の余分な水分を排出)
- にんじん:30g(気を補い脾を健やかに保つ)
- 白ごま:小さじ1(乾燥を潤し陰を養う)
- 白味噌:小さじ1.5(脾胃を温め、消化機能を助ける)
- 米酢:小さじ1(消化促進・解毒作用)
- 醤油:小さじ0.5
- ごま油:数滴(風味と潤いをプラス)
作り方:
- 大根・にんじん・きゅうりを千切りにし、少量の塩をふって軽くもみ、水分を出してからよく絞る。
- 白味噌、米酢、醤油を混ぜてタレを作る。
- 絞った野菜とタレをよく和え、最後に白ごまをふり、ごま油を数滴たらして仕上げる。
体質別アレンジのアドバイス:
脾虚で湿気が多いタイプ: きゅうりは体を冷やすため少量にとどめ、代わりに紫蘇や白こしょうを加えるとバランスが取れます。
熱性体質の方: 緑豆もやしや紫キャベツの千切りを加えると、より熱を冷まし解毒効果が高まります。
【スープ】山芋の味噌汁

効能: 脾を健やかにし腎を補い、肺を潤し咳を鎮め、気を養い心を落ち着かせる
食材(2人分):
- 山芋(長芋):80g(脾と腎を補い、肺を潤して咳を鎮める)
- ホンシメジまたはマイタケ:1/2パック(湿を除き脾を整え、気を補う)
- 小松菜またはほうれん草:ひとつかみ(肝の気を整え、湿を流す)
- 白味噌:大さじ1.5(脾胃を温め、滋養する)
- 昆布とかつおの出汁:500ml
作り方:
- 出汁を鍋に入れて火にかけ、沸騰したら山芋(一口大に切る)ときのこを加えて3分ほど煮る。
- 小松菜(またはほうれん草)を洗って食べやすく切り、鍋に加えて1分ほど煮る。
- 火を止めてから味噌を溶かし入れ、再加熱はせずそのままいただく。
体質別アレンジのアドバイス:
寒性体質の方: 生姜の薄切りを数枚加えて一緒に煮ると、体が温まりやすくなります。
燥熱体質の方: 少量の百合根や豆腐を加えることで、潤いを補い陰を養う効果が高まります。
【追加のおすすめ】食後の飲み物:紫蘇と生姜のお茶

材料(1人分):
- 乾燥紫蘇の葉:2g(風を散らし、気の巡りを整える)
- 生姜スライス:3枚(体を温め、寒さを散らす)
- なつめ:2個(心を落ち着かせ、腎を温める)
作り方:
材料をすべてカップに入れ、熱湯200mlを注いで5〜10分ほど蒸らしてから飲みます。お好みで黒砂糖を少し加えてもOK。
効能:
風を散らして寒さを取り除き、心を落ち着かせて腎を温め、気の巡りを安定させます。春の終わりの風が強い季節に特におすすめの飲み物です。
結びに
春の終わり、清明から穀雨にかけての五行と気候の変化を見極めて、食事を調整することは、天地の流れに順応し、五臓を養生することにつながります。この考え方をもとに、自分自身の体質や気候の特徴に合わせて食事を工夫することで、心身の健康を守り、未然に病を防ぐことができます。日々の暮らしの中で、「気づいて整える」ことが、もっとも自然で持続可能な養生法です。
(翻訳編集 華山律)



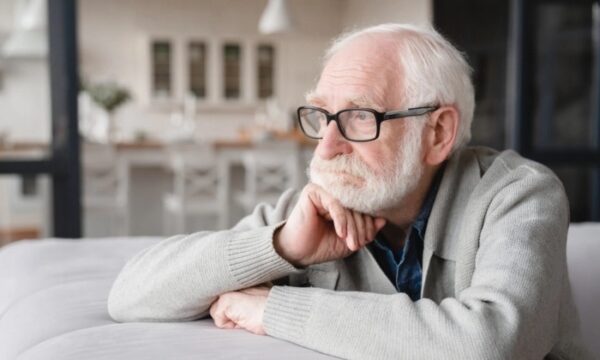



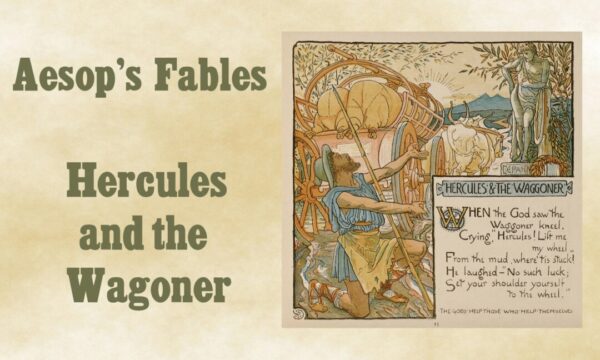
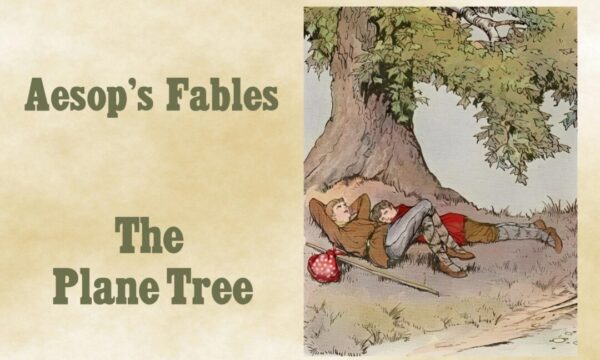















 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram




ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。