抜け毛や薄毛は、誰もがある年齢になると避けられない問題です。このシリーズの記事では、自分の抜け毛や薄毛の原因をより正確に見極め、考えられる解決策について理解を深めることを目的としています。
薬や食事によって、ある程度は抜け毛や薄毛を改善できる場合もありますが、すべての人に効果があるわけではありません。毛根が衰えたり、消失してしまった場合には、髪の毛は再び生えてきません。このような状況になると、植毛が最後の手段、あるいは簡単な解決策と見なされがちですが、実際はあなたが想像するよりも複雑な面があります。
植毛の歴史
植毛は「髪の毛を増やす方法」と誤解されがちですが、実際はそうではありません。もし髪の毛を丘の上に生える木に例えるなら、植毛とは木を増やすことではなく、茂っている場所から木を掘り出して、木のない場所に植え替える作業なのです。
植毛の起源は西洋ではなく、日本にあります。1939年、日本の皮膚科医師、奥田庄二氏が、人の頭髪移植に関する一連の論文を発表しました。彼は、火傷や頭皮に損傷を負った患者のために、頭髪を移植する技術を考案しました。パンチングツールを使って、毛根のある頭皮の部分を小さな円形に切り取り、禿げた部分に穴を開けてそれを植え込むという方法を用いました。
やがて移植された部分から発毛が見られるようになりました。彼は、移植する単位が小さければ小さいほど、特に1本の毛根ごとの移植は、仕上がりが自然になることを発見しました。
しかしこの功績は、第二次世界大戦の影響で西洋には広まりませんでした。1952年になって、アメリカ・ニューヨークの皮膚科医ノーマン・オレンテリッヒ氏が、世界で初めての毛髪移植手術の成功を発表しました。
オレンテリッヒ氏が用いたのは、直径4ミリほどの大きめの毛根付き頭皮でした。そのため、移植後に生えてきた髪は束状になり、大変不自然なものでした。この、髪が一本ずつではなく、束になって頭皮に差し込まれている状況を「ヘアプラグ」と呼ぶ人もおり、それは、まるで子どものおもちゃの人形のようでした。それでも当時は、重度の脱毛患者にとって最も人気のある外科的選択肢でした。
オレンテリッヒ氏が「西洋における現代植毛の先駆者」と言われる理由はもう一つあります。彼は、後頭部や側頭部の髪がより健康的で移植に向いており、移植後も元の髪のように抜けにくいということを初めて示した人物でもありました。
当時は、他にも禿げた部分を改善する外科的手法が試みられていました。たとえば、頭皮の一部を丸ごと移動させる皮弁移植術や、抜け毛部分の頭皮を縫い縮める頭皮縮小術などです。しかし、これらの手法は重い副作用を伴い、仕上がりも不自然でした。
その一方で、植毛技術は進化を続け、見た目の美しさも向上していきました。とはいえ、植毛には「理想とは異なる現実」もあります。いつでも植毛できるわけではなく、誰でもできるわけでもありません。手術後も脱毛治療薬を飲み続ける必要があり、さらに手術である以上、腫れや痛み、炎症、感染などの副作用は避けられません。
2種類の植毛技術
植毛手術には、一般的に用いられている2つの方法があります。
1つ目の方法は、後頭部から毛の生えた帯状の頭皮を切り取るやり方です。その後、立体顕微鏡を使って、頭皮を1~4本の毛髪を含む小さな単位に分けていきます。1本の帯状の皮膚から、通常1000~1500個に切り分けることが可能です。これらの移植片を脱毛部位に開けた小さな切り口に植え込み、皮膚を切り取った部分は縫合され、線状の傷痕が残ります。
この手術では、医師が1本以上の頭皮を切り取ることもありますが、何本取っても最終的には縫合して一本の線に整えられます。ただし、非常に短く髪を刈るヘアスタイルを好む人にとっては、後頭部の傷跡が目立つ可能性があります。
この方法は「毛包単位移植(FUT)」または「ストリップ法」と呼ばれています。
もう一つの方法は、より精密な穿孔ツールを使い、後頭部の広い範囲から毛包を1本ずつ直接採取し、それを必要な部分に植えるやり方です。こちらは「毛包単位抽出法(FUE)」と呼ばれています。
FUEでは、作業の視野を確保し、毛包を効率的に取り出すために、移植量が多い患者は頭髪を全て剃る必要があります。一方、FUTでは移植する部位の髪だけを剃ればよい場合が多いです。
多くの人が「FUEは傷跡が残らない」と考えていますが、これは誤解です。国際毛髪修復外科学会の会員であり、アンダーソンヘアセンターの植毛外科医ジェレミー・ウェッツェル氏は、大紀元時報の電話インタビューで「FUEでも実際には同じくらいの傷が残ります」と語っています。
FUEでは、FUTのような線状の傷ではなく、小さな点が広範囲に散らばって残る形になります。傷は分散しており、治癒後は髪を短くしても目立ちにくくなります。
このFUE技術が登場したのは比較的新しく、毛包を横に切断しないように丁寧に取り出し、自然な仕上がりに植え込むことができるのは、経験豊富な医師に限ります。
国際毛髪修復外科学会の会員であり、米国外科医師学会の会員、マイアミ大学の非常勤教授、個人クリニックの医師でもあるジェフリー・エプスタイン氏は、大紀元時報のメール取材に対して「FUEは線状の供給部位の切開を避けることができ、芸術的な手法で行えば非常に優れた結果を得ることができます」と述べています。
この2つの方法は、患者の状況によって異なります。
ウェッツェル医師は「FUTではより多くの毛髪を移植することが可能です」と言います。長期的に見て(複数回の手術を含む)、FUTでは合計約1万株の毛包を移植することができ、FUEでは5000~6000株程度にとどまります。また、頭頂部の毛髪がすでに薄くなっており、将来的に抜け毛や薄毛がさらに進む可能性がある患者は、再度毛包を採取する必要が出てくるため、FUTの方が適しているケースもあります。
「短い髪型を好む人はFUEを選ぶ傾向があります」とウェッツェル医師は話します。彼のクリニックで行われる植毛手術のうち、約60%がFUT、40%がFUEだという事です。
また、2つの手術法を組み合わせて行うケースや、FUEでFUTによる線状の傷跡を修復するケースもあります。
誰もが植毛に適しているわけではない
植毛ができるかどうかは、年齢、抜け毛や薄毛の進行度、そして移植に使える毛包の質によって決まります。
「すべての人が植毛手術に向いているわけではありません」と、ウェッツェル医師は率直に語ります。
40代以降に抜け毛や薄毛が気になり始めた人に比べ、20代で抜け毛や薄毛が始まった人は、症状が重く、進行が早い傾向があります。このような患者の治療では、まず薬物療法やその他の療法を組み合わせて抜け毛や薄毛を安定させることが最も重要です。医師の指導のもとで1~2年かけて脱毛が止まった後に、初めて手術を検討することができます。
長期間の治療にもかかわらず抜け毛や薄毛が続く場合、何度も植毛を繰り返して改善しようとするのは、現実的ではないかもしれません。なぜなら、毛髪が抜け続けるということは、移植に使える髪もどんどん減っていくということだからです。「手術は、進行する脱毛に永遠に追いつくことはできません」とウェッツェル医師は言います。
また、毛根の質も手術の成否を左右します。国際毛髪修復外科学会の委員で植毛外科医のラジェシュ・ラジプト氏は、大紀元時報の取材に対し、「植毛後によく髪が生える人もいれば、あまり伸びない人もいる。それは、すべての人が高品質な毛根を後頭部に持っているわけではないからです」と説明しています。
「もちろん、家族歴も重要です」と彼は言います。医師は、患者の家族において抜け毛や薄毛がどのように進行しているかを理解することが必要です。父親、祖父、父方の叔父などに、すでに抜け毛や薄毛が広範囲に進行している場合、患者本人も将来的に同様の経過をたどる可能性が高く、その場合「そもそも植毛できる対象ではない」のです。
では、どのような人が植毛に向いているのでしょうか? Dauer植毛センターの医療責任者であるマーク・ダウアー医師は『大紀元時報』に対して、「抜け毛や薄毛が極端に進行していない人、中程度の遺伝性脱毛があり、後頭部に十分な量の永久毛包がある人」が、良い候補となり得ると述べています。さらに、多くの医師は、特に若年の患者が早期に植毛を受けることには慎重な姿勢を示しています。
いつでも植毛できるわけではない
脱毛患者の状態により、すぐには植毛手術は受けられません。まずは抜け毛や薄毛を治療し、状態が安定してからでないと、植毛は行えません。
短期間で抜け毛や薄毛の進行を抑えることが重要です。「私たちがやっているのは、患者さんのために少しでも時間を稼ぐことです」と、ロンドンの植毛外科医であり、ミタル・ヘア・クリニックの創設者兼CEOのマニッシュ・ミタル医師は、大紀元時報の電話取材で語っています。
多くの人が「植毛は最終手段」「自分の重度の抜け毛や薄毛を逆転させる最後の頼み」と考えがちですが、残念ながら、抜け毛や薄毛が進めば進むほど、もとの状態に髪を戻すのは困難になります。中には、20年以上抜け毛や薄毛が続いた後に突然「もうハゲを終わらせたい」と思い立って植毛を希望する人もいますが、そのタイミングではすでに手遅れかもしれません。ウェッツェル医師は、「そのようなケースでは、手術や薬物治療をおすすめ出来ないこともあります。なぜなら、効果が見込めない可能性があるからです」と話します。
また、自己免疫疾患による抜け毛や薄毛(円形脱毛症、毛髪扁平苔癬、瘢痕性毛包炎など)の患者は、病状が活動期にある場合、植毛はできません。少なくとも2年間は症状が再発していない状態が必要で、ようやく植毛を検討することができます。ただし、それでも理想的な結果が得られない可能性があり、さらに病状を再発させるリスクもあります。これは、植毛が身体にある程度の「傷」を与える手術であるため、免疫系を過剰に刺激してしまう可能性があるからです。
植毛には忍耐と長期的な計画が必要
植毛をするには、十分な忍耐が欠かせません――最終的な効果が現れるまでに、最大で1年ほどかかることもあります。
手術後の数か月間は、新しく移植された毛包からの髪がいったん抜け落ち、手術前よりも髪が薄く見えることさえありますが、これは正常な経過です。アメリカ皮膚科学会の情報によれば、多くの患者は植毛手術から6~9か月後に、抜け毛や薄毛の改善が徐々に見られるようになります。また、新しい髪は一斉に生えてくるのではなく、段階的に少しずつ伸びてきます。
たとえ移植が成功しても、男性ホルモンの影響による脱毛症(AGA)の患者は、長期的に薬を服用し続ける必要があります。新たに移植された髪は後頭部から採取されたもので、頭頂部の本来の髪と異なり、ジヒドロテストステロン(DHT)という男性ホルモンの影響を受けにくいため、将来的に抜けることはほと
んどありません。しかし、もともとの頭頂部の髪はDHTの影響を受けやすいため、薬で守る必要があります。ウェッツェル医師は、「薬を併用しなければ、せっかくの植毛も一時的な結果に終わってしまいます。元々の髪が抜け続けることで、新しく植えた髪との間に空白ができてしまうのです」と警告しています。
ミタル医師によれば、フィナステリドを服用する前提であれば、1回の植毛手術の効果は通常およそ10年間持続します。そのため、患者は将来的に再び植毛が必要になる可能性があります。たとえば、30歳で初めての植毛を受けた場合、通常は40歳頃に2回目、さらに45歳頃に3回目で最後の手術を行う、といった長期的な流れになることが多いそうです。
薬や補助療法があったとしても、移植後の髪の保護には限界があります。長期的に見ると、抜け毛や薄毛はやはり進行していく病気なのです。したがって、最初に植毛の計画を立てる際には、現状を冷静に評価し、将来の治療のために十分な毛包を残しておく必要があります。使える毛包を一度にほとんど使い切ってしまうような計画は避けるべきです。経験のある医師であれば、将来新たに抜け毛や薄毛が起こる部位への対応も見越し、最初から生え際を低くしすぎたり、密度を高くしすぎたりするようなデザインは避けます。
医師の資格と技術について
「実際に手術を行うのは誰か? 医師なのか、それとも技術者なのか?」――これは、植毛クリニックに必ず確認すべき重要なポイントです。
FUT(毛包単位移植)は、伝統的な植毛手術であり、患者の頭皮を切開・縫合する必要があるため、外科医が行う必要があります。一方で、毛包の切り分けや移植は、植毛技術者(Hair Technician)が担当する場合もあり、もちろん医師が行うこともあります。
FUE(毛包単位抽出)は、頭皮を切開せず、点状に毛包を取り出す方法のため、頭皮を縫合する必要がありません。そのため、場合によっては技術者のみで処置が行われることもあります。言い換えれば、「頭皮の切開と縫合」は外科的処置であり、医師しか行えませんが、「毛包の移植」は、医師免許がなくてもできるというのが実情です。
「できれば、脱毛や毛髪の修復を専門とする医師に診てもらうべきです」と、ドイル医師は注意を促します。一部のクリニックでは、実際には医師が不在で、医師助手や看護師が手術を行っている場合もあります。
ミタル医師は、植毛に関する医療計画も、医師が立てるべきだと強調しています。しかし、現在の業界は必ずしも十分に整備されておらず、資格のない人が治療計画を立てているケースもあります。患者の中には「無料でアドバイスをもらえた」と喜ぶ人もいますが、そのアドバイスの質が高いとは限りません。
アメリカ脱毛協会の情報によると、植毛に関連する団体や医師のネットワークは多数存在していますが、それぞれの背景を確認することが重要です。ある肩書を持っているからといって、その人に十分な技術や正式な資格があるとは限りません。中には、登録料を払えば誰でも加入できる団体もあり、研修や情報提供だけを行い、認定はしていない団体もあります。その中でも、国際毛髪修復外科医師連盟への加盟には高い基準があり、多くの実績資料の提出が求められます。この団体の正式会員は、業界の中でも高水準を満たしているとされています。
なお、「毛髪学者(トリコロジスト)」という職業も存在しますが、「彼らは医師ではありません」と、ラジプト医師は注意を促しています。毛髪学者とは、技術的なスキルに基づいた資格であり、高校卒業後、6か月から1年の講座を修了すれば取得できるもので、薬の助言を除いた他の方法をアドバイスすることができます。
また、よく見かける植毛の「ビフォー・アフター」写真は、希望を持たせてくれる一方で、その裏にある時間や努力が語られないことも多いのです。「それが1回の手術か、4回の手術か、私たちには分からないことがあるのです」と、ウェッツェル医師は指摘します。たとえば、1枚目の写真ではかなり抜け毛や薄毛が進んでおり、2枚目ではフサフサの髪がある場合、それは1回の施術ではなく、長年にわたって複数回の手術を経て得られた結果である可能性が高いのです。
ウェッツェル医師は、「一部のクリニックでは、一度に5000株の毛包を移植できるとうたっていますが、それは非常に大規模な手術であり、実際にそれを高いレベルでこなせる施設は限られています」と述べています。彼自身は、より小規模な手術を好み、1回の手術で約2500株の毛包を移植するスタイルをとっています。
手術後の回復と注意点
植毛には、かゆみ、額の腫れ、毛包炎、FUT(ストリップ法)による肥厚性瘢痕、しびれ、感染、出血、移植毛の脱落など、さまざまな合併症や副作用が起こる可能性があります。
手術後は、まず十分な休息が必要です。FUTは切開と縫合を伴うため、回復には約2週間の休養が推奨されます。FUE(毛包単位抽出法)の場合は比較的軽度ですが、それでも理想的には1週間程度の休息が望まれます。
以下は、術後の回復を促すための実践的な方法と注意点です。
- 術後数日間は、額に氷を当てて冷却するのが効果的です。2~3時間おきに、20分ほど氷で冷やすことで、血管が収縮し、腫れやあざを軽減できます。
- 手術後1週間程度は、就寝時に頭を15~30度ほど高くして休むことで、頭部の腫れを防ぎやすくなります。
- 術後数日が経過し、医師の許可が出たら、ベビーシャンプーを使ってやさしく洗髪することができます。ただし、シャワーヘッドから直接水を当てるのは避けてください。水圧が毛包に刺激を与える可能性があります。
- 移植後の2週間は、毛がまだしっかりと根付いていないため、非常にデリケートな状態です。植毛部位にはブラシを当てたりマッサージをしたりしないようにし、きつめの帽子なども避けましょう。毛包が引っ張られ、脱落の原因となります。
- 術後1週間は、激しい運動や汗をかくような行動を控えましょう。プール、サウナなどは少なくとも3週間以上経ってからが望ましいとされています。
より良い回復を目指すなら、少なくとも手術前後の期間中は禁煙・禁酒を真剣に考えるべきです。
ウェッツェル医師は、「喫煙や飲酒の有無が、植毛の結果に大きく影響します」と述べています。ニコチンは毛包に通じる細い血管を収縮させ、血流を悪化させるため、毛包の修復を妨げ、抜け毛や薄毛の原因にもなります。アルコールは、コラーゲンの生成や新しい血管の形成を阻害し、傷の治癒を妨げます。また、血小板の凝固機能にも影響を与えるため、出血量が増え、移植の成功率が下がる可能性があります。
(翻訳編集 華山律)







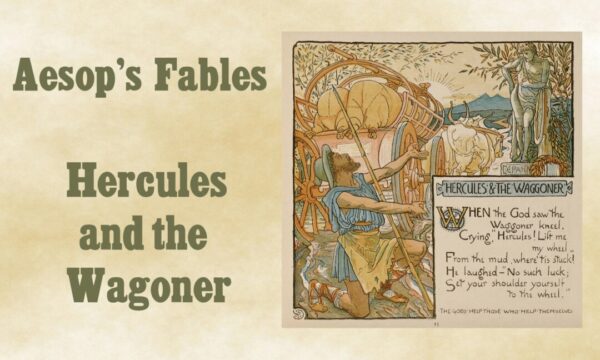
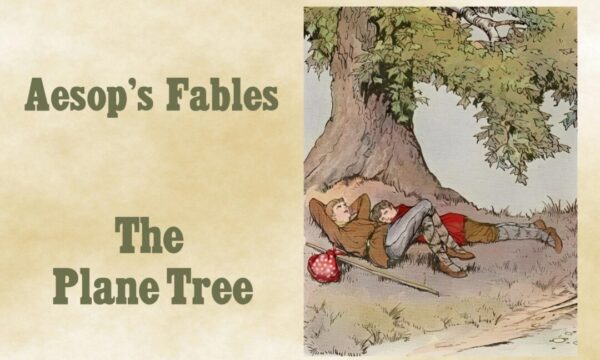















 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram




ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。