診察に訪れる患者さんの中には、開口一番「先生、最近『火』がこもっている感じがします」と訴える方がいます。そこで「どんなふうに『火』を感じますか?」と尋ねると、「口が渇いて喉もカラカラで、ずっと水を飲みたくなるんです」と答えることがよくあります。
口の渇きは軽い症状ではない―中医学における基本的な診察ポイント
口の渇きは単なる主観的な感覚ではなく、中医学において重要な診断要素の一つです。中医学では「辨證論治(体質や症状の特徴を見極めて治療を行う)」を基本としており、そのために「望(視診)・聞(嗅覚や聴覚を用いた診察)・切(脈診)・問(問診)」という四つの診察法(四診)を用います。口の渇きは、この四診の中でも特に重視されるポイントであり、その原因はさまざまに分類されます。
一、体に熱がこもっている場合
これは、いわゆる「火」がこもることで体内の津液(水分)が消耗してしまう状態で、最もよく見られる状況です。
例えば、春先に風邪が流行すると、喉の痛みや乾燥、声のかすれといった症状を訴える人が増えます。これは、外から入った熱邪(外感熱邪)が肺を傷つけたために起こるもので、治療には「清燥救肺湯」や「麦門冬湯」などがよく用いられます。
また、夜更かしが続くとニキビができたり、便秘になったり、口臭が強くなったりすることがあります。これも「火がこもる」典型的な症状です。中医学では、こうした症状を「心火」「肝火」「胃火」などに分類し、それぞれに適した漢方薬を処方します。
さらに、辛いものや刺激の強い食べ物を摂りすぎることも、体に熱がこもる原因になります。例えば、唐辛子やニンニク、生姜茶などを大量に摂取すると、体内に余分な熱がたまりやすくなります。筆者が最近診察した患者さんの中にも、ひどい口の渇きと胸のつかえを訴える方がいました。いくら水を飲んでも渇きが治まらず、息苦しさまで感じるというのです。診察してみると、舌苔が乾いて黄色くなっていました。しかし、風邪の症状は特にありません。詳しく話を聞くと、その方は毎日生姜茶を飲んでいたのです。
「生姜茶は体にいい」と聞き、冬から春にかけてずっと飲み続けていたとのこと。しかし、気温が上がっても飲み続けたため、体内に熱がこもりすぎてしまいました。そこで、生姜茶をやめてもらい、体を潤す作用のある漢方薬を処方したところ、次の診察時には舌の状態も正常に戻り、口の渇きや咳、胸のつかえも改善しました。
二、陰液が不足し、体内の水分が十分に作られない場合
例えば、高齢者は腎の陰が不足しやすく、唾液の分泌が減るため、口の渇きを感じやすくなります。また、長期間にわたって夜勤を続けたり、夜更かしや過労を重ねたりすると、慢性的に肝や腎の陰が消耗し、さらに胃の陰まで不足することがあります。
こうした場合、舌が赤く苔が少なくなり、脈が細く速くなるのが特徴です。治療には、体を潤す作用のある漢方薬がよく用いられます。
例えば、山薬(サンヤク)、沙参(シャジン)、玉竹(ギョクチク)、天花粉(テンカフン)、生地黄(ショウジオウ)、熟地黄(ジュクジオウ)、麦門冬(バクモンドウ)、枸杞子(クコシ)、女貞子(ジョテイシ)などが代表的です。
三、体を温める力が不足し、水分が口や舌に行き渡らない場合
これは、冷えが原因で起こる口渇です。体を温める「陽気」(エネルギー)が不足すると、ちょうど火力の弱いボイラーのように、水分が蒸発せず、口や舌まで十分に届かなくなります。そのため、口が渇いているのに、水分をとっても潤わない状態になります。
このような場合は、体を温める作用のある乾姜(カンキョウ)や桂枝(ケイシ)などの生薬を使い、体の「火力」を高めることで水分の循環を促し、口の渇きを改善します。このタイプの口渇では、舌が淡く苔が白い、寒がり、疲れやすいといった特徴が多く見られます。
また、別のケースとして、もともと胃に熱がこもりやすい人が、暑い日に大量の冷たい飲み物や食べ物を摂ると、消化器官が一時的に冷えすぎてしまい(寒包火)、体内の水分の巡りが悪くなることがあります。この状態では、体の熱がうまく発散できず、かえって口渇がひどくなるのです。これは現代人に特に多いケースで、氷や冷たい飲み物を摂りすぎた結果、逆に「火がこもった」ように感じることがあります。
こうした場合、中医学では寒さと熱のバランスを整える治療を行い、体内の熱を適切に発散させる生薬を組み合わせて処方します。単に「熱を冷ます」だけでは、かえって症状が悪化することがあるため、慎重な対応が必要です。
「避けるべき食材」を知り、症状を悪化させないように
口の渇きは、環境や季節、地域の気候とも深く関係しています。大陸性気候の国では湿度が低く、口の渇きを感じやすくなります。また、長時間の飛行機移動でも、機内の乾燥した空気の影響で、口や目、肌が乾燥しやすくなります。
そのため、こまめな水分補給を心がけることが大切です。特に注意したいのは、機内で提供されるおやつです。ナッツ類などの乾燥しやすい食品が多く含まれているため、食べすぎないほうがよいでしょう。もし食べるなら、飛行機を降りた後にするのが無難です。
口の渇きを改善するには、体を潤し、水分を生み出す食べ物を摂るのが効果的です。例えば、梨、山芋、キクラゲなどは特におすすめです。一方で、冷たいものを大量に摂るのは避けるべきですし、体を熱しやすい食べ物はさらに控えたほうがよいでしょう。
具体的には、ネギ、生姜、ニンニク、辛い鍋料理、ごま油を使った鶏料理、揚げ物や焼き物、ナッツ類などが挙げられます。こうした食べ物を多く摂ると、口の渇きがさらに悪化する可能性があります。もし、これらに気をつけても口の渇きが改善されない場合は、一度専門の医師に相談し、適切な診断を受けることをおすすめします。
(翻訳編集 華山律)






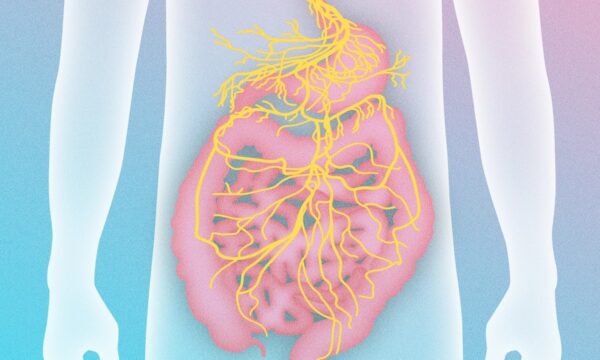


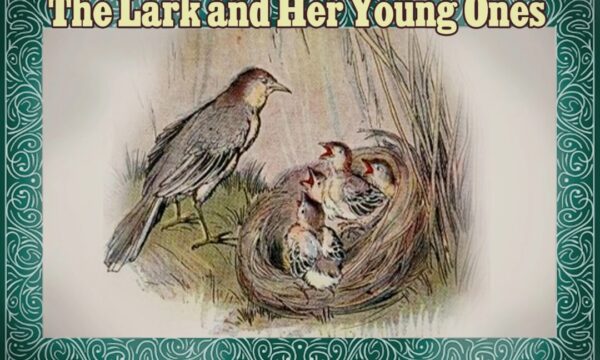
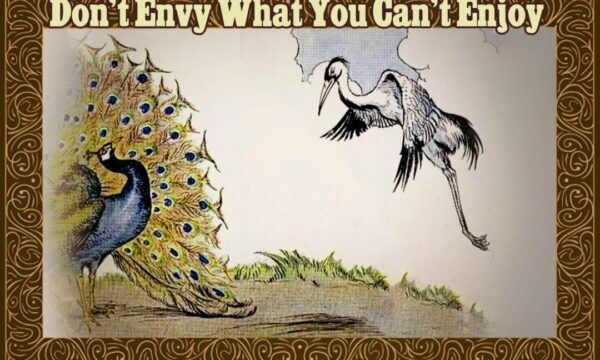









 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram




ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。