寒水が並行し 春先の冷え込みが発生する
『黄帝内経』によれば、毎年の気候は、冬の「大寒」から始まり、2か月ごと、つまり節気4つをひと区切りとして、1年の24節気を6つの期間に分け、それぞれが異なる五行のエネルギーに支配されるとしています。
現在はその第2の期間、「二之気(にのき)」にあたり、春分(3月20日)から立夏(5月20日)までの時期に該当します。この時期、地球は「木」「火」「水」という三つのエネルギー(気)に支配されており、風・熱・寒が交じり合った気候が現れやすくなります。風が強く、気温が上下しやすいのが特徴で、人体にさまざまな影響を及ぼすことがあります。
地球本来の6つの気の五行的性質は毎年変わることはありません。二之気の時期には、春の「木の気」に加えて「火の気」が同時に作用し、風が多く、陽気が強まり、全体としては温暖な気候になるのが本来の姿です。
しかし、地球と同時に宇宙から入ってくる6つの外気の性質は毎年変化します。この変化によって、地球上の気候にも異変が起きます。2025年は「乙巳年」にあたり、この年の二之気(春分~立夏)は、地球本来の「火の気」ではなく、「寒水の気」が主導します。この寒水の気は北方から来る冬のエネルギーであり、その影響で「春なのに冬のような寒さ」が訪れるのです。
さらに、乙巳年は1年を通して「風木の気」が支配的となり、大気中の「金の気」が不足します。自然界の金の気が不足すると、本来木の気を抑えるはずの金の力が弱くなり、風(木の気)が勢いを増します。そのため、今年の春は特に風が強く、また気温の変動が大きいため、「風熱」や「風寒」による外感病(風邪のような症状)を引き起こしやすくなります。
加えて、金の気に属する肺のエネルギーも弱くなりやすく、肺機能が低下しがちです。呼吸器の調子を崩しやすくなるため、丁寧な養生が必要です。
また、寒水の気は人体の腎経(腎臓の経絡)に直接影響を与えやすく、腎陽(腎の温める力)が弱くなることで、手足が冷たくなる、冷えを感じるといった症状が現れやすくなります。さらに、寒さの影響で肝気の巡りも悪くなり、肝の働きが抑制されることで、肝と脾のバランスが崩れる可能性があります。
四つの健康上の問題
風寒または風熱による外感 寒水の気の影響によって気温の急激な変化が起こりやすく、風寒や風熱にさらされることで、風邪、喉の痛み、頭痛などの症状が現れやすくなります。
肺気の不足 2025年の乙巳年は「風木の気」が主導しており、自然界の「金の気」(肺は五行で金に属する)が不足します。そのため、肺のエネルギーが弱くなり、虚弱性の咳、アレルギー性鼻炎、息切れ、だるさなどの問題が起こりやすくなります。
腎陽の虚弱 寒水の気は腎経(腎の経絡)に直接影響を及ぼしやすく、手足の冷え、疲れやすさ、腰や膝のだるさ・痛みが現れることがあります。さらに、水分代謝が滞り、脾胃の働き(消化吸収)にも影響を与えることがあります。
肝鬱脾虚 寒気が肝のエネルギーを抑え、肝と脾のバランスが崩れることで、情緒の不安定(気分の落ち込み)、消化不良、腹部の張り、食欲不振といった症状が起こりやすくなります。
四つの食養生法
1、脾腎を温め、寒さを払って陽気を守る
- 適した人 : 手足が冷える、腰や膝がだるく力が入らない、疲れやすい人
(1)黒豆と紫米のおかゆ
食材 :
黒豆50g、紫米80g、生姜3枚、水500ml
効能 : 腎の陽気を補い、寒さを取り除いて体を温め、体力を高める。
作り方 :
・黒豆はあらかじめ6時間ほど水に浸けておく。紫米は洗っておく。
・黒豆、紫米、生姜を鍋に入れ、水を加えて煮立てる。
・沸騰したら弱火にして40分ほど煮込み、豆がやわらかくなり、米が煮崩れるくらいで完成。
(2)かぼちゃの味噌汁
食材 : かぼちゃ100g、豆腐50g、味噌適量、昆布だし300ml
効能 : 脾胃を温めて消化を助け、免疫力を高める。
作り方 :
・かぼちゃは皮をむいて一口大に切り、豆腐も小さく切る。
・昆布だしを煮立て、かぼちゃを入れて柔らかくなるまで煮る。
・豆腐を加え、火を止めてから味噌を溶かし入れ、よく混ぜて出来上がり。

2、肺の気を補い、肺を潤して陽気を守る
- 適した人 : 咳が出る、鼻炎がある、風邪をひきやすい人
(1)白きくらげと杏仁の豆乳ドリンク
食材 : 白きくらげ5g、甘杏仁10g、豆乳250ml
効能 : 肺を潤し、咳を鎮め、肺の気を強めて乾いた咳を改善する。
作り方 :
・白きくらげは水で戻し、固い部分を取り除いて小さくちぎる。
・甘杏仁と白きくらげを少量の水と一緒にミキサーでペースト状にする。
・これに豆乳を加え、弱火で5分ほど温めたら完成。
(2)しらすと豆腐のとろみスープ
食材 : しらす50g、豆腐100g、クコの実5g、卵1個、塩適量
効能 : 肺の気を補い、免疫力を高めて体力の回復を助ける。
作り方 :
・しらすはさっと洗い、豆腐は一口大に切る。卵は溶いておく。
・鍋に水を入れて沸騰させ、豆腐としらすを加えて5分ほど煮る。
・卵液を流し入れてかき混ぜ、クコの実を加えて塩で味を調えたら出来上がり。
3、肝の気を通じさせて気の巡りを整え、肝と脾のバランスを調える
- 適した人 : 気分が落ち込みやすい、消化が悪い、肝の気が滞っていると感じる人
(1)烏梅と紫蘇の薬膳茶
※「烏梅」とは、梅の未熟な実を燻製(くんせい)にした生薬のこと
食材 : 烏梅2個、紫蘇の葉5g、黒糖適量、水300ml
効能 肝の気の滞りを解き、気分を軽くし、消化を助けて食欲不振を改善する。
作り方 :
・烏梅と紫蘇の葉を水に入れ、沸騰後5分ほど煮る。
・火を止めてから黒糖を加えてよく混ぜ、温かいうちに飲む。
(2)緑豆もやしと柑橘のさっぱりサラダ
食材 : 緑豆もやし100g、柑橘50g、オリーブオイル適量、塩少々
効能 : 体にこもった熱を冷まし、肝と脾の調和を促進し、消化力を高める。
作り方 :
・緑豆もやしはさっと30秒ほど湯通しし、水気を切っておく。
・柑橘は皮をむいて房に分け、もやしと和える。
・塩とオリーブオイルを加えてよく混ぜたら完成。
4、風寒・風熱による感冒を予防する
- 適した人 : 体質が弱く、風邪をひきやすい人
(1)生姜と香菜の卵スープ
食材 : 生姜5g、パクチー3g、卵1個、水300ml、塩少々
効能 : 風を払い寒さを散らし、風邪の予防と免疫力の向上に役立つ。
作り方 :
・水を沸騰させ、薄切りにした生姜を加える。
・溶き卵を流し入れてかき混ぜ、卵がふわっと固まったらパクチーを加える。
・塩で味を調えて出来上がり。

(2)れんこんと山芋の鶏スープ
食材 : れんこん100g、山芋50g、鶏肉150g、クコの実5g、塩適量
効能 : 気と血を補い、体力を高めて寒さから体を守る。
作り方 :
・鶏肉は熱湯で下ゆでし、アクを取る。れんこんと山芋は食べやすく切る。
・すべての材料を鍋に入れ、水を加えて約40分煮込む。
・最後に塩で味を整えて完成。
まとめ
2025年の春(春分~立夏)は寒暖の差が大きく、風が強く吹きやすい季節です。食事はこの節気に合わせて、脾腎を温め、肺を潤し陽気を守り、肝の気の巡りを整え、風邪を予防することが大切です。冷たい・生ものは避け、体を温めて滋養する食材を積極的に取り入れ、気候の変化にうまく対応できるようにしましょう。
(翻訳編集 華山律)






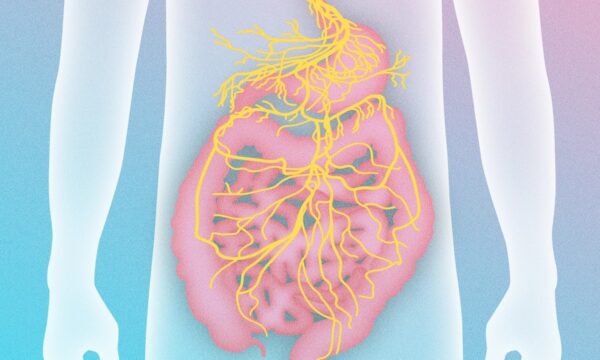


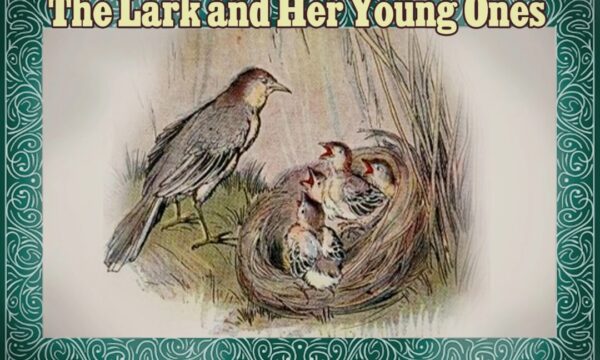
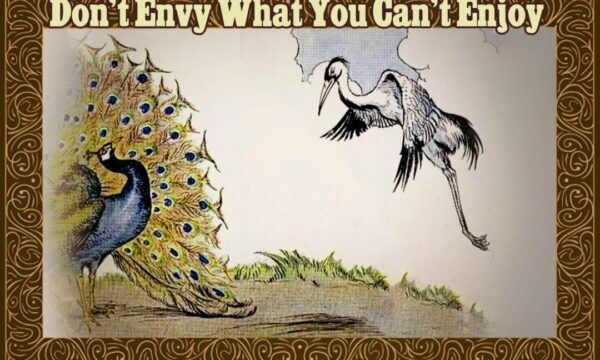









 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram




ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。