清明は肝の養生に 菜の花がちょうど旬
清明を過ぎると春の陽気が本格化し、体内の「肝」の働きが最も活発になります。ただしこの時期は、精神的ストレスによってそのバランスが崩れやすく、イライラ、不眠、頭重、消化不良などの不調が出やすくなります。この時期の養生では、肝の気を巡らせて滞りを解き、熱をさまし、脾胃(胃腸)を整えることが大切です。
五行の考え方では、肝は「青(緑)」と関係があり、春に旬を迎える緑の野菜を食べることが、食材の力が肝に届き、たかぶった火の気や滞った気血をやさしく整えてくれます。気血の巡りが整えば、心も体も自然と健やかに保つことができるのです。
ちょうど今が旬の「菜の花」は、肝の熱をさまし気を巡らせる働きがあり、肝・脾・肺のバランスも整えるという、まさに自然が与えてくれた“食の良薬”です。私たちの体に必要なものは、季節の恵みの中にすでに用意されているのだと、気づかせてくれる食材でもあります。
菜の花の養生効果
五味・五性:微寒、苦味・甘味
帰経:肝・脾・肺
◎ 主な効能
- 肝の気を巡らせ、気分の滞りを和らげる
- 肺の熱をさまし、うるおす
- 脾胃の働きを助け、食欲を整える
- 目の疲れや乾燥をケアする
「菜の花」養生レシピ3選
① 菜の花のおひたし

作り方
菜の花はさっと下ゆでし、しょうゆ・みりん・昆布とかつお節のだしを合わせた調味液に浸し、冷蔵庫で冷やして味をなじませます。お好みで白ごまやおろし生姜を少し加えると、香りが引き立ちます。
風味の特徴
あっさりとした中にほのかな甘みとうま味があり、後味にやさしい余韻が残ります。
こんな方におすすめ
- 気分が沈みがちで、ストレスを感じやすい方
- 肝火が強く、不眠や目の乾きを感じる方
- 顔が赤くなりやすい方
期待できる効果
- 肝の気の巡りを良くし気分の滞りを和らげ、肝の熱を鎮める
- さわやかな香りで食欲を引き出し、胃腸の働きを助けて湿気を取り除く
- 冷やして食べることで春の余分な熱をさますのにも役立つ
※胃腸が冷えやすい方は、おろし生姜やしょうが汁を加えると寒さを中和し、胃を守ることができます。
② 菜の花と卵の炒め物

作り方
ゆでた菜の花を切って、卵と一緒に炒める。
調味は塩・醤油・味噌などお好みで
風味の特徴
菜の花のほろ苦さと卵のまろやかさが調和し、後味に旨みが残る
こんな方におすすめ
- 冷たいものですぐお腹を壊す方
- 疲れやすく、顔色が冴えない方
- 春になるとやる気が出にくく、ぼんやりしがちな方
期待できる効果
- 脾胃の働きを高め、気と血を補う
- 肝をいたわりながら、目にもやさしい
- 春の疲れを癒し、体のリズムを整える
③ 菜の花のごま和え

作り方
下ゆでした菜の花に、すりごま+みりん+醤油を加えたごまダレで和える
アレンジ
白ごまや練りごまを加えて、風味と栄養価をアップ
こんな方におすすめ
- お通じが不安定な方
- 肌が乾燥しやすく、血の不足を感じる方
- 生理前にイライラしやすい方
期待できる効果
- 腸を潤し、便通を促す
- 血を補い、肝のバランスを整える
- ごまは肝と腎にも働き、五臓をいたわる
おすすめの組み合わせ
主食と一緒に 白ごはんに添えれば春のお弁当にぴったり
雑穀ごはんと合わせて 脾をいたわる養生ごはんに
体が冷えやすい方は しょうが入り味噌汁を添えて温め効果をプラス
まとめ 五行の知恵で春を整える
五行の考え方では、春は「木」に属し、肝を司るとされています。木は土(脾)から生まれますが、強くなりすぎると脾や肺の働きを損ねることもあります。
菜の花のように、少し苦みがありながら体を冷やしすぎない食材を適度にとることで、陽気を高め、肝の巡りを助け、胆の働きを整えることができます。しかも、脾胃を傷める心配もありません。
組み合わせる食材や調味によって、以下のような養生効果が期待できます。
肝の巡りを整える(+かつおだし)
脾や肺を養い、気を補う(+卵)
腸をうるおし、便通を整える(+ごま)
菜の花は、春にぴったりの、肝・脾・肺をやさしく整える理想的な養生野菜といえるでしょう。







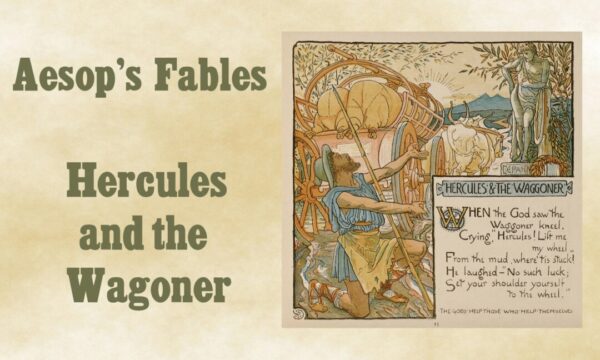
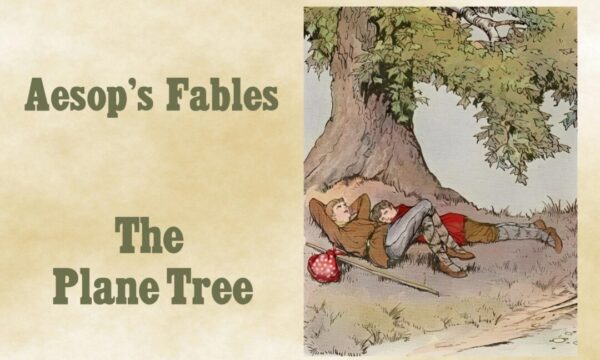















 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram




ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。