唐代の女帝である武則天に対する評価は、歴代を通じて賛否が分かれています。「非常に優れた才能と見識を持つ政治家であったが、その人柄は非常に厳格で冷徹であった」と述べられています。
ここでは、詩の内容に基づいて話します。
武則天(ぶそくてん)は十四歳の時、その美しさから唐の太宗の後宮に召し上げられ、『才人』の位を与えられました。その後、唐の高宗(太宗の子である李治皇子)が即位すると、彼女は再び宮中に迎え入れられ、『昭儀』に任命されました。
さらにその後、正式に皇后の位を与えられました。
唐の高宗はもともと、長男の李忠(りちゅう)を皇太子に立てていましたが、
武則天が皇后に即位した後、大臣の許敬宗(きょけいそう)と共謀し、
「子は母によって尊ばれるべきである」との理由で奏章(公式な形での報告や上奏文)を提出し、皇太子の交代を求めました。
その結果、李忠は廃され、当時まだ三歳であった武則天の長男・李弘(りこう)が皇太子に立てられました。
その後まもなく、李忠は謀反を企てたとして陥れられ、処刑されました。
李弘は成長すると、生まれつき仁愛の心を持ち、有能な人物となりました。しかし、武則天は権力を独占しようと考え、李弘が皇帝に即位した後、自分の意のままにならなくなることを恐れていました。
そのため、李弘が二十歳の時、毒酒を使って命を奪ったと伝えられています。李弘の死後、武則天は自身の次男である李賢を皇太子に立てました。
李賢は非常に聡明で才能に恵まれ、高宗皇帝の政務を補佐し、見事にこなしていました。太子に立てられた後、母である武則天の権力奪取の陰謀を察知し、次兄の末路を思い出して、自身もいずれ同じ運命を辿るのではないかと感じていました。
そのような思いから、李賢は『黄台瓜辞(こうだいかじ)』という詩を作り、楽師に練習させ、宮中で歌わせることで、武則天に思い直してほしいと願ったのです。
その詩の全文は以下のとおりです。
種瓜黃台下,瓜熟子離離。
→黄台のもとに瓜を植えしが、熟れたる実は枝にたわわに垂れぬ。
一摘使瓜好,再摘使瓜稀。
→一たび摘めば、なお美しく、再び摘めば、実はまばらとなる。
三摘尚自可,摘絕抱蔓歸。
→三たび摘むも、なおわずかに実を留む、すべてを摘み尽くせば、つるを抱えて帰るのみ。
この詩は表面的には瓜を詠んでいるように見えますが、実際には瓜そのもののことではありません。武則天の四人の実子を瓜に例え、その心を改めさせる深い意味が込められています。
「瓜熟子離離」とは、陛下の子どもたちが皆、立派に成長したことを意味しています。
「一摘使瓜好」とは、長男を処罰したことで、他の子どもたちが警戒し、慎みを持ち、軽はずみな行動を取らなくなるだろうという意図です。しかし、もし二人を処罰すれば、残る子どもたちがあまりにも少なくなってしまいます。
さらに、すべてを亡き者にしてしまえば、最終的には陛下一人が孤独に残されることになるでしょう。――この詩には、そうした深い嘆きと忠告の心が込められているのです。
このような詩歌の表現は、権力欲に取り憑かれた武則天の心を動かすには、あまりにも難しいことでした。かえって、陛下が「瓜を摘む」決断を下すことを加速させる結果となったにすぎません。
調露二年(西暦680年)、李賢は太子の位を廃され、庶人となり、巴州(現在の四川省巴中県)へ配流されました。それでもなお、武則天は安心せず、四年後に使者を派遣して李賢に自害を命じました。その時、李賢はわずか三十一歳でした。
その後、武則天が崩御された翌年(西暦706年)、弟の唐中宗・李顕の勅命により、李賢の霊柩は四川から陝西へ改葬され、乾陵に合葬されることとなりました。
(翻訳 陳武)







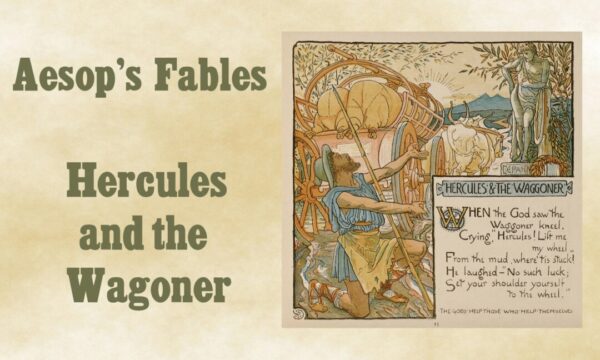
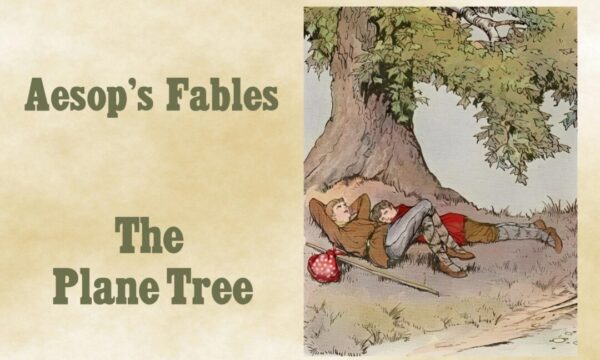









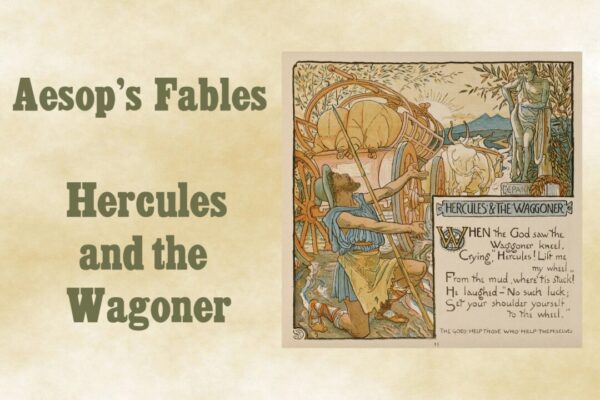
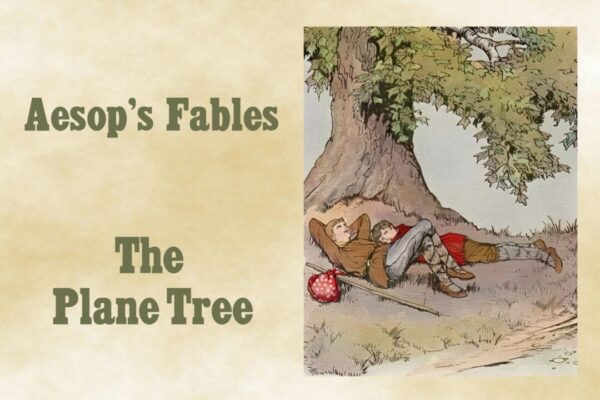

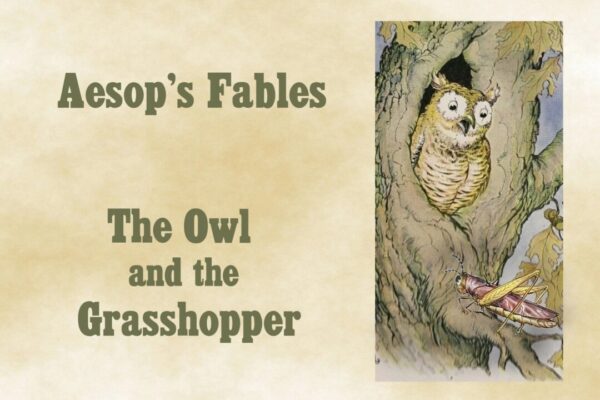

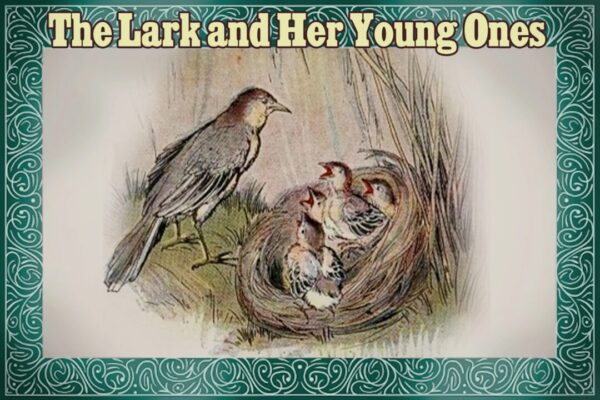
 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram




ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。