薬用植物 ツリガネニンジン、トウシャジン
キキョウ科のツリガネニンジン(釣鐘人参)やトウシャジン(唐沙参)の根は、南沙参(なんしゃじん)として漢方薬に用いられます。これらの根にはイヌリンやサポニンといった成分が含まれており、気管や気管支に溜まった痰の除去や、咳を鎮める作用があります。補陰(滋潤)作用もあるため、麦門冬(ジャノヒゲの根)や玉竹(アマドコロの根)などとともに益胃湯(えきいとう)に配剤され、脱水傾向の口渇や咳の症状に用いられることも多い薬草です。また、慢性肝炎などで喉が渇いたり皮膚が乾燥したりする場合には、地黄(じおう)や川楝子(せんれんし)などとともに配剤された一貫煎(いっかんせん)という処方を用います。
日本ではツリガネニンジンやトウシャジンを「トトキ」と呼び、食用にしています。春には新芽を軽く茹でておひたしに、秋には掘り出した根からひげ根を取り除き、茹でて油で炒めて食べます。粘膜を刺激するサポニンが含まれるため、茹でた後、水にさらすのが調理のポイントです。
(吉本 悟)
関連記事
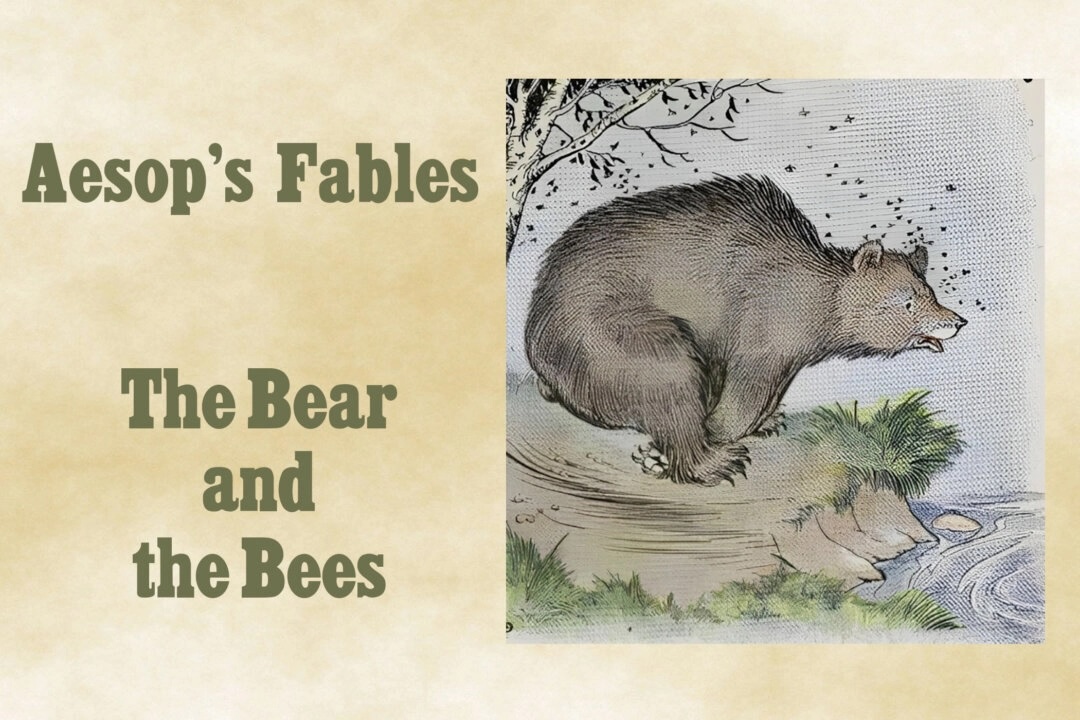
森の中で不思議な出来事が起きたクマ。怒りと冷静さの違いが生む結果とは?冷静に行動する大切さを教えてくれる、おもしろくてためになる物語です。

グルテンアレルギーが引き起こす不安や消化不良の関係について詳しく解説。中医学を通じて、心と体の不均衡がどう健康に影響するのかを学びましょう。

ラベンダーは日当たりと水はけのよい環境でよく育ちます。地植えとコンテナ、それぞれのメリットや育て方のポイントを園芸の専門家が解説します。

長時間の座り姿勢や加齢で腰がつらい方に。整形外科医の陳兆龍氏がすすめる、腰椎のケガを防ぐストレッチと、中医学のアプローチを紹介します。

炭酸飲料の新しいかたち「発酵ソーダ」が注目されています。乳酸菌や酵母が生み出す微炭酸が、腸の働きにどう作用するのか?簡単な自家製レシピとともに解説します。