元の気ってなに?
毎朝ジョギングを欠かさない近所のお年寄りに「お元気ですね」と声をかけ、しょんぼりしている友人を「元気出せよ」と励まします。普段何気なく使っているこのことば、よくよく考えてみると何とも不思議なことばです。
「元気」には大きく分けて二つの意味があります。一つは、「活動の源となる気力」ということで、「元気出せよ」の「元気」がそうです。古くには、「元気」には、「万物が生まれ育つ根本となる精気」という意味がありました。文字通り、「元の気」ということで、「元気出せよ」の「元気」はこの用法からの派生だと考えられます。
もう一つは、「健康だ」ということで、「お元気ですね」の「元気」がそれにあたります。ただ、この意味の「元気」は本来、「減気」と書かれたようです。このときの「気」は病気の意で、「病の気を減ずる→病が快方に向かう」ということです。また、病気平癒のために祈祷してその「験(ゲン)」が表れる意で「験気」とも書かれました。そして、病気が治るということは、本来の気力に戻ることであることから、「元の気」の意である「元気」と混同され、次第にともに「元気」の字が当てられるようになったようです。「元気」に直接には関係なさそうな二つの意味があるのはこのためです。
ところで、中国語の『元気』には「健康」の意味はありません。「元の気」の意とそこからの派生義しかなく、『傷元気(活力を損なう)』とか『元気旺盛(活力旺盛)』のように使われます。
(智)
おすすめ関連記事:知ってた? じゃんけんの語源
関連記事
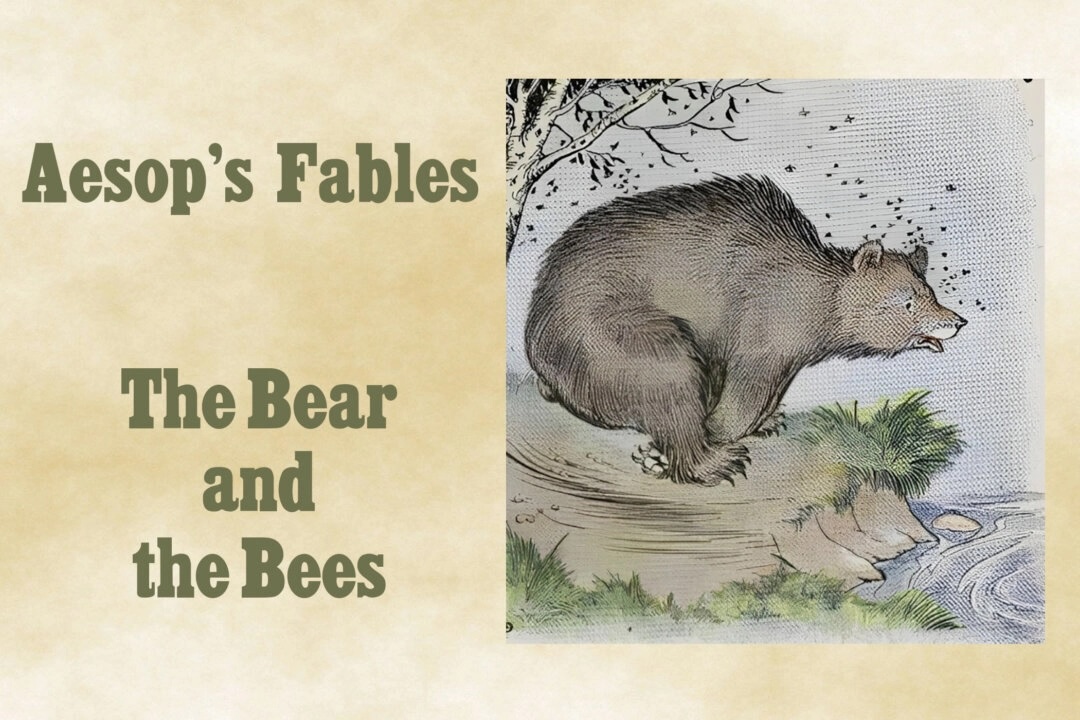
森の中で不思議な出来事が起きたクマ。怒りと冷静さの違いが生む結果とは?冷静に行動する大切さを教えてくれる、おもしろくてためになる物語です。

グルテンアレルギーが引き起こす不安や消化不良の関係について詳しく解説。中医学を通じて、心と体の不均衡がどう健康に影響するのかを学びましょう。

ラベンダーは日当たりと水はけのよい環境でよく育ちます。地植えとコンテナ、それぞれのメリットや育て方のポイントを園芸の専門家が解説します。

長時間の座り姿勢や加齢で腰がつらい方に。整形外科医の陳兆龍氏がすすめる、腰椎のケガを防ぐストレッチと、中医学のアプローチを紹介します。

炭酸飲料の新しいかたち「発酵ソーダ」が注目されています。乳酸菌や酵母が生み出す微炭酸が、腸の働きにどう作用するのか?簡単な自家製レシピとともに解説します。
