【紀元曙光】2020年1月19日
戊辰戦争は1868年1月19日(慶応3年12月25日)に、江戸の薩摩藩邸が焼き討ちに遭って消失した事件を発端とする。庄内藩指揮下の新徴組が襲撃、放火した。
▼この戦いを挟む時期を、次代の元号を冠して明治維新と呼んでいる。維新とは、中国古典の一つである『詩経』に見られる言葉だが、初めて引用したのは幕末の水戸藩士・藤田東湖とされる。
▼時代を新たにする、というのが維新の基本的な意味であろう。明治維新が「正義」であったかどうかは、分からない。ただし必然ではあっただろう。江戸幕府にとって、対外圧力が高潮する当時の世界情勢は、とても耐えられるものではなかった。
▼政治の中心は江戸にありながら装飾的な権威は京都にあり、行政は各地の諸藩に委任するという、サーカスの曲技的な方法で、徳川三百年はとりあえず平穏にやってきた。それは奇跡的な成功かも知れないが、筆者も江戸時代好きなので、良かったと思っている。
▼その江戸幕府が瓦解するに当たり、かつて関ヶ原で敗れた長州や薩摩が、恨みを忘れぬ亡霊のごとく東征してきた光景は、想像するに不気味なものがある。幕末から明治への激動の歴史は、真っ先に攘夷に沸騰した水戸藩が真っ先に消え、諸藩の動揺のなか、最後まで生真面目に武士道を貫こうとした会津藩が満身創痍となり、函館に走ったわずかな残り火が消えて、終わった。
▼戊辰戦争は、鳥羽伏見などの西国から始まった印象をもつが、花火の着火点は江戸であった。火が着くよう秘密工作を指示したのは薩摩の西郷隆盛である。歴史は、なんとも興味深い。
関連記事
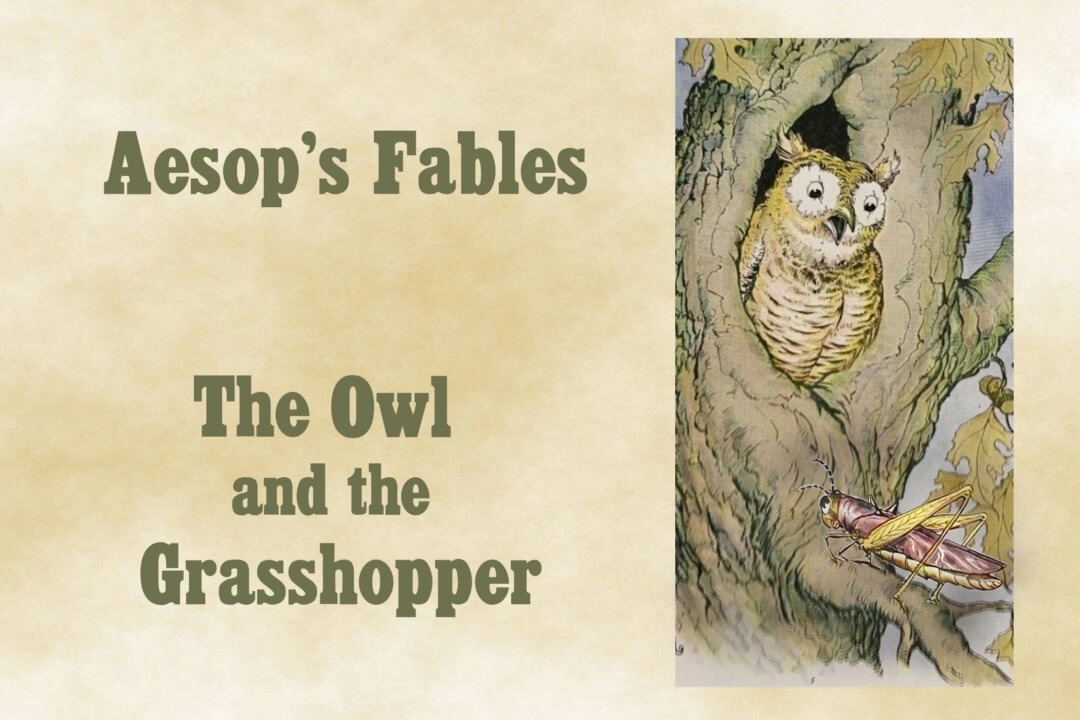
「フクロウとキリギリス」の物語で学ぶ、甘い言葉やお世辞が真の賞賛とは言えないという教訓。イソップ寓話の魅力とともに、道徳的な価値を感じてみましょう。

清明の季節は「肝」の働きが高まり不調も出やすくなります。今が旬の菜の花は、肝の熱を冷まし気の巡りを整える優れた食材。簡単に取り入れられる養生レシピとともに、春の五行養生をご紹介します。

年齢とともに増える抜け毛や白髪。実は日々の食事で改善の余地があります。髪に必要な7つの栄養素と、中医学が教える髪と内臓の深い関係について解説します。

長年うつ病に苦しんだ女性が、薬ではなく「精神修養」によって回復。絶望の中で見つけた“希望”が、人生を根底から変えた──その実例と、科学的裏付けとは。

中医学では、緑内障の原因を「怒りや憂うつ」「代謝機能の低下」「夜更かしによる精の消耗」など全身の気血の乱れとして捉え、漢方や鍼、体操で改善を図ります。