【紀元曙光】2020年1月15日
成人の日は1月第2日曜であるが、1999年までは1月15日であった。この日は小正月に当たり、本来ならば旧暦の1月15日がその日だった。
▼明治6年に新暦になってからも、「旧暦と同日」という概念が残り、あまり新旧の別を意識していないのは、日本史の不思議な現象の一つであろう。忠臣蔵の12月14日は吉良邸討ち入りの日であるが、もちろんこれは旧暦のその日である。
▼今の日本人は、すべて新暦に規準を置いてしまうから、東京高輪の泉岳寺で行われる赤穂義士祭は、毎年12月14日に行われる。年中行事といっても、伝統に基づくものではなく、娯楽や観光が主たるイベントなので新暦のほうがやりやすい。
▼日本人も昔は旧暦を併用していたし、もっと昔ならば旧暦が主で、ほかに数種類の和暦が生活のなかにあった。それは伊勢暦(いせごよみ)に代表されるように、農業を主とする当時の生活に役立つような情報、例えば吉凶や農事のかかり始めを知らせるような、生活年鑑の役割を果たしていた。
▼1月15日の小正月には、その年が豊穣であるようにとの願いから、予祝(よしゅく)として、切りとった小枝に餅花や繭玉をつけて屋内に飾った。併せて、この日に男子の元服の儀をとりおこなったことから、今日の成人式へとつながることになる。
▼主に中華圏の国だが、東アジアの一部の国(中国、ベトナム、台湾など)では、まだ旧暦(農暦)を併用している。今年の旧正月は1月25日。多くの外国人が日本を訪れるようになった今日、日本人も昔のカレンダーに興味をもって良いように思う。
関連記事

春夏は“木火”の季節。体の内側から整えるには「金水(肺と腎)」のケアが鍵です。黒きくらげと白きくらげを使った簡単レシピで、陰陽のバランスをおいしく調えましょう。

海と大陸を結ぶ運河の国、パナマ。歴史ある街並みと世界遺産、美食とにぎわい、そして巨大貨物船が行き交う運河の絶景をめぐる濃密な24時間をご紹介します。

スムージーだけじゃない!チアシードは心臓や腸を守る栄養の宝庫。オメガ3、繊維、鉄分が豊富な理由と、手軽に取り入れる方法をご紹介します。

タブレットやPCより手書きが脳に効く?最新の脳波研究が明かした、書くという動作が記憶や創造力に与える効果と、その驚きの仕組みとは。
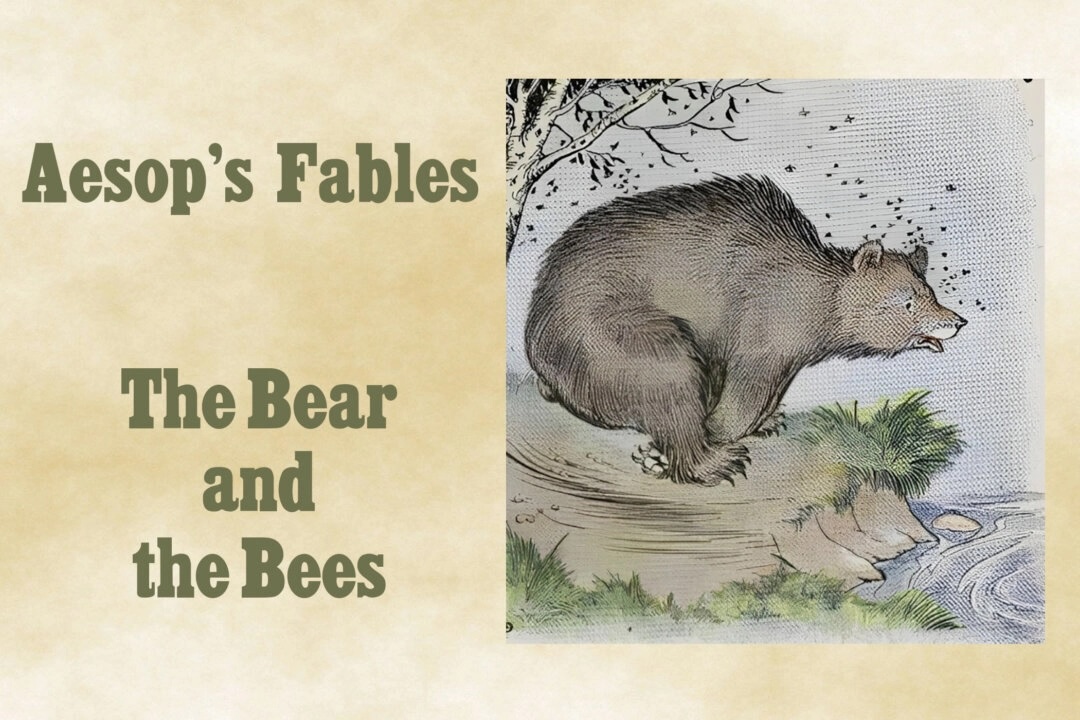
森の中で不思議な出来事が起きたクマ。怒りと冷静さの違いが生む結果とは?冷静に行動する大切さを教えてくれる、おもしろくてためになる物語です。