【歌の手帳】はちす葉の
蓮葉(はちすば)のにごりに染まぬ心もてなにかは露を玉とあざむく(古今集)
歌意「蓮の葉は、泥の濁りに染まらない清らかな心をもっている。なのに、なぜその葉の上に置く露を玉のように輝かせて、人をあざむくのだろう」。
僧正遍照(そうじょうのへんじょう816~890)の作。俗名を良岑宗貞といい、小野小町に恋しました。側近として仕えた仁明帝が崩御した850年に、出家して遍照となります。
『小倉百人一首』にもある遍照の歌「あまつかぜ雲の通ひ路吹き閉じよ乙女の姿しばしとどめん」。なぜ僧侶でありながら「天女の舞姿がもっと見たい」などと詠ったか。以前から不思議だったのですが、これは出家前の作でした。
出家後は、表題の歌のように、やや理屈っぽい歌風になります。
(聡)
(読者の皆様へ)下のコメント欄へ、ご自作の「短歌」「俳句」をお寄せください。歌にまつわるお話も、ぜひお書き添えください。皆様とともに作り上げる、楽しいコーナーにしたいと願っております。なお、狂歌や川柳は、また別の機会とさせていただきます。お待ちしております!
関連記事
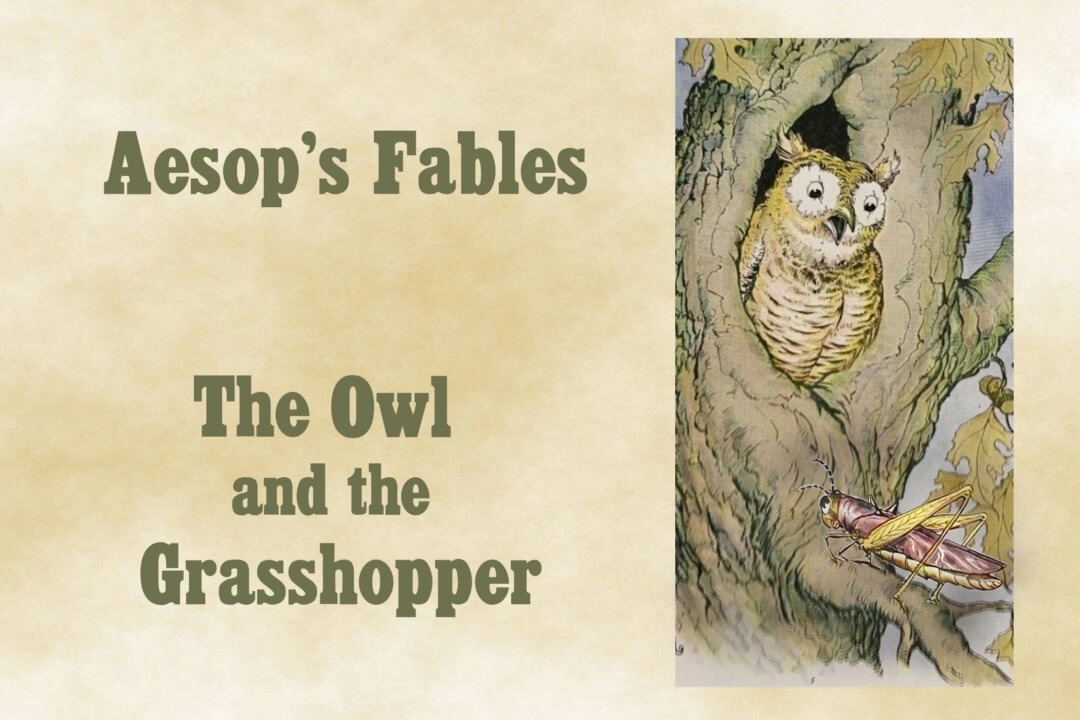
「フクロウとキリギリス」の物語で学ぶ、甘い言葉やお世辞が真の賞賛とは言えないという教訓。イソップ寓話の魅力とともに、道徳的な価値を感じてみましょう。

清明の季節は「肝」の働きが高まり不調も出やすくなります。今が旬の菜の花は、肝の熱を冷まし気の巡りを整える優れた食材。簡単に取り入れられる養生レシピとともに、春の五行養生をご紹介します。

年齢とともに増える抜け毛や白髪。実は日々の食事で改善の余地があります。髪に必要な7つの栄養素と、中医学が教える髪と内臓の深い関係について解説します。

長年うつ病に苦しんだ女性が、薬ではなく「精神修養」によって回復。絶望の中で見つけた“希望”が、人生を根底から変えた──その実例と、科学的裏付けとは。

中医学では、緑内障の原因を「怒りや憂うつ」「代謝機能の低下」「夜更かしによる精の消耗」など全身の気血の乱れとして捉え、漢方や鍼、体操で改善を図ります。
