ここ暫くのニュースは新型コロナウイルスで持ちきりであるが、これについては前回書いたので、今回は敢えて違う話題を取り上げることにする。
最近、新型コロナウイルス問題がなければ、もっと大きく報道されたであろう芸能ニュースが二つあった。一つは槇原敬之の逮捕、もう一つは中居正広の事務所独立である。この二つのニュースで思い出されるのが、槇原敬之が作詞・作曲し、SMAPが歌った「世界に一つだけの花」である。
2003年にリリースされたこの歌は大ヒット曲となり、当時は中学校などでも盛んに歌われたようである。当時の中学生と言えば、現在30歳前後の世代である。この曲がヒットしていた当時、私には一つ疑問があった。それは、この曲の歌っている人たちが、その歌詞をどのように解釈していたかである。私は二つの正反対の解釈がありうると思っていた。
一つは、自分は素のままでも独自性のある存在なのだから、宝飾品やブランド物のバックで飾らなくてもいい、特別なものは欲しがらない、他人の富や成功に嫉妬しないという解釈である。もう一つは、自分はもともと特別な存在なのだから、何の努力をしなくてもいい、それでも社会から支援されて十分なお金をもらう価値のある人間だという解釈である。実は当時、周囲の人にこの歌詞をどちらの意味で解釈しているか何度か聞いてみたことがある。誰に聞いても、そこまで深く考えていないという回答だった。ただ、深く考えていなくても、無意識にどちらかの解釈をとっているはずであると私は思っていた。
当時存命だった筑紫哲也は、この曲をいたく気に入っており、「反戦歌」として持ち上げていた。この歌詞を反戦歌と捉えるのは、どちらかというと後者の解釈をしているのだろうと考えていた。私は、前者の解釈ならこの歌はいい歌だと思うが、多くの子どもたちが後者の解釈で歌っているとしたら、将来困ったことになるのではないかと恐れていた。それから約10年後、この懸念は現実のものとなった。子どもの頃、世界に一つだけの花を歌って育った学生には、その歌詞に後者の意味で影響を受けたと思われる振る舞いが、しばしば見られるようになったのである。そのエピソードを2つ紹介しよう。
あるとき、学生に外国の学会から電子メールが来ているはずだと言った。彼は「来ていない」という。私はおかしいと思って「そんなはずはないけど。本当に来ていない?」と聞いた。そうすると彼は「絶対来ていない」と自信満々に言う。そこで「僕に検索させて」と言って、パソコンのメールボックスを検索すると、その学会からのメールが5秒で見つかった。
またあるとき、別の学生が学会発表の練習をすることになっていた。そこで始める前に「発表時間は何分?」と尋ねた。すると「分からない」と言う。私が「そんなはずはないでしょう。学会からのメールか学会のホームページには必ず載っているはずだけど」と言うと、彼は「絶対にない」と言い張る。そういう押し問答をしている横から、中国人留学生がその学会のホームページを調べて、「ありました。15分です。」と教えてくれた。
いずれのケースも、学生たちに共通するのは「根拠のない自己肯定感」であった。それが邪魔になって、ほんのちょっとした努力すら怠る。これはまさに、世界に一つだけの花の歌詞を後者の意味に解釈して歌い続けてきた結果育まれてきた価値観ではないかと強く感じたことを覚えている。ちなみに、世界に一つだけの花ブームを経験していないせいか、今の学生がこうした極端な反応を示す例に遭遇したことはない。
前回、養老孟司著の「バカの壁」を紹介したが、この本が出版されたのも2003年である。その続編「超バカの壁」で養老氏は次のように書いている。
ナンバーワンよりオンリーワン、世界に一つだけの花だというような言い方が支持を得るのは戦後教育の賜物でしょうか。しかし、若い人にはこの逆を言ってあげないと救われないと思っています。あなたはただの人だと言うべきです。(中略)
そもそも個性というのはあるに決まっている。そこに自信があればいちいち口に出すこともない。わざわざオンリーワンだ何だと声高にいうというのはその確信が弱いからこそだと思えるのです。他人に認めて欲しい。だからわざわざ主張をするのです。
上述の学生の振る舞いを見るにつけ、養老氏の先見の明を感じずにはいられなかった。
冷戦後、「世界に一つだけの花」と同様に、根拠のない自己肯定感を高める教育を行ってきたのが、米国の学校教育である。その結果、米国のミレニアル世代は極端に左傾化している。自ら社会主義者であることを公言する米国大統領選の民主党有力候補バーニー・サンダースを熱狂的に支持しているのも、ミレニアル世代が中心である。
実は、根拠のない自己肯定感を高めると、左翼的考えを持ちやすくなる。その理由は、このコラムの初回「なぜ人は共産主義に騙され続けるのか」で書いた内容に関連する。該当箇所を引用しよう。
日本と欧米の左翼に共通する点は、いずれも自らの属する社会や文化を憎み、その破壊を意図していることである。その憎悪の感情は、過大な自己評価ゆえに、周囲が自分を正当に評価していないと不満を持つことから生じている場合が多い。
つまり、根拠のない自己肯定感は過大な自己評価につながり、それが社会への不満を高めて左翼運動へのシンパシーを強めていくというわけである。
当然ながら、左翼は自尊心を強める教育の支持者である。彼らは、自己肯定感をもつことによってはじめて、人間は他人にやさしくなれると主張する。しかし、日本の「世界に一つだけの花」世代を見ていると、その主張は説得力が乏しいように思われる。
上述の中国人留学生が当時、研究室の同僚と学会から帰ってきたときに、私に話したことがある。学会で装置のデモをするため、大きな荷物を持っていったのだが、荷物の運搬で苦労している学生が横にいても、日本人学生は全く手伝う気配がなかったそうである。この例に限らず、世界に一つだけの花世代には、自分さえよければいいという行動が他の世代より多いように見えるのは気のせいだろうか。
なお、米国の学校教育で行われている自尊心を高める教育の実態は、米国YouTubeチャンネルPragerUの動画の一つ“Why Self-Esteem Is Self-Defeating” で紹介されている。日本語の字幕を私がボランティアで付けているので、字幕機能で日本語字幕を選んで是非ご覧いただければと思う。
執筆者:掛谷英紀
筑波大学システム情報系准教授。1993年東京大学理学部生物化学科卒業。1998年東京大学大学院工学系研究科先端学際工学専攻博士課程修了。博士(工学)。通信総合研究所(現・情報通信研究機構)研究員を経て、現職。専門はメディア工学。特定非営利活動法人言論責任保証協会代表理事。著書に『学問とは何か』(大学教育出版)、『学者のウソ』(ソフトバンク新書)、『「先見力」の授業』(かんき出版)など。
※寄稿文は執筆者の見解を示すものです。
※無断転載を禁じます。



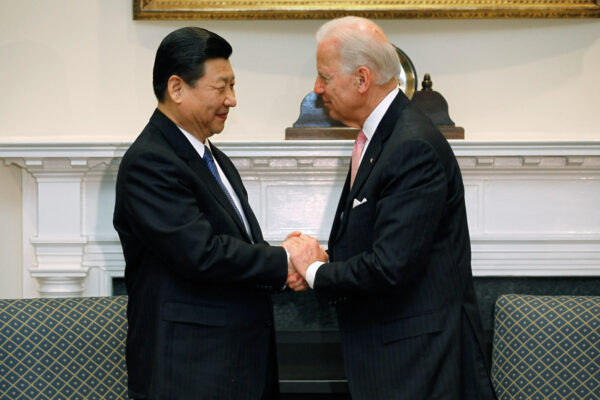





 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram




ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。