[小山町(静岡県) 29日 ロイター] – 東京五輪の女子自転車タイムトライアルが行われた28日、最下位にもかかわらず多くの記者の注目を集める選手がいた。「さまざまな理由で国を離れることを余儀なくされている8200万人の人々に、希望と平和のメッセージを送るため私はここにいる」──難民選手団の1人、マソマハ・アリザダ(25)はレース直後に記者たちにそう語った。
イスラム系シーア派の少数民族ハザラ系のアリザダは、1996年にアフガニスタンで生まれた。タリバンが権力を掌握する不安定な政治情勢の下、隣国イランに移り住み、10歳で一度カブールに戻った。「難民チームを、そして女性の権利を代表してここに立てることをうれしく思う」と話すアリザダは、難民として認められたフランスで暮らしている。
イランにいたころ、アリザダが夢中になって見ていたのが日本の映画だ。タイトルは覚えていないというが、女性が1人で屈強な男性たちに立ち向かっていく姿に魅了された。「私の国や私の育った文化では、女性は常に取るに足らないものとされていた。当時は自分の置かれていた状況と映画の中と、どちらが現実であるか理解できなかった」と、アリザダはロイターとのインタビューで語った。
あの映画の女性のように強くなりたいと思った彼女は、テコンドーやバスケットボールをはじめ、複数のスポーツに挑戦した。そして自身の才能を発揮できると行き着いたのが自転車だった。
しかし、アフガニスタンではつらい経験をした。女性が自転車に乗ることは「異常」だとみなされ、心無い言葉で嘲笑や非難をされただけでなく、石を投げられたり、見知らぬ人にすれ違いざまに殴られたりもした。「彼らが女性にして欲しくないことを私がしていたから」と、アリザダは振り返る。自身を取り巻く環境への疑問は日に日に大きくなっていった。誰にでも自分がしたいことをする権利はあるはずだ、と。
一番の理解者となってくれたのは父親だった。自分がやりたいと思ったことがあるのなら最後まで諦めずに頑張れと今も励まし続けてくれる父。アリザダは試合後、記者団の取材の中で何度も感謝の言葉を口にした。
アリザダは2016年に姉妹と共にフランスのドキュメンタリー映画に出演した。それをきっかけに支持が広がり、17年に難民認定されて家族とともに同国へ移住した。北部リールの大学で土木工学を学ぶ学生でもあり、勉強と練習を両立させながら国際オリンピック委員会(IOC)から奨学金を取得、東京出場を果たした。
そのフランスでも、イスラム教徒の女性が身に着けるヒジャブで常に頭を覆い肌を出さない服装をしていることに奇異の目が注がれることがあると苦笑いする。文化としても女性としてもそれが「私の選択」と語るアリザダは、五輪でもいつもと変わらずヒジャブ姿にヘルメットをかぶりレースに臨んだ。
五輪の大舞台に立つという夢はかなえたが、アリザダには次の大きな目標がある。大学で土木工学の知識を深め、祖国アフガニスタンのインフラ整備、特に橋の建設に尽力したいという。
「アフガニスタンを嫌いだと思ったことは一度もない。差別など多くの問題はあるが、私はアフガニスタンを愛している」とアリザダは話す。ズーム越しのインタビューの最中、試合中の気迫あふれる姿とはまた違った希望に満ちた表情を見せてくれた。「いつかアフガニスタンに平和が訪れたら、女の子たちが何の屈託もなく自転車に乗っている姿を見てみたい」とアリザダは語った。
(田中志保 編集:久保信博)






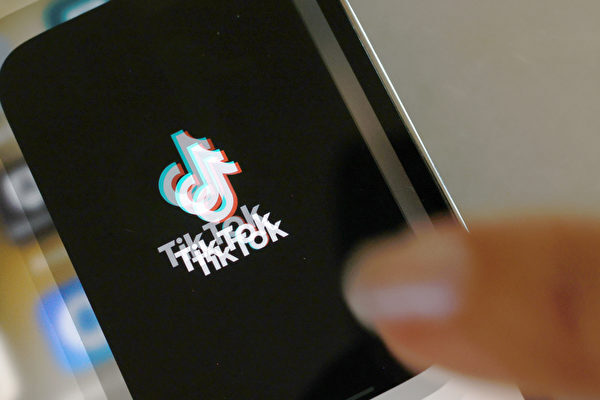


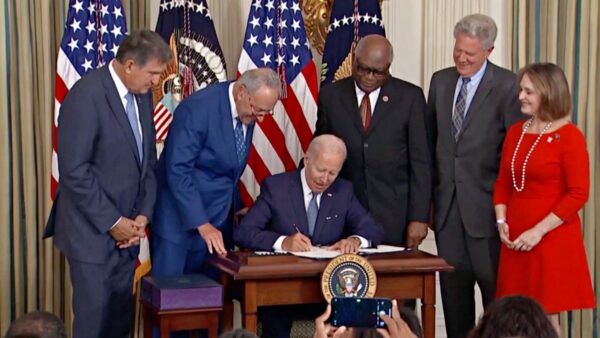
 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram




ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。