ーー8月末の概算請求について。反撃能力を念頭に防衛力の抜本的強化を掲げ、過去最大となる5兆円5000億円相当となった。
反撃能力を備えるということは、当然のことだ。専守防衛ならば抑止力さえない。相手は(日本を)叩き潰せる十分な準備をしない限りは攻めてこない。叩かれて終わりなのか。日本は反撃能力を持って、一発殴ってきたら三発殴り返すぐらいの用意がなければならない。
防衛費拡大といっても他の先進国と比較すればまだまだ低い。F-35なんて高価なもの買ってしまったから。揃えた装備品を常時稼働させるということは現状の予算では資金繰りの面で難しい。
自衛隊は、米軍や旧日本軍のように工廠(こうしょう)を持たない。自衛隊を守る防衛産業がなければならない。民間の防衛産業と呼ばれる、三菱重工業、川崎重工業、IHI、NEC、日立、三菱電機とかに頼っている。防衛産業が儲かって、経営が立ち行くようにしなければ自衛隊の戦力強化にならない。
日本が防衛予算を2倍にするというと、米国のメーカーはもっと日本に売り込もうとするだろう。増えた予算の多くを米国製の武器購入に取られては、日本の防衛産業の強化が出来ないし、実質防衛強化にもつながらない。防衛予算の多くが日本国内で回るようにしなければならない。
ーー中国当局者との交流について。
中国の記者に言われたことがある。「田母神さんは日本の3大右翼の一人だ」と。それは誰かと聞いたら「石原慎太郎、西村慎吾、田母神俊雄」だと答えた。
私は現役で中国と歴史論争をした人間だ。統合幕僚学校長の時、中国の範長龍陸軍中将・統合幕僚副長に会った。のちに中国人民解放軍のトップ、上将になった人物だ。
彼とは歴史論争を展開した。中国の国防大学を訪問したときだ。30分の対談時間が範長龍陸軍中将との間で設けられた。彼は自分は満州出身だという。子供の頃から日本軍がどれほど残虐であったか、親や親戚から散々聞かされてきた。私の体に染み付いていて忘れることができない、という。
一方日本の悪口をさんざん聞かされて、私はだんだん腹が立ってきた。「私は呼ばれてきたお客さんだぞ」と。30分間文句で終わるのはたまったものではないと、10分後に私は手を上げて制止して、私にも話をさせてほしいと。それから反論した。
当時の満州の人口のことだ。1932年満州建国時は3000万人だった。人口動態は中将はご存知かと。13年後の1945年、人口は5000万人を超えた。残虐行為が行われるような地域に人は集まらない。満州は人口が毎年100万人も増えるほど豊かで治安が良かったということではないか、これが歴史的な証拠だ。だから私はあなたの言う歴史認識には同意できない、こう伝えた。
ーー相手の反応は。
びっくりしたような顔をしていた。日本人は反論しないと思っていたようだ。しかし「歴史認識を超えて軍の交流は進めよう」と範長龍中将は言った。
だけど中国側はいじわるをする。北京訪問時、私は空将(空軍中将)だった。入国時、礼儀として相手国も階級を揃えて迎える。こちらが20数名で訪問したので相手も陸軍中将以下相応の人数を用意して到着時のレセプションをやってくれた。
軍の恒例で帰る前の夜、答礼のレセプションを日本側が準備した。一流ホテルの北京飯店でこちらがもてなす会食を設けた。しかし答礼レセプションには将軍は誰も来なかった。空港に我々訪問団を出迎えた大佐以下4人しか来なかった。大佐のほかには彼の部下の少佐が1名と通訳を含む中尉2名だったかな。4人しか出席しなかった。
他の人たちは「突然仕事ができていけなくなった」という。これは嘘だろう。私が歴史認識の論争を行ったことに対する抗議だろう。
以来、国防大学には私の訪問時の写真が7、8年にわたり飾られていたそうだ。私の後輩がその後も訪問しているが変わっていないそうだから。「あいつには気をつけろ」という意味かもしれない。
日本には、「相手はそのうちわかってくれるだろう」という文化がある。「相手の言うことをこちらが聞いて認めてあげていれば、相手はそのうち気づくだろう」と、そう思い込んでいる。
しかし、これを外交の場でやってはいけない。何も言わずに通じるはずがない。反論しなければ相手の言い分を認めたということになる。そう思い、私はその時反論した。言ったら関係悪くなると心配して日本人は言わない。言わないと、国益を損なっている。
ーー岸田政権は中国関係は「言うべきは言う」と説明しているが、どう評価する?
もうちょっと気合い入れた方がいい。








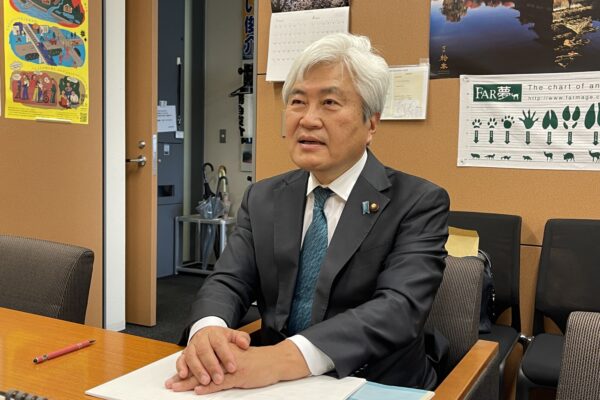

 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram




ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。