2018年5月、中国領事館職員だった董羅彬(とう らひん)さんは、駐在先のニュージーランドで政治亡命した。その直後に大紀元の取材に応じたが、安全への配慮から、報道はしばらくの間見送られた。
赴任からわずか2か月後の出来事だった。董さんはなぜ亡命を決意し、厳重な警備と密告体制のなか、いかにして中国領事館から脱出できたのか。彼の口から語られたのは、あらゆる自由を剥奪され、海外でも高圧的な管理に服さなければならない中国領事館員の苦悩と辛酸だった。
自由を剥奪された中国領事館員
中国共産党の人権抑圧は在外公館の職員も例外ではない。外交官を含む職員は相互の監視を命じられ、消費活動すら制限されていた。
公的な身分証明書となるパスポートは、董さんはオークランド空港を出た瞬間に没収された。中国領事館の2階には機密保管庫があり、董さんによると、領事館員のパスポートは全てそこに保管されていた。24時間体制で警備され、一般職員が入るのは不可能だった。
董さんによると、駐在期間中は給料が直接支払われず、帰国後に一括して振り込まれる。長く働けば働く程、より多くの給料を当局に押さえられることとなるのだ。「中国領事館員には中国共産党に反感を持つ人も少なくないが、亡命者が少ない理由の一つに、給料を押さえられていることが挙げられる」。個人用品を揃えたいときは、一度に600米ドルを限度に、領事館から「借金」していたという。
領事館員の単独行動は禁じられ、外出する際には少なくとも3人で行動しなければならず、互いに監視することが求められた。部外者との接触も禁止され、違反すれば帰国を命じられる恐れがあった。
さらに「地元の新聞を読んだり、外部のウェブサイトを閲覧したりすることは許されなかった」と董さんは振り返る。スマートフォンのSIMカードやインターネットへの接続機器は全て領事館が用意したものを使った。私たちの全ての行動は筒抜けだと、総領事は訓示していた」。

蘇る恐怖の記憶
キリスト教徒の家庭に生まれた董さんは幼い頃から中国共産党の残酷な手段を目撃してきた。
「私が5歳のときだった。中国共産党はキリスト教への取り締まりを強化し、教会を支配下に置こうとした。もちろん村の信者たちは抵抗した。すると武装警察と軍隊が村を包囲し、神父や信者らに暴行を加えた。昼間にはレンガと棍棒で殴り、夜に出かけようものならそのまま射殺された」。
「神父を助けようとした信者らは家の庭に拘束され、殴られた。一人が気絶すればその体の上にもう一人乗せて殴り続けた。亡くなった人もいれば、障害が残る人もいた。血は庭の外にまで流れてきた」。
信仰への弾圧は、董さんの亡命に対する決意を強めた。いっぽう、幼い時の経験から、亡命に失敗して中国共産党の手にかかれば命が危ないとわかっていた。
塀の向こう側に広がるのは未知の世界。英語も話せず、頼れる者もいない。不慣れな異国の地でどうやって生き抜いていけばいいのか。そして国内に残してきた最愛の家族はどのような仕打ちに直面するのか。決して容易な決断ではなかった。
自由への限りない渇望と目の前に横たわるいくつもの障壁。二者の間で董さんは葛藤した。「塀の向こう側に自由な世界が広がっていると知っていた。でも、最初の一歩はなかなか踏み出せなかった」。
脱出の試み
董さんはまず、秘密のルートで現地のSIMカードを入手した。「夜になると、このSIMカードを使って海外のウェブサイトを閲覧した。ボイス・オブ・アメリカ、ドイチェ・ヴェレ、大紀元、BBCなどを見て、人権と信仰の自由を求める正義の声がこれほど多いのだと知った。これほど勇気づけられたことはなかった」。
董さんはその後、外の世界へと続く隙間を見つけた。当時、オークランド中国領事館は隣接する物件を購入したばかりだった。改修工事が続き、出入り口の扉は鍵ではなくワイヤーロックが外側から巻かれていた。力ずくで押せば隙間ができ、内側から手を伸ばしてロックを外すことができた。新しい物件の防犯カメラはまだシステムに接続されていなかった。
ある日の真夜中、ついに一人抜け出した。中国領事館からほど近い道路を挟んだ向かい側にカトリック教会を見つけ、神父と会話することができた。「神父はインド系で、英語しか話せなかった。翻訳ソフトを介してコミュニケーションをとった」。夜が明けないうちに戻ってきたため、誰にも気づかれることはなかった。
董さんはその後も秘密の出入りを繰り返しては教会に通った。しかし自由な日々を謳歌できるのも、束の間だった。
(つづく)






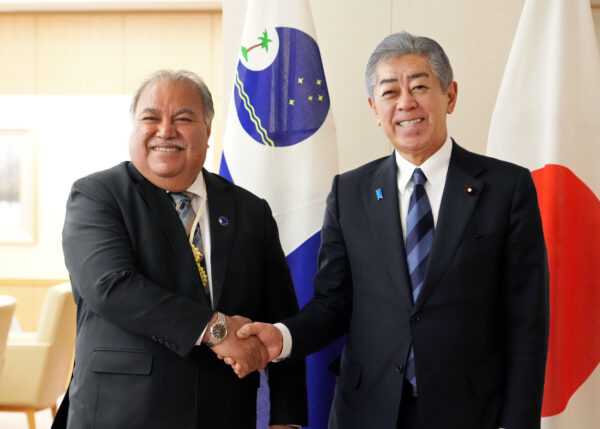



 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram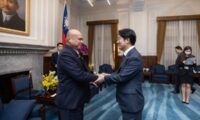




ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。