10月14日、中国共産党は台湾海峡で大規模な軍事演習を行い、その夜に終了を宣言した。この突然の軍事演習は国際的な注目を集めた。中国共産党の軍事演習は、頼清徳総統の「祖国論」に対する発言を狙ったものか、あるいは台湾統一の大戦略の一環か、疑問が残る。
一方で、北京は最近、沿海地域の産業を中西部や内陸に移転させるよう求める文書を発表し、中国共産党が何らかの動きを進めていることを示唆した。中国共産党はどのような大規模な計画を進めているのだろうか?
中国共産党が突如として軍事演習を行い、台湾封鎖作戦計画の第一歩を実施
元中国共産党海軍中佐の姚誠(ようせい)氏は、新唐人の『菁英論壇』番組で、今回の「聯合利剣-2024B」が単なる軍事演習ではなく、台湾封鎖作戦のシミュレーションであり、具体的な作戦計画に移行する第一歩であり、兵力の集結を目的としていると述べた。作戦計画の第一段階の演練の主な目的は、部隊が迅速に戦闘位置に集結することであり、ミサイル発射に関することではない。中国共産党党首の習近平は、陝西で軍隊の政治工作会議を開催した後、作戦予案を作戦計画に変更し、実行計画はすでに策定されていた。中国共産党は頼清徳総統が5月20日に中華民国の総統に就任し、双十節の国慶講話を行うタイミングを捉えて、計画の第一段階の科目を実施した。今後も計画の科目や作戦計画に基づいて段階的に実施していくだろう。
姚誠氏は中国共産党海軍に在籍していた際、台湾封鎖作戦の予備計画の一部を修正することに関与した。その内容は多岐にわたった。
今回は高度に機密性のある状況下での迅速な集結が行われる。具体的には、海軍と空軍に関して、東部戦区は五つの主要な科目を発表し、最初のものは軍種の合同突撃だ。
軍種とは、東部戦区において陸軍、海軍、空軍、ロケット軍の四つの軍種が迅速に集結することを指す。実際には、まだ動いていない部隊や一般には知られていない部隊も存在するが、全ての部隊は準備が整っている。通常の規模に基づくと、今回台湾周辺の六つの地域に展開する兵力は、航空機が125機、艦艇が17隻で、4隻の海警船は含まれていない。
後備兵力は四つの基数で構成され、基地での第一レベル戦闘準備も125機の航空機だ。第二レベル戦闘準備に入ると、その数は二倍、つまり250機になる。第一レベル戦闘準備はパイロットが戦闘機のコックピットに座っている状態で、第二レベル戦闘準備はパイロットが空港に到着し、全旅団の航空兵と航空機が滑走路に集結し、要員は自宅で待機している。これは作戦計画の重要な部分だ。
秘密作戦
今回の軍事演習は、突然実施され、命令が出されたのはわずか1時間あまり前のことだった。部隊は事前に通知を受けておらず、もし通知があった場合、情報が漏れる可能性が高かったであろう。前の晩、多くの隊員が「今晩は早めに寝て、明日の朝に用事がある」と話していたが、それが作戦計画に関するものとは言えなかった。したがって、今回の軍事演習の計画は台湾だけでなくアメリカにも反応を許さず、中国共産党軍も突然命令を受けて急遽集結したという。
ミサイル部隊と遠距離砲兵部隊は、同時に集結し準備を整える必要がある。ロケット軍については詳細は不明だが、確実に準備が整っていると考えられる。特にミサイル部隊は、包囲の過程で特別な状況が発生しないように配慮している。私たちの理解によれば、2つの集団軍の8つの支援連隊が陣地に入り、いくつかの電子妨害部隊も準備が整っているものの、まだ動いていない状況だ。
姚誠氏は、最近中国共産党が太平洋に向けて大陸間弾道ミサイルを発射したことが、台湾封鎖作戦計画の一環であると指摘した。中国共産党が台湾を制圧する際の主な課題は、反介入作戦であり、アメリカの介入を防ぐことだ。
大陸間弾道ミサイルの発射は、アメリカに対する警告であり、「私はあなたの本土を攻撃することができる」というメッセージを発信している。中国共産党の核兵器はアメリカのものに比べて劣っているため、使用には特定の原則が存在する。つまり、「私は報復能力を持っていますが、あなたを壊滅させる力はありません。しかし、この報復能力を軽視してはいけません」ということだ。
姚誠氏は以前、中国共産党が武力による台湾の統一をほぼ放棄したと述べた。台湾への上陸には非常に高い犠牲が伴い、軍隊がそれを望んでいないからだ。その代わりに、台湾封鎖に切り替えた。1986年に策定された台湾封鎖作戦計画は、封鎖によって台湾内部に混乱、経済崩壊、国民の恐慌を引き起こし、武力による降伏を迫ることを目的としている。
しかし、上陸を放棄するのは一時的な措置であり、特定の状況が整えば再び上陸する可能性があり、これには多くの要因が関与しており、アメリカの選挙、中国共産党内部の安定、習近平の軍に対する指導力、来年の第20回中央委員会第4回全体会議などが含まれるという。全体会議の後には軍の委員会の拡大会議が行われ、習近平の指導部や戦前の人員配置が求められるだろう。
産業移転:戦争準備の新たな段階
テレビ製作者の李軍氏は『菁英論壇』で、中国共産党国務院が文書を発表し、資金、技術、労働を密集させた産業を中国の東部から中部や西部、中心都市から内陸部へ秩序正しく移転させることを推進していると述べた。この文書には軍事的な戦備に関する具体的な記述はないが、戦争準備に関連していることは明らかだ。中国共産党は西部開発を引き続き推進しており、今回この問題を強調した理由は、今年に入ってからアメリカが台湾での戦争の可能性について言及していることと密接に関係していると考えられる。
アメリカのインド太平洋司令官は、台湾海峡で戦争が発生した場合、アメリカが中国沿岸の交通ハブや重要な軍事施設、製造業を破壊する意向を示している。これは沿岸地域全体を麻痺させることを意味する。また、アメリカ軍は最近、台海での戦闘が始まると「地獄のような状況」が現れると警告している。したがって、中国共産党が戦争を起こすつもりであれば、ハイテク産業や製造業、軍事産業の企業を内陸に移転させる準備をすることが必然的な行動と考えられる。
李軍氏は、中国共産党の今回の動きが非常に重要である一方で、表面的には隠蔽性が強いと指摘した。この動きは、9月25日に国務院が発表した就業に関する指導文書に含まれており、就業圧力を解決するかのように見えるが、国内の一部の学者は、これを重要な国家戦略と見なしている。現在の産業移転は非常に困難であり、社会全体の環境が大きく変化しているため、政府の行政命令だけで人材、資金、技術を移転することはほぼ不可能だ。このような移転の具体的な成果について、李軍氏はあまり期待していないと考えている。
このような大規模な産業移転は、中国共産党が政権を握って以来、すでに四回行われており、1960年代の三線建設がその一例だ。
三線とは、戦略的な位置に基づいて全国を前線地域、中間部地域、後方部地域に分けたもので、略して一線、二線、三線と呼ばれている。
第三線地域は海岸線から最も近い地点でも700キロ以上離れており、周囲には青藏高原、雲貴高原、太行山、大別山などの山脈が天然の防壁として存在している。
特定の状況下で戦争の準備が必要な場合、第三線地域は理想的な戦略的後方支援地となる。
1960年代には、戦争準備のために三線が強調され、多くの工場や施設が偏遠地域に建設されたが、1980年以降、ほとんどの三線地域の企業は倒産した。
「大紀元時報」の編集長である郭君氏は『菁英論壇』で、三線建設における多くの工場の移転が1970年代に完了したと述べている。重工業プロジェクトや兵器工場、研究機関はほぼ完成しているが、関連工場などの供給チェーンは未完成だ。また、三線地域は交通が不便で、多くの工場が山の谷間に建設されているため、安全性が重視されているが、経済的利益はほとんど考慮されていない。
核兵器の地下保存
そのため、改革開放が進むにつれて、企業が利益を重視するようになると、これらの企業は衰退するか、都市に移転するか、あるいは別の用途に転用されることになる。1980年代の初めには、プロジェクトは主に地下長城の建設に焦点を当てていた。山の内部には地下トンネルがあり、多くの都市の交通はこれらの地下トンネルを利用している。
郭君氏は、中国共産党の核兵器は主に陸上から発射されることをベースとしており、海上や空中の核兵器は信頼性が低いと述べた。陸上の核兵器には主に二種類あり、一つは固定式で、地下施設にあるミサイルサイロで、発射時にはサイロの蓋が開く。この固定式の核兵器は、戦争が勃発すると敵から厳重に監視され、必ず攻撃されて特定の地点で破壊されることになる。
もう一つは、移動式の大陸間弾道ミサイルを運ぶ大型トラックや列車を使った輸送方法で、これにより攻撃を回避しやすくなる。アメリカの報告によると、中国共産党の移動式核兵器の一部は、中国中西部の地下トンネル、通称「地下長城」に隠されており、これは最高機密とされている。
その長さは数万キロに達し、内部は広々としていて、二台の大型トラックが並行して走行できるスペースがあり、その中には巨大なショッピングモールも存在している。
この地下長城は1970年代初頭に設計され、1980年代にも建設が続けられた。
戦争の準備
当時の党首であった毛沢東は、世界大戦が勃発するのは時間の問題だと考えていた。中国共産党の経済は悪化し、工業も振るわなかったため、戦争をできるだけ先延ばしにすることを提案した。鄧小平の時代に入ると、中国共産党は国際情勢に対する見方を変え、戦争は回避可能であると認識するようになった。そのため、毛沢東時代のすべての計画と戦略は戦争に備えるものだったが、1950年代の朝鮮戦争で、中国共産党は現代戦争の威力を目の当たりにした。
朝鮮戦争では、中国共産党軍とアメリカ軍の死傷者比は約10対1であり、これはアメリカが、朝鮮戦争において限定戦争の戦略と戦術を採用したためだ。したがって、毛沢東の考えは、戦争が勃発した場合、中国共産党は沿岸地域を放棄し、中部と西部の山岳地帯に退避して抵抗を続けるというものだった。
したがって、中国共産党は1960年代から70年代にかけての建設において、基本的に沿海地域には投資しなかった。これは毛沢東の戦略思想に基づいており、彼は持久戦と人民戦争、つまりゲリラ戦を志向していた。中国共産党が言う敵を人民戦争の大海に引き込むというのは、戦争を通じて相手を経済的に崩壊させることを意味する。中国共産党は死者や貧困を恐れず、彼らの言葉によれば、中国人は草を食べても生き延びることができると言う。この考え方は対日戦争の理念とも関連している。
中国共産党は毛沢東思想をまとめ、戦争に関する二つの要素を挙げている。一つは持久戦、もう一つは人民戦争およびゲリラ戦だ。中国の対日戦争は1937年に始まり、第一段階では国民党の国民政府が、上海や江浙地域の工場を中西部に移転した。国民政府の統計によると、1937年下半期から1940年6月までの3年間に、中国政府は沿海地域から448の工場と鉱山を移転し、物資は12万トン、技術者は1.2万人を移動させた。その中で、上海と長江デルタの企業が60%以上を占めている。これらの工場の大部分は西部の四川に254、中部の湖南に121、陝西に27の工場が移転し、さらに自発的に移転した工場もあった。後方に移転した工場は合計で600以上に達し、これらの工場の内陸移転はその後の8年間の対日戦争において重要な役割を果たした。
一方で、前線の軍需を支援し、軍事工業を発展させた。また、民間製品の供給を促進し、中西部の経済に積極的な影響を与えた。重要なのは、戦争の経済力を維持し、後方支援地の工業と鉱業の建設のための物質的基盤を築いたことだ。中国共産党の考え方は基本的にここから来ている。したがって、現在中国共産党が産業の大移転を要求していることは、外部から見ると以前の三線地域建設や中国共産党の戦争全体の考え方を連想させ、また中国共産党が大規模で持続的な戦争の準備を進めていることを示唆している。
遠距離からの攻撃を防ぐ
姚誠氏は、中国共産党が大規模な戦争の準備を進めていると述べている。未来の戦争はすべて遠距離攻撃になると予想されている。例えば、アメリカの航空母艦は必ず1千キロ以上離れた場所に停泊しなければならない。遠距離攻撃では、航空母艦の戦闘機の作戦半径は限られている。もし1千キロ以上離れた地点から大陸を攻撃する場合、攻撃は1千キロの沿岸地域にしか届かない。
現在、国家の戦闘レベルや能力は主に戦略的深さに依存している。台湾は戦略的深さを持たないものの、2千キロ以上の射程を持つミサイルを保有している。そのため、もし戦争が勃発すれば、アメリカ、日本、台湾のF-35戦闘機が、中国大陸の沿岸や空港、港に突入し、壊滅的な攻撃を行うことが可能だ。(現在知られている政府機能のある都市や軍事施設はステルス戦闘機や爆撃機ならば、迎撃される前に攻撃が可能ということだ)
しかし、1千キロの内陸に直接触れることは難しいため、海上の核潜水艦は二次核打撃の手段として機能し、攻撃型原子力潜水艦が発射するトマホークミサイルの射程も2千キロだ。陸上にも二次反撃の手段があり、中国共産党が展開できる軍隊はロケット軍で、61基地は安徽省の黄山にあり、海に最も近い位置にある。62基地は昆明、63基地は湖南省の懐化にあり、他の基地は西北、河南、寧夏、甘肅に位置している。
このような状況では、これらの基地を攻撃する時、ミサイルを発射すると空中での滞留時間が長くなり、飛行距離が延びるため、迎撃される可能性や精度が高まる。したがって、重要な攻撃基地を1千キロ以上離れた場所に配置することは、戦争に対する効果的な防御策となる。
大紀元の主筆である石山氏は『菁英論壇』において、90年代にアメリカの著名なシンクタンクであるランダ社の報告書を見たことがあると述べた。その報告書によると、台湾海峡で危機が発生した場合、アメリカは介入し、全面戦争を選ばざるを得ないとされている。これは、アジアの軍事基地に依存し、空中での優位性を活かして、中国国内を爆撃する必要があることを意味している。このため、中国共産党が企業を山の中に移すことは非常に重要だ。最近では攻撃の可能性や戦争の迫り具合は不明だが、中国共産党の全体的な戦略は、この方向に進んでいると考えられるため、引き続き注意が必要だ。







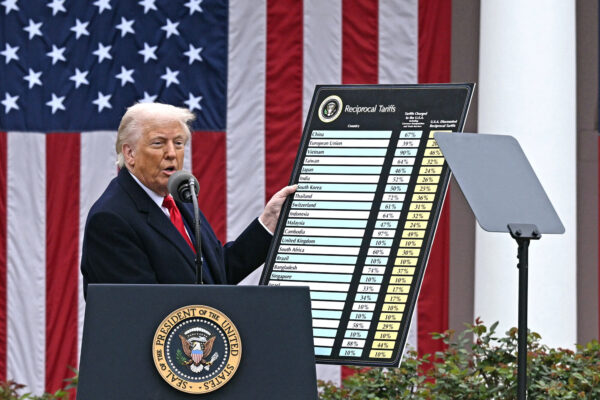


 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram




ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。