自民党の外交部会が政府の「中国人向け観光ビザ緩和方針」に強い批判を表明し、それに対する岩屋外相の「誤解」発言が党内の不満を増幅させる中、政府と与党の連携不足が浮き彫りになっている。背景には日本国民の中国共産党に対する根深い危機感があり、領土問題、人権侵害、日本の土地・不動産大量購入問題、経済的影響力拡大などへの懸念が高まっている。今後の対中政策において、国民感情を考慮した慎重かつ効果的な対応が求められている。
自民党の外交部会などが1月28日に党本部で開いた会合で、中国人向け観光ビザ(査証)の緩和方針をめぐり、政府への批判が再燃した。2024年12月に岩屋毅外相が中国訪問時に表明したこの方針に対し、党内から反発の声が上がっている。
岩屋外相は1月24日の記者会見で、党側の批判的な認識について「多分に誤解がある」と発言したが、これが党内の不満をさらに高める結果となった。星野剛士外交部会長は会合後、記者団に対し「誤解していると会見することは心外だ。政府と党が非常に良くない関係に陥る」と述べ、強い不快感を示した。
批判の背景には、政府から党への事前説明がなかったことへの不満がある。また、オーバーツーリズム(観光公害)への懸念や、日中間の未解決問題が存在する中でのビザ緩和に対する疑問の声も上がっている。
一方、岩屋外相は「今回の措置がただちに中国人観光客の無秩序な急増につながるものではない」と説明し、「政府として引き続き丁寧に説明を行う」と述べている。
この問題は、政府の外交政策決定過程における与党との連携のあり方や、日中関係の今後の展開に影響を与える可能性がある。
日本国民の対中危機感
昨今、日本国民の間では、中国共産党の拡大に対する危機感が高まっている。内閣府の世論調査(令和5年9月)の結果によると「中国に親しみを感じない」との回答は86.7%に達している。この危機感の背景には次のような要因が考えられる。
領土問題と軍事活動
東シナ海や南シナ海は日本にとって極めて重要なシーレーンである。これらの海域の安定と自由な航行の確保は、日本の国益にとって不可欠であり、ここでの中国の軍事活動の活発化が、日本の安全保障に対する懸念を高めている。
南シナ海は、日本の貿易と経済安全保障にとって極めて重要だ。日本のエネルギー輸入の約80%が南シナ海を通過しており、日本の貿易全体の約25%が南シナ海を経由している。南シナ海は、日本と東南アジア諸国連合(ASEAN)、欧州連合(EU)との貿易ルートとして不可欠だ。
東シナ海も日本の安全保障と経済にとって重要な海域だ。日中間の排他的経済水域(EEZ)の境界画定が未解決であり、天然資源の開発をめぐる問題も存在する。また、尖閣諸島周辺の領有権問題も、この海域の戦略的重要性を高めている。
日本政府は、これらの海域の安全と安定を確保するために積極的な外交政策を展開している。日米同盟はもちろん、ASEAN中心の安全保障対話に積極的に参加し、ベトナムやフィリピンとも二国間協力を強化し、海洋安全保障の重要性を強調している。
人権問題
中国共産党(中共)政権による人権侵害の実態が、大紀元の継続的な報道によって明らかになっている。特に深刻なのは、チベット、ウイグル、南モンゴルなどの少数民族地域での組織的な弾圧である。また、1999年以降続く法輪功修練者への大規模な迫害は看過できない。彼らは拷問や違法な拘束の対象となっており、さらに懸念されるのは、良心の囚人、特に法輪功修練者やウイグル人からの強制的な臓器摘出の疑惑である。
言論の自由も厳しく制限されており、政府批判者への弾圧やインターネット検閲が日常的に行われている。これらの人権侵害に対し、国際社会からの反応も見られる。ロンドンに本拠を置く独立した国際民衆法廷、中国民衆法廷が、中国における強制臓器摘出の証拠を審査し、その実態を認定した。
各国の対応も進んでおり、スペイン、イタリア、イスラエルなどが自国民の中国への移植ツーリズムを防止する措置を講じている。国連人権理事会などの場でも、中国の人権状況に対する懸念が繰り返し表明されている。
これらは対岸の火事ではない。日本がこれらの凶悪犯罪を黙認し声を上げず、中国と医療分野での協力を進めれば、強制臓器摘出の仕組みが日本へ輸出されるかもしれない。
日本政府は中共政権への働きかけを強化し、これらの弾圧中止や人権状況の改善を求めること、人権問題に関して他国と協力して中国に圧力をかけること、そして中国の人権状況について日本国内外に向けて積極的に情報を発信することが重要だ。国際社会の継続的な関心と行動が、状況を変える鍵となるであろう。
これらの問題は、日本国民の中国共産党に対する不信感を増大させる要因となっている。
中国人による日本の土地や不動産の大量購入
中国人による日本の土地や不動産の購入には、単なる投資目的以上の深い背景がある。その主な要因として、中国人は中国共産党政権に対し強い不信感を持っており、自身の資産を他国に移動させ逃避したい狙いがある。もうひとつは中国共産党が日本の安全保障を脅かす目的での土地購入の可能性だ。
中国人富裕層による海外不動産購入の背景には、複数の理由がある。中国共産党の一党支配体制下で、自国内に全財産を置くことに政治的リスクを感じる富裕層が少なくない。また、反腐敗キャンペーンや経済減速により、富裕層とその資産の海外逃避が進んでいる。言論統制や過剰な規制から逃れ、より自由な環境を求める動きもある。さらに、子供の教育のため、政治的影響の少ない環境を求める家族も存在する。
一方、中国人による日本の土地購入は、安全保障上の懸念も引き起こしている。2023年度には、安全保障上重要な施設周辺で中国人や中国法人による203件の土地・建物取得が確認された。北海道や離島での大規模な土地取得も報告されており、安全保障上の懸念が高まっている。
日本は外国人による土地取得の規制が緩く、多くの国々と比べて制限が少ないのが現状である。重要施設周辺の土地取得により、不適切な情報収集活動が行われる可能性も指摘されている。
日本政府は「重要土地等調査規制法」を施行するなど、対策を講じ始めているが、さらなる規制強化を求める声も上がっている。一方で、外国人投資家の権利と国家安全保障のバランスをどう取るかが今後の課題となっている。
この問題は、中国人の個人的な資産保全戦略と日本の国家安全保障という、複雑な要素が絡み合っている。今後、日本政府には慎重かつ効果的な政策立案が求められるであろう。
経済的影響力の拡大
中国の経済的影響力の拡大に伴い、日本の経済安全保障に対する懸念も高まっている。特に、重要技術や資源の管理、サプライチェーンの脆弱性などが問題視されている。
政治的対応
このような状況を背景に、日本政府は防衛費の拡大など、中国に対する抑止力強化を進めている。こうした政策は、国民の危機感を反映したものと言えるだろう。
一方で、日中関係の改善を求める声も存在する。経済面での相互依存関係や、地域の安定のために対話を重視する意見もある。しかし全体としては、中国共産党の拡大路線や人権問題に対する日本国民の危機感は確実に高まっており、これが日本の対中政策にも影響を与えていると言えるだろう。
対中政策において、中国人向け観光ビザの緩和方針が議論を呼んでいる。しかし、より重要なのは、中国共産党に対する日本国民の根本的な危機感である。今後は、この危機感に応える形で、政府の対応策や与党内での議論の展開が注目されている。政府には、国民感情を考慮しつつ、慎重かつ効果的な対中政策の立案が求められている。



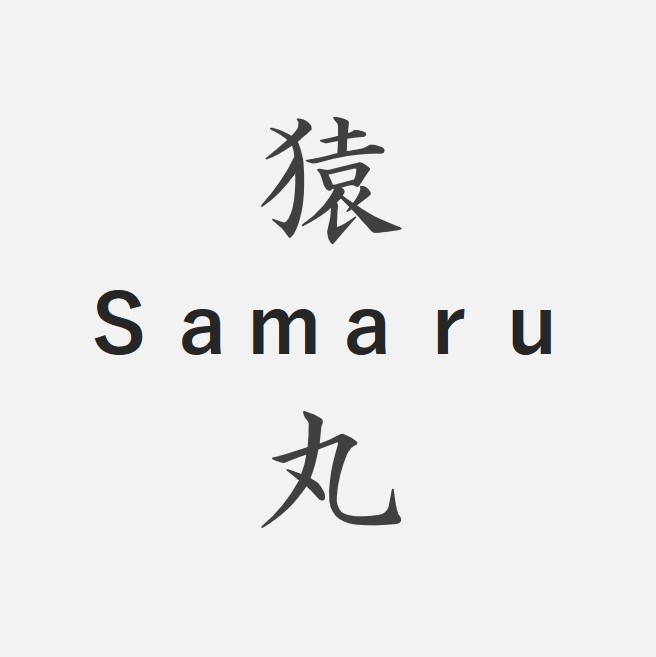






 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram




ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。