近年、企業が発令する転勤辞令が、社員の退職意向を高める要因として注目されている。リクルートワークス研究所の調査によれば、「望まない勤務地への異動」が退職を考える最大の理由となり、「望まない上司のもとへの異動」や「役職の降格」を上回った。この背景には、社会全体の価値観やライフスタイルの変化がある。
転勤NGの増加とその理由
転勤を拒否する社員が増えている理由として、以下のような要因が挙げられる。
第一に、共働き世帯の増加だ。総務省のデータでも示されるように、共働き世帯は専業主婦世帯を上回っており、配偶者もキャリアを持つケースが一般的になった。このため、転居を伴う異動はどちらか一方の仕事を犠牲にするリスクを伴う。
第二に、子育てや介護といった家庭環境への配慮である。特に子どもの転校や親の介護が必要な状況では、遠方への転勤は大きな負担となる。また、単身赴任という選択肢も育児や介護との両立を困難にする。
第三に、新型コロナウイルス感染症拡大以降普及したリモートワークが意識変化を促している。「必ずしも現地に行かなくても仕事はできる」という考え方が広まり、物理的な転居を伴う異動への抵抗感が強まっている。
さらに、住宅ローンを組んで持ち家を購入した人々にとっては、「地域で生活基盤を確立したい」という思いも強い。これら複数の要因が絡み合い、「転勤NG」の声が若手社員を中心に増加していると想定される。
企業側の対応と課題
こうした状況を受け、一部企業では転勤制度の見直しが進んでいる。NTTグループは2022年7月から「リモートスタンダード制度」を導入し、リモートワークを基本とした働き方を推進している。この制度により、社員の勤務場所を自宅とし、転勤や単身赴任を原則廃止する方針を掲げた。出社が必要な場合は「出張扱い」とし、交通費や宿泊費も支給される仕組みとなっている。
この新制度は、社員の住む場所の自由度を高めることを目的としており、当初はグループ内の約3万人を対象に適用された。その後、対象者は拡大され、2023年2月時点で約4万人に達している。また、この取り組みにより単身赴任者が減少するなど、従業員の負担軽減にもつながっているという。また、ニトリホールディングスでは2023年3月に地域限定社員制度「マイエリア制度」を採用し、従業員が転居せずに通勤可能な地域限定の勤務を選択できる仕組みを提供している。
一方で、多くの企業では依然として従来型の転勤制度が維持されており、人材流出リスクが課題となっている。2024年4月のエン・ジャパンによる調査では、「転勤辞令が出た場合に退職を検討する」と答えた人は約7割に達し、とりわけ20代では78%と高い割合だった。このような状況下で、企業は柔軟な人事制度設計や経済的・精神的サポートの充実が求められている。
リモートワークやテクノロジー活用による働き方改革は進んでいるものの、日本企業全体で見ると転勤制度への依存度は依然として高い。株式会社マイナビが2025年2月27日に「転勤と転職に関する調査レポート」を発表した。この調査は全国の企業を対象に実施され、転勤制度についての今後の方針を尋ねた結果、「拡大する予定」と回答した企業が35.2%、「維持する予定」と回答した企業が59.2%となり、両者を合わせると9割以上に達している。一方で、「縮小する予定」と回答した企業は5.6%にとどまった。この調査結果は、企業が転勤制度を依然として重要な人事施策と捉えていることを示している。

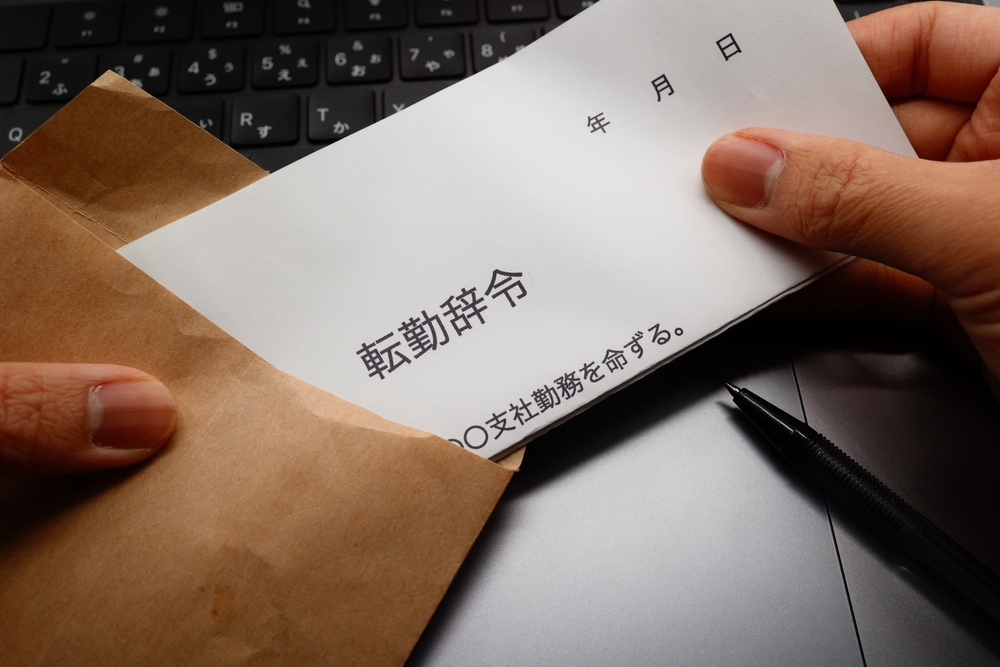








 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram




ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。