4月2日、アメリカのトランプ大統領が大規模な相互関税を発表し、世界市場に激震が走った。新たな貿易緊張が急速に高まり、国際貿易の既存秩序が揺らぎ始めた。トランプ氏の関税リストには抜け目がなく、中共のような敵対国だけでなく、最も親しい同盟国や南極近くの無人島にまで対象が及んでいて、この措置は、全世界に影響を及ぼす規模であった。なぜ彼は、このような動きに出たのだろうか?
4月3日以降、株式市場は急速に下落した。トランプ氏は、なぜ株価の暴落を気にかけなくなったのか? 本当に計画を持っていたのか? 新任財務長官スコット・ベッセント氏の言葉によれば、関税政策は、すでにある戦略を始動させており、これは単なる混乱ではなく、より大きな構想の序章にすぎない。この構想は、世界の貿易体制そのものを、再編しようとする試みであると言う。
このような大規模な転換は、過去に二度しか例がない。一つは1944年のブレトンウッズ体制の発足、もう一つは1980年代初頭、レーガン大統領とサッチャー首相が推進した新自由主義秩序の始まりであった。現在、時代は2025年を迎え、アメリカを中心とした新たな国際秩序が、混乱の中から現れつつある。この秩序において、各国は、三つのグループに分類されることになった。
ベッセント財務長官は次のように説明した。アメリカは世界の国々を「緑」「黄」「赤」の三つのバスケットに分類し、それぞれの国は、アメリカとの貿易協定に基づき、位置づけが異なり、ある国々は低関税、軍事的保護、優先的なドルアクセスといった特権を享受できるが、他の国々は、独自の力で生き延びる必要があるということだ。
米国の新経済チームとその狙い
では、トランプ氏の目指すグローバル新秩序とは何か? この構想は現実味を帯びているのか? それとも一部メディアが揶揄するように、「狂人とその取り巻き」が描いた幻想に過ぎないのか?
この問いに答えるには、トランプ氏の新たな経済チームの構成と思想を理解することが不可欠である。まず、財務長官スコット・ベッセント氏、彼はかつてソロスと共にイングランド銀行に挑んだヘッジファンドマネージャーであり、経済史をイェール大学で教えた経験も持つ。
次に、ホワイトハウス経済諮問委員会の委員長スティーブン・ミラン氏、彼はハーバード大学で経済学博士号を取得し、マンハッタン研究所の研究員であると同時に、ヘッジファンドの戦略家としても知られていた。彼が最近発表した論文「グローバル貿易体制再編ユーザーガイド」は、ウォール街で注目を集めていた。
この二人は、アメリカの脱工業化を重大な脅威と見なし、多くの発言や記事を通じて警鐘を鳴らしてきた。そのため、トランプ氏の選挙綱領に共鳴し、経済チームに参加したのである。彼らの掲げる目標は、「アメリカを製造業大国として復活させる」ことにあった。
なぜトランプチームは、製造業に執着し注目するのか。1940年代、アメリカは、世界屈指の製造業国家であったし、雇用全体の40%が製造業に従事していた。現在では、この割合が10%以下に低下している。脱工業化は、アメリカの工業中心地帯を崩壊させ、2024年にはこれらの地域が、トランプ氏に圧倒的な支持を示した。
さらに、中国をはじめとする他国に対して、アメリカの工業力は大きく遅れを取っており、もし軍事衝突が起これば極めて不利な立場に置かれると言う。歴史的にも、民間の工場と技術は迅速な軍事対応に不可欠である。副大統領J・D・ヴァンス氏は、「中共の一つの国有企業が昨年建造した商船の数は、アメリカが第二次世界大戦以降に建造した総数を上回っている」と指摘した。
このような現状を踏まえれば、トランプ政権が、製造業の復活を目指す理由は明確であり、しかし、すべての国に関税を課し、最も親しい同盟国に対してまで「彼らは我々の仕事と富を奪い続けてきた。敵味方を問わず、我々の国から多くのものを持ち去ってきた。率直に言えば、友人のほうが敵よりも恐ろしい存在だ」と言い放つ必要があるのかという疑問は残った。
アメリカは、長年にわたり世界で最も強力な国家として君臨してきた。現在の貿易体制もアメリカ自身が設計したものである。にもかかわらず、トランプ氏はなぜこれに不満を抱くのか? この問いに答えるためには、歴史的背景をたどる必要があるのだ。
アメリカの脱工業化は、一朝一夕で進行したものではない。二つの経済体制がこの流れを導いた。第一は1944年から1973年のブレトンウッズ体制、第二は1980年代初頭のレーガン政権から2016年のトランプ政権誕生まで続いた新自由主義体制であった。
ブレトンウッズ体制
ブレトンウッズ体制は、20世紀40年代に確立された制度であり、1944年、アメリカのブレトンウッズにおいて、国連通貨金融会議が開催され、関連するルールが制定された。同時に、安全保障の面では、複数の協定が結ばれ、最終的には、NATOや日米安保条約の成立へと発展した。要するに、アメリカ以外の国が、この体制に参加することは、以下の三点を意味する。
第一に、自国通貨をドルに連動させ、さらにドルを金と連動させるという構造の一部となること。
第二に、アメリカの軍事的保護に依拠し、必要に応じてアメリカの軍事基地を自国に受け入れる立場をとること。
第三に、アメリカが同盟国の産業競争力向上を支援しつつ、自国市場を開放する一方で、同盟国には一定の範囲で、自国市場をアメリカ企業から保護する余地が認められること。
この体制には、ベッセント氏が提唱した三つのバスケット、すなわち緑・黄・赤の区分が存在する。同盟国は緑のバスケットに属し、すべての恩恵を享受する。中立国は黄色のバスケットに分類され、恩恵は得られないが、個別の協定締結による協力関係の構築が可能である。共産主義国は、赤のバスケットに属し、ブレトンウッズ経済秩序の枠外に位置づけられた。
この体制は、ドルを世界の準備通貨としての地位に据えた。しかし、世界経済の成長とともにドルの需要が増加し、アメリカはジレンマに直面した。準備通貨の発行国として、アメリカは世界の貿易および貯蓄需要を満たすために、ドルと米国債を継続的に供給する必要があった。一方で、ドルは金と連動しており、金の供給量には限りがある。このため、アメリカは次のいずれかを選ばなければならなかった。すなわち、ドルの増発によって金本位制の信頼性を損なうか、もしくは金本位制を堅持し、ドルの供給を制限して世界経済の成長を抑えるかであった。
このジレンマの結果として、1971年にニクソン大統領は、ドルと金の兌換停止を表明し、ブレトンウッズ体制の終焉をもたらした。
その後、世界経済は、不安定な時期を迎え、1980年代初頭には、レーガン大統領とサッチャー首相が主導する新自由主義的世界秩序が登場した。
新自由主義秩序
新自由主義的世界秩序の特徴は、以下の通りである。
第一に、関税の引き下げ。
第二に、国際的な投資障壁の緩和。
第三に、柔軟な為替レートの導入。
第四に、アメリカが、友好国の安全保障を担う構造。
自由市場の原則に基づくこの新たな秩序は、ブレトンウッズ体制ほど厳格ではなかった。各国にドルの使用を義務づける正式な協定は存在しなかったが、各国は、その利便性と信頼性に基づいてドルを選択した。
この体制の下では、アメリカ以外の国々にとって、ドルを蓄積する強い動機が生じた。ドルの保有によりアメリカへの輸出が容易になり、逆にアメリカからの輸入には不利となるためである。特筆すべき点として、世界貿易機関は、自由貿易の利点を強調しつつも、実際には発展途上国が、アメリカに対して、高い関税を課すことを容認していたのだ。
また、固定為替レートの消失により、アメリカ資産への準備需要が高まり、ドルの価値を押し上げた。強いドルは、アメリカ国民を全体的に裕福にした一方で、アメリカの製造業の価格競争力を低下させ、安定した製造業の雇用が、国外へと移転する結果を招いた。特に、中国が2001年に世界貿易機関(WTO)に加盟した後、この動きは「チャイナ・ショック」として顕在化した。
2016年にトランプ氏が初めて大統領に選出されたことは、新自由主義秩序の終焉を象徴する出来事となった。というのも、トランプ氏は若年期から「自由貿易」が、アメリカに及ぼす負の影響を直視し、関税政策に強い関心を寄せていたためであった。
トランプ氏は一体何を望んでいるのか?
トランプ陣営の情報を分析した結果、トランプ氏のグローバル新秩序における全体計画は、アメリカの再工業化を推進しつつ、ドルを世界的な準備通貨として維持することにあると結論づけた。
では、彼らはどのように行動しているのか。
第一のステップは、関税の混乱を引き起こすことである。現在の状況は、まさにその段階にある。
この局面で、トランプ政権は、自らの立場を明確にした。株式市場の下落や一時的な経済の混乱をものともせず、トランプ氏は「椅子に三本目の脚を加え、それを交渉に使った」と語っている。すなわち、現在の関税の混乱は、計画の残りを実行するための交渉材料を形成する目的に基づいており、これが次の段階へとつながる。
第二のステップは、互恵的な関税協定の締結である
報道によれば、すでに70か国以上がアメリカ側と接触し、関税に関する協議を希望している。これこそがトランプ陣営の狙いである。この段階における長期的な目標は、ベッセント氏の言葉を借りれば、「関税が解決しようとする課題とは、公平な競争環境の構築、創造性と安全、法の支配と安定に報いる国際貿易体制の形成、賃金抑制、通貨操作、知的財産の盗用、非関税障壁や過度な規制の排除にある」となる。
トランプ氏の一期目における貿易戦争は、期待された成果には至らなかった。中共との激しい関税戦争にもかかわらず、中国の製造業の台頭を食い止めることはできなかった。その理由は、中国がベトナムやメキシコといった第三国を経由することで、高関税を回避する仕組みを活用したためである。ゆえに、今回のトランプ氏は、関税の適用範囲をあらゆる国、さらには無人島にまで広げ、「この愚かな抜け穴を封じる」と宣言したのだ。
ミラン氏は『グローバル貿易体制再編ユーザーガイド』の中で、次のように述べている。「トランプ大統領は、関税を交渉成立のための材料と見なしている。すなわち、懲罰的関税の導入後、ヨーロッパや中国といった貿易相手国が関税引き下げや通貨協定との引き換えで、より柔軟な対応を示すようになるという構図である」
この見解こそが、グローバル新秩序における最終段階の要点なのだ。
最終ステップは、「マール・ア・ラーゴ協定」の締結である
ミラン氏は『グローバル貿易体制再編ユーザーガイド』の中で「マール・ア・ラーゴ協定」に触れている。現在、この概念についての言及は少ないが、私の見立てでは、彼らの最終的な目標は、ドルの価値をある程度抑制しつつも、ドルの準備通貨としての地位を維持することである。ベッセント氏が言及したグリーン、イエロー、レッドの通貨バスケットを踏まえるならば、新秩序の中で、グリーンバスケットに分類される国々が自国通貨をドルに連動させ、ドルが過度に強くなる場合には自国通貨の上昇を約束する仕組みが構想されている。その見返りとして、彼らは世界最大の消費市場へのアクセス、安全保障上の恩恵、そしてドルシステムへの良好なアクセスを獲得することになると言う。
ベッセント氏は、最近の講演でこう語った。「国際貿易体制とは、軍事、経済、政治の複合的な関係網であり、いずれか一つを孤立して論じることはできない。これこそがトランプ大統領の世界観であり、ゼロサムゲームではなく、アメリカ国民の利益を最大化するために、再編可能な構造である」
以上の理由により、トランプ大統領による現在の経済的混乱には、一貫した論理が存在しており、計画性に基づいたものであると判断し、表面的には混乱して見えるが、その背後には明確な秩序があったのだ。トランプ陣営は、現行の国際秩序が、もはやアメリカ国民の最大利益と一致していないとの見解に立ち、現在の関税政策を交渉材料として活用した。彼らの狙いは、相互関税を活用して、レッドおよびイエローバスケット諸国の競争環境を是正することにあった。さらに、通貨取引が成立すれば、関税の大幅な引き下げも視野に入っているだろう。





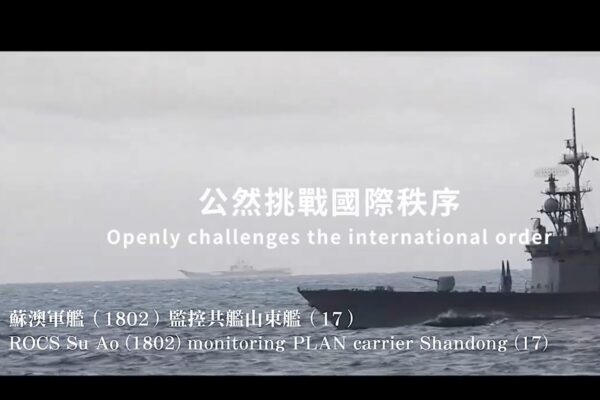




 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram




ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。