ドナルド・トランプ大統領が今週、中国に対して145%の関税、世界のその他の国々に対して10%の関税を課す方針を発表し、90日間の交渉期間を設けると発表したため、世界と金融市場は安堵のため息をついたようだ。
一般的な通念では、いかなる関税もマイナスであると考えられているが、現実はもっと微妙であり、必ずしも通念通りとは限らない。
教科書的な貿易経済学は、スコットランドの経済学者アダム・スミスが、スコットランドとポルトガルが羊毛とワインの相互利益貿易を行うという単純な理論モデルを用いたことから始まる。関税なしで貿易する方が、両国にとって利益になるというものだ。多くの経済学者は、国際貿易の利益を概念化する際に、この知的枠組みを活用してきた。
しかし、現代の貿易は、17世紀のスコットランドを例にした教科書の内容とは大きく異なり、例えば、スミスが執筆していた当時、スコットランドの寒く湿った気候では、ワインの生産が不可能だった。つまり、当初のモデルでは、両国は生産物に関して一種の独占権を享受していた。これは今日の石油生産国と似ていた。その石油は、他の国では石油埋蔵量がないため、生産できないからだ。
現実には、現代の貿易はまったく異なる要因に強く依存していた。例えば、「ネットワーク効果」が国際貿易に大きな影響を与えていた。ネットワーク効果とは、関連する産業やビジネスが近接して存在することで、より広範な競争優位性を生み出す現象のことだ。わかりやすい例として、ニューヨークやロンドンの金融業界、シリコンバレーのテクノロジー業界などが挙げられる。
貿易可能な製品にも同じようなことが言える。中国は、自国の製造業全体を支える産業ネットワークを何年もかけて構築してきたが、それが永続するとは限らない。
別の例として、スミスが用いた当初の貿易モデルは、グローバル資本の流動性を考慮していなかった。労働力は国境を越えて移動できないかもしれないが、資本は非常に流動的だ。極端な例を挙げれば、米国、アフリカ、中国、欧州で、ロボットを導入する場合のコストの差はどれくらいだろうか? 導入コストに違いはなく、生産量も同じである。つまり、どこに設置しても生産性は同じで、価格差は本質的に存在しない。
しかし、反直観性は、単に国際貿易の経済学だけでなく、協力する国とそうでない国に基づく関税の賦課にも当てはまる。大雑把に言えば、積極的に関税を引き下げるために協力する国々は、相互の関税を低くすることで利益を得るが、紛争が起きれば、関税を引き上げることで利益を得ることもある。
現在の議論にとって最も重要なことは、米国のような大国は、相手国が不正を行っている貿易摩擦に直面した場合、関税率を引き上げることで、利益を得ることができるということである。
この「最適関税率」のテーマに関する代表的な論文は、トランプ政権の関係者によるものではなく、現在の世界貿易機関(WTO)のチーフエコノミストであるラルフ・オッサ氏によるものだ。2014年、オッサ氏は、米国にとっての最適な関税率は2.5%ではなく、おおよそ60%であると試算した。ただし、これは産業や関税の対象によって大きく異なり、この知見は、現在進行中の貿易戦争に直接関係した。というのも、主な発見のひとつは、特定の第三国に対して、貿易障壁を維持しつつ、少数の国々が貿易を自由化することで、貿易の利益がより直接的に共有され、大きな利益を得られるという点だ。
換言すれば、トランプ大統領がベトナム、インド、メキシコ、カナダ、ヨーロッパ、日本といった主要国と取引を成立させつつ、中国に対する障壁を維持し続ければ、自由化した側の国々がより多くの利益を得て、中国の利益は減少することになる。
国際貿易の経済学は複雑で、しばしば直感に反する。ただし、「あらゆる関税は悪である」という通説は、研究によって裏付けられているわけではない。貿易における多くの制限は、関税という形では現れない。全米経済研究所(NBER)の発表した研究では、トランプ政権一期目における米国の対中輸出の減少の約90%が、市場要因ではなく、非公式な非関税障壁によるものであることが示された。
民主主義における活発な議論には、私たちの指導者や、私たちが決断を下す際に頼りにしている情報を疑うことも、含まれるべきである。経済研究の現実は、中国やその他の国々との貿易協定交渉に、どのように臨むべきかについて、微妙な差異を明らかにする全体像を描いていた。
どんな関税も悪であるという従来の常識は、単に現実を表していないだけだ。









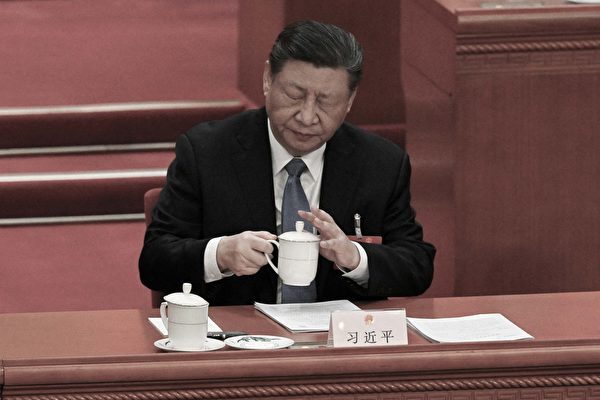
 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram




ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。