石破茂首相は22日夜、物価高騰への対応策として、5月22日からガソリン価格を1リットル当たり定額で10円引き下げる方針を明らかにした。首相官邸で記者団の取材に応じたもので、与党からの提言を受けて決定したと説明した。
石破首相は「与党の提言を重く受け止め、アメリカとの協議を前進させるとともに、国内対策についても企業や国民生活への影響をよく注視しつつ、必要な支援に万全を期していく。ガソリン価格について、当面、定額の引き下げ措置を実施する」と述べた。
今回の措置はガソリンだけでなく、軽油も1リットル当たり10円、重油と灯油は5円、航空機燃料は4円の値下げが実施される予定である。背景には、生活必需品の価格上昇が続く中、国民や企業の負担を軽減する狙いがある。
この方針は、同日午後に自民党と公明党の政策責任者が官邸を訪れ、ガソリン価格の定額引き下げを速やかに導入するよう申し入れたことを受けて決まった。会談後、与党側は「現行の仕組みを見直し、定額引き下げをすぐに実施することで、税制改正よりも早く対応できる」と強調した。
また、電気・ガス料金についても、需要が増える7月から9月まで補助を再開する方針が示されている。
今回のガソリン価格引き下げ措置について、与党内からは「この対策だけでは足りない」との声も上がっており、今後もさらなる物価高対策の議論が続く見通しだ。
問題点は?
今回のガソリン価格引き下げ措置については、いくつかの問題点が指摘できる。
まず、定額引き下げや補助金による価格抑制は、国の財政負担が大きくなり、長期的に続けることが難しいという課題がある。これまでの補助金制度でも、国の予算が膨らみ続け、財源が赤字国債に頼る状況となっている。今後も補助が続けば、国民全体の税負担や将来世代への負担が増える可能性が高い。
また、ガソリン価格を一律で引き下げる政策は、車を利用しない人や都市部の住民には恩恵が及びにくい一方、車を頻繁に使う富裕層や大企業にも同じように利益が渡るため、政策効果が公平とは言い難い。本来支援が必要な低所得者や物流業者などに限定した対策の方が、より効率的であるとの指摘もある。
「定額で10円引き下げる」とは?
「定額で10円引き下げる」とは、国が石油元売り会社に補助金を出し、その分だけ卸売価格を引き下げることで、消費者がガソリンスタンドで支払う価格が1リットルあたり10円安くなる仕組みである。
つまり、「補助金」という形で石油元売り会社に資金が流れる仕組みとなっており、政策の透明性や実効性に疑問が残る。補助金の配分が適切かどうか、また政官業の癒着の温床になっていないかという批判も根強い。
また、ガソリン税の「トリガー条項」(一定価格を超えた場合に自動的に税負担を軽減する仕組み)は依然として凍結されたままであり、根本的な税制改革が先送りされている。減税による価格引き下げの方が即効性や透明性が高いという意見も多いが、政府は補助金方式を優先している。
最後に、今回の措置は選挙対策との見方もあり、持続的な経済政策としての説得力に欠けるとの批判もある。
このように、ガソリン価格引き下げ政策には、財政負担の増大、公平性や持続性の問題、政策の透明性、税制改革の遅れなど、複数の課題が存在している。



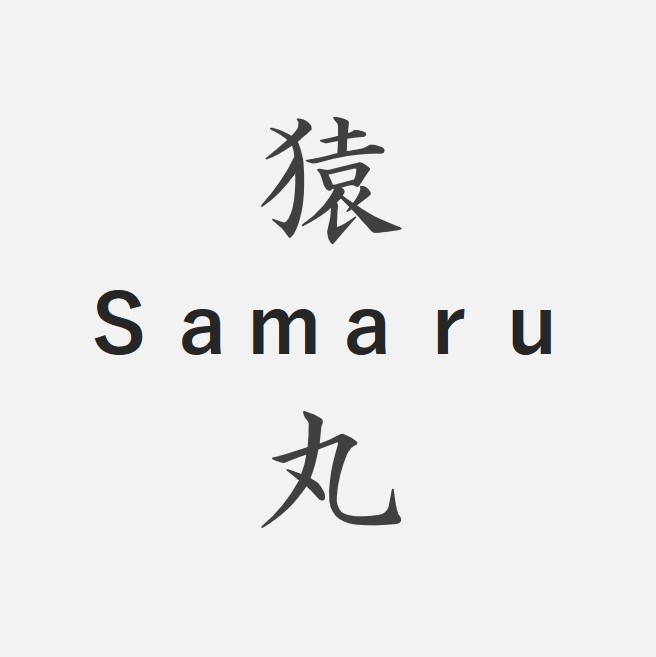






 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram
ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。