いま、アメリカで使用を見直している合成着色料の一部は、日本では依然として食品や医薬品に使用されている。
赤色3号――その名を聞いても一般消費者には馴染みは薄いかもしれないが、菓子や水産練り製品、医薬品のコーティングなどに使われてきた歴史を持つ着色料である。
2025年に入ってから、アメリカはこの着色料を含む複数の合成色素について、使用禁止を含む大きな方針転換に踏み出した。
この動きは、単なる規制の話ではなく、食品の安全性と企業の対応、消費者の選択のあり方を問い直すものとなっている。
アメリカでは赤色3号の全面禁止を決定
2025年1月、米食品医薬品局(FDA)は赤色3号(エリスロシン)の食品および経口医薬品への使用を段階的に禁止することを正式に発表した。食品については2027年1月、医薬品については2028年1月までの全面禁止を目指す。これは「デラニー条項」と呼ばれるアメリカ独自の法的基準に基づく判断であり、動物実験での甲状腺腫瘍の発生を根拠とした。
さらに4月、FDAは赤色40号、黄色5号、青色1号など他の石油由来の合成着色料6種類についても2026年末までに段階的な排除を目指す包括的な方針を発表。シトラスレッド2号とオレンジBに関しては、認可取り消しの手続きを年内に開始する方針だ。
アメリカの規制は、科学的評価と法的整合性の両面からの対応であり、「リスクがゼロではないものを市場に残すことの妥当性」が問われている。
EUは警告表示と使用制限で対応
一方、EUでは赤色3号は1994年から使用が厳しく制限されており、現在はカクテル用チェリーなど限られた用途のみに認可されている。さらに赤色40号や黄色5号などの着色料については、子供の行動に悪影響を与える可能性があるとの警告表示を2010年から義務化している。
EUは「リスクゼロ」よりも、許容摂取量(ADI)に基づいた現実的な管理を行っているが、消費者への情報提供を重視する姿勢が際立っている。
日本では使用継続 規制強化の動きは見られず
こうした国際的な動向に対して、日本では厚生労働省が赤色3号を含む合成着色料11種の使用を継続許可しており、国際的な評価機関JECFAによる安全性評価を根拠としている。
医薬品については、一部製品でヨーロッパ基準の摂取上限を超えていた例が確認されたものの、厚労省は使用禁止ではなく自主的な点検対応にとどめている。
毎日新聞ニュースサイト英語版「TheMainichi」によると、FDAの禁止措置を考慮して、CAA(消費者安全法)は染料の安全性の見直しが必要かどうか検討すると報じている。
業界では天然色素への移行も
一方で、実際の市場では静かな変化が進みつつある。菓子や漬物、かまぼこ業界を中心に、天然由来の色素への切り替えが進行中であり、とくにアメリカやEUに輸出する企業では、規制対応のために製品レシピを変更する必要が出てきている。
国内市場では表示義務があるとはいえ、合成着色料がどの程度使われているかを意識して選ぶ消費者はまだ限られているのが現実である。
国際規制の変化に 私たちはどう向き合うべきか
現時点では、日本は科学的評価を尊重しつつ規制の変更には至っていない。しかしながら、アメリカやEUのように、より厳しい基準や情報開示を進める国は増加している。
どのようなリスクを受け入れ、どのようなリスクを避けるべきか――その判断には、科学だけでなく、社会の選択が関わってくる。
私たち消費者自身も、商品の裏側にある情報に目を向けることが求められているのかもしれない。赤色3号という一つの着色料をきっかけに、日々口にする食品の「見た目」の背後にある問題を考えてみることは、今後ますます重要になっていくだろう。







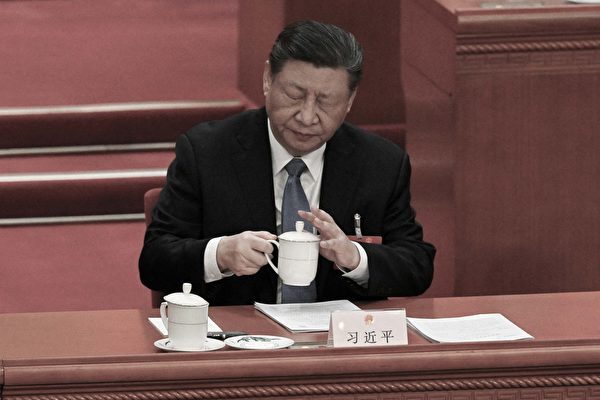


 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram




ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。