就任からわずか72日後の4月2日、トランプ米大統領は、包括的な貿易政策の変更を発表し、全ての国に対して、相互関税を導入するとともに、この日を「アメリカの解放の日」と宣言した。
アメリカは、これまで数十年にわたり、低い貿易障壁を維持しつつ、自国には、ほとんど関税がかからない自由貿易協定を推進してきた。しかしトランプ氏は、こうした一方的な貿易体制が他国に利用されてきたと批判し、これを是正する新制度の導入に踏み切った。
トランプ氏は演説で、大型の図表を使い、各国が米製品に課している関税の実態を示し、それぞれの国の障壁に見合った「相互関税」の新たな基準を説明した。新制度では、すべての国からの輸入品に一律10%の基本関税が課されるほか、各国の対米関税率に応じて追加関税が上乗せされる。
この新たな関税政策は、米国内製造業の再興と雇用創出を目的とするものだが、インフレの加速や経済への短期的・長期的な影響については、現時点では不透明だ。
1.一律10%の関税
トランプ氏は、すべての国からの輸入品に対し、最低10%の関税を課すと発表し、この一律関税は、4月5日午前0時1分から施行されることになる。
また、
「外国はついに、世界最大の市場である我々の市場にアクセスする特権に対して、対価を払うことになる」
と、述べた。
2.高い関税障壁の国々に追加の「相互関税」
トランプ米大統領は、すべての国からの輸入品に対し、最低10%の関税を課すと発表した。この一律関税は、4月5日午前0時1分から施行されると言う。
今回の貿易措置は、1977年の「国際緊急経済権限法(IEEPA)」に基づき、大統領が国家緊急事態を宣言したうえで実施され、この法律は、大統領に輸入品の規制などを行う権限を与えるものだ。
米国は昨年、約4.1兆ドル相当の商品とサービスを輸入しており、ホワイトハウスは、新関税によって、今後10年間で数兆ドル規模の歳入が見込めると試算した。
3.中国に高率の追加関税
昨年、アメリカは、中国との貿易赤字が約3000億ドル(約45億円)に達し、過去最高を記録した。中国共産党による技術の強制移転、知的財産の盗難、国家補助金などの不公平な貿易慣行は、長年、アメリカの企業と労働者を脅かすとして両党から批判されてきた。また中国は、人為的に価格を抑えた輸出品で、世界市場を席巻しているとの指摘もあった。
トランプ大統領は就任後、フェンタニル密輸問題を国家緊急事態と位置づけ、中国製品全てに20%の関税を課した。中国は今もフェンタニルの原料の主要供給源であり、これがメキシコやカナダに送られ、違法薬物に加工されてアメリカに密輸されている現実があった。
中国に対する関税は、34%の報復関税を加えた合計54%となる。これはトランプ氏が選挙中に示していた最大60%の対中関税に迫る水準だ。
トランプ氏は、
「アメリカ国民は大きな代償を払っている。中国は長年、アメリカを大いに利用してきた」
と、語った。
ホワイトハウス関係者は記者会見で、中国がカンボジア、インドネシア、タイ、ベトナムなどの第三国を経由して関税を回避していると指摘した。
「ベトナムの関税が問題ではない。問題は、中国がそこを利用して商品を送り込んでくることだ」
と、関係者は説明した。
米サウスカロライナ大学エイキン校の謝田教授は、
「他国は、アメリカの圧力に妥協する可能性があるが、中国がトランプ氏の新たな関税政策に屈することは、考えにくい。中国は、グローバル経済の中心的な存在で、他の国とは異なる」
との見方を示した。
「トランプ氏はまず他の国々との問題を片付け、その後に中国との問題に集中する構えだ」
と、語った。
4.カナダとメキシコは新関税の対象外
トランプ政権が発表した新たな相互関税措置について、カナダとメキシコは対象から除外された。両国にはすでに違法移民や合成麻薬フェンタニルの流入を理由に25%の関税が課されており、今回の措置とは別に、この関税が継続される。
これまでアメリカ・メキシコ・カナダ協定(USMCA)に適合する自動車など一部品目は、関税が免除されていたが、この免除は4月2日に期限切れとなり、延長についての発表はない。ただ、USMCAに関連した一部製品やカナダからのエネルギー製品に適用されている関税軽減措置(10%)については、引き続き維持されると言う。
米政府は、カナダやメキシコが違法移民やフェンタニル問題に十分対応した場合、現行の特別関税措置を終了させ、新しい相互関税制度に切り替える方針だ。
一方、カナダのマーク・カーニー首相は、アメリカによる自動車関税に対抗措置を取ると表明し、
「米国が導入する相互関税は、世界の貿易体制を根本から変えるものだ」
と、懸念を示した。
5.トランプ氏、新関税導入の正当性を主張
トランプ大統領と政権幹部は、新たな関税措置について、長年続いてきた世界貿易の構造的な不均衡を是正し、「アメリカを再び豊かにする」ために必要だと説明した。
トランプ氏は2日、
「わが国は50年以上にわたって、近隣諸国からも遠く離れた国々からも、友好国・敵対国を問わず搾取されてきた」
と述べ、
「外国のずる賢い連中が、アメリカの工場を荒らし、我々の『アメリカン・ドリーム』を切り裂いてきた」
と、強い言葉で現状を批判した。
トランプ氏はまた、北米自由貿易協定(NAFTA)の締結以降、アメリカの製造業が衰退し、500万人の雇用が失われたと指摘。
「この取引こそが、史上最悪の貿易協定だった」
と述べ、過去の政策が19兆ドルにのぼる貿易赤字をもたらしたと強調した。
昨年のアメリカの貿易赤字は1.2兆ドルに達し、過去最大となった。トランプ氏は、このような慢性的な貿易赤字について、
「もはや単なる経済問題ではなく、安全保障と国民生活を脅かす国家的な緊急事態だ」
と、語った。
関税の適用を回避するために、各国と交渉する余地があるかどうかについて、政権幹部は「これは交渉ではない」と明言し、
「国家的な緊急事態であり、単に『関税を少し下げる』といった表面的な対応では、本質的な問題である非関税障壁や制度的な不公平は、解決しない」
と、述べた。
各国が報復措置を取った場合でも、大統領は柔軟に対応し、アメリカの利益が損なわれないよう措置を講じる構えだと言う。
カリフォルニア州に本拠を置く経済シンクタンク「ミルケン研究所」のチーフエコノミスト、ウィリアム・リー氏は、トランプ氏が相手国の関税率の半分にとどめている点について「交渉を容易にするための「親切な」アプローチだ」と分析している。ただし、他国が対抗措置を取れば、トランプ氏は、さらに高い関税で応じる可能性があると述べた。
6.トランプ経済政策における関税の位置づけ
新たな関税措置について、支持者らはこれを単独の対策ではなく、トランプ政権の経済政策全体の一環として位置づけている。
米経済シンクタンク「ミルケン研究所」のチーフエコノミスト、ウィリアム・リー氏は、関税を「国内の所得向上とサプライチェーンの強化に向けた戦略的な手段」と評価した。特に相互関税の効果は、トランプ氏が進める他の政策――規制緩和や法人税率の引き下げ――と組み合わさることで、米国内への製造業の回帰や技術革新を促進すると指摘した。
リー氏は、こうした政策が総合的に働くことで、トランプ氏の掲げる「強いアメリカ経済」の実現に近づくと述べたのだ。
トランプ氏は、10億ドル(約1500億円)以上の大型投資の推進を専門に担う新たな部門を商務省内に設置する方針も示した。
謝田氏も、トランプ氏が打ち出した追加投資や減税措置、税控除などは「米国民の所得向上と税負担の軽減を目的としたもの」だと指摘し、これらの施策により、
「関税によって物価が上昇しても、それを打ち消すだけの購買力の向上が見込める」
との見方を示した。
7.注目すべき経済指標
アメリカの株式市場は2022年以来最大の四半期下落を記録した。背景には、トランプ前大統領による新たな関税政策への懸念があった。S&P500は第1四半期に4.6%下落し、NASDAQは約10%の下げ幅となった。ゴールドマン・サックスは、アメリカ経済が今後12か月以内に景気後退に陥る確率を従来の20%から35%に引き上げており、その一因として関税政策を挙げた。
一方で、ミルケン研究所のチーフエコノミスト、ウィリアム・リー氏は、今回の株安や経済不安を「一部メディアや専門家が不当に関税のせいにしている」と指摘し、関税によって市場に一定の不透明感が生じていることは認めつつも、その影響は誇張されていると言う。
リー氏によれば、アメリカの輸出はGDPの約11%、輸入は約14%に相当する。関税や報復関税の影響が懸念されているが、アメリカ経済全体に及ぼす影響としては、
「恐慌や深刻な景気後退を招くほどの規模ではない」
と述べ、
「過剰な懸念だ」
と、強調した。
一方、経済学者イアン・フレッチャー氏は、関税の規模そのものよりも、それが市場に与える心理的な衝撃の方がリスクになると指摘する。
「トランプ氏は1期目の関税で大きな混乱がなかったことで自信を持っているが、今回はそれを大きく超えている」
と、語った。
フレッチャー氏は、関税を5年程度かけて段階的に導入すれば、市場も冷静に対応できると主張。また、トランプ氏が年初に一部関税を見直したように、今後発表された関税も規模縮小の可能性はあると見た。ただし、企業が投資計画を立てる際、新たな不確実性の要因となることは、否めないと述べた。
関税の実施が進む中で、実体経済への影響は、今後の経済指標に表れてくると予想されている。
謝田氏は、関税の影響を見極める上で「雇用統計」や「実質所得の伸び」に注目すべきと指摘した。
一方リー氏は、米国内における「国産品の消費割合」や「国内投資の動向」に注視していると言う。
「消費者の財布の動きが真の先行指標だ」
と述べ、関税導入後に物価上昇が定着した場合は、
「インフレリスクが現実化する可能性がある」
と、警戒感を示した。












 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram

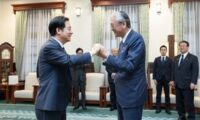


ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。