トランプ米大統領は4月2日、相互関税の発表の際に、「日本では、我々の友人(日本)がアメリカ産の米(コメ)に700%の関税を課しており、コメやその他の製品を売らせたくないのだ」と発言した。これに対し、江藤拓農林水産大臣は「論理的に計算しても、そのような数字は出てこない」と反論した。
しかし、この「700%」という数字は完全に無根拠とも言い切れない。
実際の関税とその根拠
日本では、WTOのミニマム・アクセス(MA制度、低い関税での輸入枠)により、年間約77万トンのコメを関税ゼロまたは低関税で輸入している。これは国内消費量の約8%に相当する。
一方、この枠を超える輸入米には精米で1キログラムあたり341円の関税がかかる。この関税率は2000年に設定し、2025年現在も維持している。
たとえば、2004年当時の輸入米価格(1キログラムあたり43.8円)を基に関税率を計算すると、
関税率 =(341 ÷ 43.8)×100 ≈ 778%
となり、「700%超」という主張の根拠となっている。
ただし、現在では国際価格の上昇や円安の影響で輸入価格も上がっており、仮に1キログラムあたり100円とすれば、実効関税率は約341%に低下する。関税率は米価により変動するため、固定的に「700%」とするのは適切ではないが、完全に誇張とも言えない。
また、現実にはミニマム・アクセス枠外での商業的な輸入はほとんど存在しない。これは、341円という関税額が実質的な輸入抑制策として機能しているとの見方を裏付ける。
ミニマム・アクセス米の流通と用途
ミニマム・アクセス米は、国内市場ではほとんど流通していない。消費者が店頭で見かけることは稀である。主な用途は以下の通り。
1. 加工・業務用(飼料用を含む)
ミニマム・アクセス米の大部分は、せんべいや米菓、みりん、清酒、焼酎などの加工品、または外食産業や給食などの業務用として利用している。また、品質や需要のバランスによっては、家畜の飼料用に転用することもある。
2. 備蓄用
政府は、食糧安全保障の観点から、輸入米の一部を国家備蓄米として保管している。これは災害時や不作の年など、緊急時に供給を安定させるためのものである。
3. 援助用(政府開発援助=ODA)
政府は余剰米を国際機関を通じて援助物資として提供しており、人道支援の一環としての役割も果たしている。
日本の米価が高い背景
日本のコメは、海外と比較して極めて高い価格帯にある。2025年3月の全国のスーパーにおける平均価格は、5キログラムあたり税込4206円であり、同月の東京都区部では、うるち米(コシヒカリ以外)の小売価格が5キログラムあたり4557円に達している。
一方、海外における標準的な米の小売価格は、タイで約50〜65円/キロ、中国で120〜140円/キロ、韓国で300〜350円/キロ、アメリカで100〜280円/キロ程度となっており、日本のコメは2〜8倍以上の価格差がある。
その背景には、以下のような構造的課題がある。
● 小規模農家の多さ
1戸あたりの水田面積は平均1.5ヘクタールと小さく、機械化や効率化が進みにくい。
● 高齢化と労働力不足
労働集約型の米作りに対し、農村では高齢化と人手不足が深刻化している。
● 土地利用の制約
山地が多く農地が分散しており、農地の統合や転用にも制度的制約がある。
● 資材コストの高さ
肥料や農機の多くが輸入に依存し、円安や仕入規模の小ささがコストを押し上げている。
● 政策の影響
減反政策や価格支持制度により、安定供給を重視する一方で競争力強化が後回しにされてきた。
● 市場競争の欠如
JAを通じた流通が主流で、自由な価格競争が働きにくい構造となっている。
今後の方向性 「守る農業」から「稼ぐ農業」へ
現在、日本の農業は若者の米離れや高齢化による担い手不足といった構造問題を抱えており、関税による保護だけでは限界がある。
今後は、高品質な国産米を海外に売り込む輸出戦略や、農業の大規模化・効率化によるコスト削減を進め、「守る農業」から「稼ぐ農業」への転換が求められるだろう。
国際的にも評価される「おいしい日本米」を広めていくことは、農業再生の鍵となり得る。








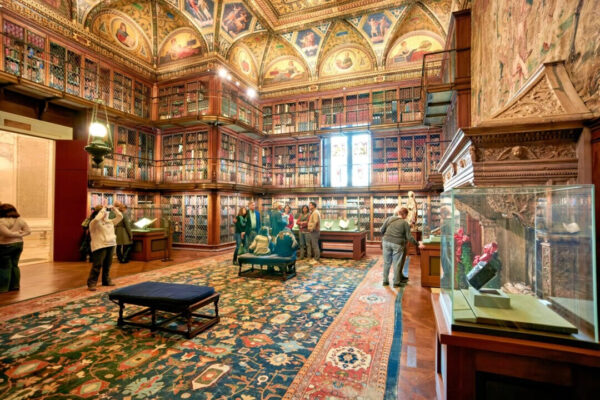

 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram




ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。