論評
トランプ政権による相互関税は、株式市場に混乱を引き起こし、アメリカの貿易相手国や国内の政敵からは「有害な貿易戦争だ」と批判を受けている。一部の党派的な経済学者は、トランプ政権の関税政策を、1930年の悪名高いスムート・ホーリー関税法になぞらえて批判している。同法は世界恐慌を長引かせたとされる。しかし、経済史家アミティ・シュレーズ氏をはじめとする経済学者らは、その原因はむしろルーズベルト政権のニューディール政策( 公共事業を行うことで失業者に仕事を与えた)にあるとしている。
しかし、関税政策に対する多くの反応には、それがトランプ政権のより大きな地政学的戦略にどのように貢献しているかについての理解が欠けている。
トランプ氏の関税は、政権の世界に対する全体的な地政学的アプローチの中で見るべきだ。このアプローチには、モンロー主義(アメリカ合衆国がヨーロッパ諸国に対して、アメリカ大陸とヨーロッパ大陸間の相互不干渉を提唱したことを指す)の再活性化、中東やウクライナでの関与縮小、ロシアと中国との三角外交、インド太平洋地域への戦略的軸足の転換などが含まれ、トランプ氏は経済を外交の手段として使っているのである。
このような発想は、アメリカ建国の父の一人、初代財務長官アレクサンダー・ハミルトンに遡る。ハミルトンは、保護主義ではなく、国内産業の育成を目的として関税を活用すべきだと主張した。議会は彼の提案の大半を採用し、それらは「穏健」と評されていた。
ベッセント財務長官はハミルトンを引き合いに出し、関税が歳入増加、国内の産業や雇用の促進、そして同盟国・敵対国の双方とのより公正な貿易交渉に役立つと説明している。ベッセント氏は関税をトランプ氏の外交政策目標と明確に結びつけ、「同盟国に自国の防衛費を増やすよう促すこと、アメリカの輸出品に対する海外市場の開放、違法移民の終息やフェンタニル密輸の阻止に向けた協力の確保、または軍事的侵略の抑止」といった目標を挙げている。
これは、経済政策を安全保障や外交の手段として活用するという考え方だ。、一部の学者や戦略家はこれを「地経学(ジオエコノミクス)」と呼んでいる。ハミルトンは、おそらく米国初の地経学戦略家とも言える。アメリカ初代大統領ジョージ・ワシントンが8年間の任期中に進めた現実的な外交路線は、ハミルトンの経済政策と表裏一体だった。
ワシントンは、ハミルトンの助言に従い、かつて敵国だったイギリスとの関係改善を目指した。英仏の紛争において、同盟国フランス側につくことを拒否した。
ワシントンの「告別演説」は、ハミルトンが推進した関税政策とともに、自国の利益を最優先する「アメリカ第一主義」の経済・外交方針の先駆けとされている。こうした考え方は、今のトランプ氏の経済・外交政策のモデルのひとつとも言える。ただし、これが唯一の歴史的なモデルというわけではない。
イギリスの歴史家ポール・ケネディ氏は、著書『大国の興亡』の中で、経済と外交の相互作用について見事に描いている。同氏はこのように説明している。
「軍事力の支えには通常、経済力が必要であり、富を獲得し保護するためには軍事力が必要だ。しかし、国家の資源の過度な部分が軍事に振り向けられ、富の創出が損なわれれば、長期的には国力の弱体化を招くことになる」
たとえば、ハミルトンのような経済戦略は、17世紀フランスの財務大臣ジャン=バティスト・コルベールにも見られる。コルベールは関税と税制を用いて国内産業の振興を図り、それを国家安全保障に結びつけた。結果としてフランスは海軍力を強化し、国内インフラの整備も実現した。ルイ14世の拡張主義的な外交政策が最終的に財政を疲弊させ、成果を損なった。
トランプ氏の外交政策は、むしろワシントンやハミルトンの現実主義に近く、コルベールを支えたルイ14世のような拡張主義とは一線を画している。トランプ氏の外交政策は、ルイ14世の政策というよりも、ワシントンやハミルトンの政策に似ている。
国家戦略における経済の役割は、第二次世界大戦においても決定的だった。アーサー・ハーマンは『自由の工場』で、アメリカが戦争に勝利できたのは、産業・技術・物資の驚異的な動員力によるものだと強調した。中国の造船能力がアメリカの200倍以上である今、トランプ氏が進める再工業化政策は、まさに急務と言える。
ハミルトン流の地経学的戦略は、冷戦の勝利を導いたレーガン政権の戦略にも見られる。レーガン政権は国家安全保障指令NSD-66およびNSD-75通じて、ソ連帝国を崩壊させる地経学・地政学的戦略を展開した。
具体的には戦略技術の貿易制限、エネルギー政策、軍拡(600隻規模の海軍)などを通じて、ソ連経済への圧力を強化した。ウィリアム・クラーク国家安全保障担当補佐官は、経済こそソ連の最大の弱点であり、それが決め手だったと指摘した。
冷戦終結後、戦略家エドワード・ルトワック氏は『アメリカンドリームの終焉: 世界経済戦争の新戦略』を著し、アメリカは地政学的戦略の手段として、地経学に重点を置く必要性を主張した。この本の提言は、中国の指導者たちには強く響いたようだが、アメリカの政策決定者たちは見過ごした。だがトランプ氏は、その重要性を本能的に理解しているように見える。
ルトワック氏は最近、Xに投稿した。
「無制限なグローバル化の追求によって大きく衰退したアメリカの産業を再建するためには、関税による保護が必要だ。確かに、それにより物価が上がる可能性はある。しかし、再工業化は不可欠だ。造船なしに海軍は成り立たない」と指摘した。
トランプ大統領の関税を単独で捉える人は、その真の目的を見誤っている。これは、「米国第一」の包括的戦略の一環だ。製造業を国内に回帰させ、海外における国家安全保障上の目標を支えるための産業基盤を強化する狙いがある。
CBSニュースによれば、世界各国の指導者はトランプ氏の関税政策を批判しているが、批判者を含む多くの指導者がトランプ氏との新たな貿易協定の交渉を模索している。というのも、「なぜアメリカ製品は関税を課され、アメリカは同等な関税を課さないのか」という疑問は、トランプ氏の主張に説得力を持たせる。
自由貿易とは、公正な貿易であるべきだ。トランプ氏は言葉通りに動く。アメリカが最優先なのだ。






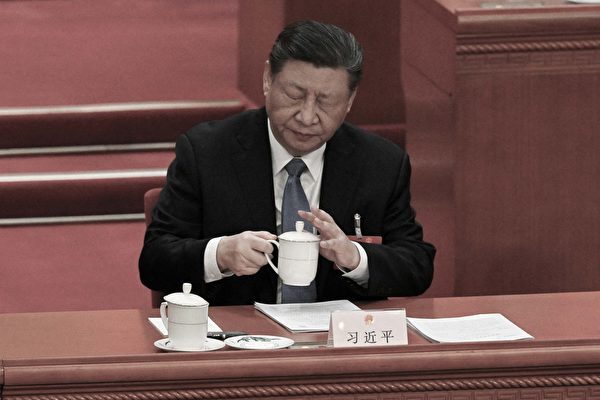



 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram




ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。